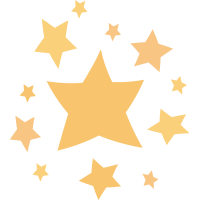3、窃盗罪の民事上の時効期間は?

窃盗は他人の財産を侵害する行為ですので、窃盗罪を犯すと刑事上の責任だけでなく、民事上の責任も発生します。
公訴時効が完成して刑事上の責任を負う可能性が低くなった後でも、民事上の責任が残ることもあります。
本章では、窃盗罪の民事上の時効についてみていきましょう。
(1)盗品の時効取得の期間は20年
他人の所有物を窃取した場合でも、民法上の「取得時効」が成立し、時効を援用することにより(民法145条)、自分の所有物となります。
取得時効が成立するまでの期間は、20年です(民法162条1項)。
ただし、取得時効が成立するためには「所有の意思をもって」「平穏に」かつ「公然と」占有を続ける必要があります。
盗んだ物であっても、その物に対する占有が平穏であること又は占有が公然であることは推定されますが、盗んだ物を隠し持っているような場合は、「平穏に」かつ「公然と」という要件を満たすかどうかが問題となります。
「平穏に」というためには、所有権者との関係で占有を取得または保持するために暴行や強迫を用いていないことをいうと考えられているため、盗んだときの行為態様やその後の保管状況等によっては「平穏に」とはいえない可能性があります。
また、「公然」とは、占有を取得または保持するために、特にこれを秘密にして他人の目にふれないようにしないことをいうと考えられているため、盗んだ物を隠し持ち続ける場合には「公然」といえない可能性があります。
すべての要件を満たさなければ取得時効の期間は進行しませんので、要件を満たさない状態で持ち続けていた場合は、いつまで待っても取得時効は成立しません。
(2)不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年
盗んで得た物は、民法上の「不当利得」に当たります。
不当利得とは、法律上の原因がないのに利得が生じた場合に、利得を得た受益者に対して、その利得によって損失を被った損失者にその利得を返還する義務を負わせて、受益者と損失者との間に財産上の均衡を図り、公平を回復しようとする制度です。
前述のような取得時効が完成しない限り、物を盗んだ受益者は物を盗まれた損失者に対して、その物を返還しなければなりません(民法703条)。
損失者の受益者に対する不当利得返還請求権は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき」又は「権利を行使することができる時から十年間行使しないときに消滅時効にかかります(同法166条1項)。
「権利を行使することができることを知った」というためには、「権利を行使することができる」ことと、権利の発生原因等を認識し、権利行使の相手方を認識することが必要と考えられています。
一般的に、「権利を行使することができる」とは、期限の未到来や条件の未成就のような法律上の障害がないことを意味すると考えられており、例外的な場合を除き、権利行使をできることを知らないというような事実上の障害があっても時効期間は開始します。
そうすると、損失者が受益者である犯人を知ってから5年、または受益者による犯行後10年で消滅時効にかかると考えられます。
取得時効よりも時効期間が短いですが、損失者から不当利得返還請求を受けた場合には、利息を付して返還しなければならないことに注意が必要です(同法704条)。
利息の算定に用いる法定利率は、民法改正に伴い2020年4月以降は年5%から年3%へ変更となりました(同法404条2項)。
(3)損害賠償請求権の消滅時効は3年
被害者から不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、盗品の弁償や慰謝料などの損害賠償を請求されることもあります(民法709条、同法710条)。
損害賠償請求権の消滅時効期間は、次のいずれかのうち早い方です(同法724条)。
- 損害および加害者を知った時から3年
- 不法行為の時から20年
「損害」を知った時とは損害の発生の事実を知ることであり、「加害者」を知った時とは、加害者に対する賠償請求が事実上可能な程度に知ったといえるかにより判断すると考えられています。
被害者が加害者の氏名や連絡先を知った時、又は加害者の氏名や連絡先を知らなくとも、賠償請求の相手方を具体的に特定して認識でき、調査すれば容易に氏名等が判明し得る状態に至った時には「加害者」を知った時といえる可能性が高いでしょう。
そのため、「損害および加害者を知った時」といえる状態になるまでの間は、3年の時効期間は進行しないため、犯行から20年が経過するまで損害賠償請求権は時効にかからないことになります。
(4)民事上の時効期間はリセットされることがある
民事上の時効は、時効が停止し得る公訴時効とは異なり、一定の事由があれば時効の「完成猶予」又は「更新」という効果が生じます。
時効の「完成猶予」とは、猶予事由が発生しても時効期間の進行自体は止まりませんが、本来の時効期間の満了時期を過ぎても、所定の時期を経過するまでは時効が完成しないこといいます。
また、時効の「更新」とは、更新事由の発生によって進行していた時効期間の経過が無意味なものになり、新たにゼロから進行を始めることをいいます。
ここでは、時効期間がリセットされるという意味で、時効の「更新」を中心に解説します。
時効期間がリセットされる主な事由は、以下のとおりです。
- 裁判上の請求等
- 強制執行等
- 承認
「裁判上の請求等」とは、裁判上の請求、支払督促、裁判上の和解・民事調停・家事調停、破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加のいずれかの事由をいい、これらの事由が生ずると、時効の「完成猶予」となり(民法147条1項)、その後、裁判手続において確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、完成猶予後に、時効期間が「更新」されます(同条2項)。
盗品の返還請求や損害賠償請求の裁判を起こされた場合、その時点で時効期間がリセットされます。
「強制執行等」とは、強制執行、担保権の実行、形式競売、財産開示手続の各事由が生ずれば、時効の「完成猶予」となり(民法148条1項)、その事由の終了時に時効期間が「更新」されます(同条2項)。
なお、仮差押え・仮処分によって時効が「更新」されることはありませんが、仮差押え等に引き続いて本案訴訟が提起された場合には、「裁判上の請求」にあたりますので、確定判決等により時効が「更新」されることになります。
盗品の返還請求や損害賠償請求の裁判を起こされて認容判決が確定したものの、盗品を返還しなかったり、損害賠償金を支払わなかったりしたことによって差押え等の強制執行の手続が行われた場合、再び、その時点で時効期間がリセットされます。
裁判外で被害者から内容証明郵便などで請求された場合は、「催告」に当たり、その時から時効の進行自体は止まりませんが、6ヶ月間を経過するまでの間は時効の完成が猶予されてしまいます(民法150条1項)。
また、裁判外で催告を受けた場合に、盗んだ物を「返します」、弁償金や慰謝料などを「支払います」などと答えた場合は「承認」に当たり、承認があった時から時効期間が「更新」されますので(民法152条1項)、注意が必要です。
4、窃盗罪で時効を待つのと被害者と示談をするのは、どちらが得策?

窃盗罪を犯してしまっても、刑事上及び民事上のそれぞれの時効が完成すれば、責任を負わずにすむということになります。
そうであれば、時効期間が経過するまで待とうと考える方もいることでしょう。
とはいえ、窃盗罪で時効が成立する可能性はどれくらいあるのか、刑事上の公訴時効の完成を待つのと被害者と示談するなどの対応を行うのと、どちらが得策なのかという点も気になることでしょう。
以下で解説していきます。
(1)時効が完成する可能性は低い?
窃盗罪で公訴時効が完成するかどうかはケースバイケースであり、可能性の高低を一概にいうことはできません。
一般論としては、被害額が軽微な窃盗事件であれば被害者が諦めたり、被害届を出されても警察が積極的に動かなかったりして、やがて公訴時効が完成する可能性もあります。
逆に、被害額が大きい場合や被害額が小さくても同種の犯行を何件も繰り返しているような場合には、警察も捜査に本腰を入れることが多いので、公訴時効が完成することは難しいと考えるべきです。
結論として、どのような事案でも100パーセント、公訴時効が完成するとは言い切れません。
そうである以上は、「いつか捜査が始まるのではないか」「もしかしたら取調べを受けたり、逮捕されたりするかもしれない」という不安や罪悪感を抱えながら長期間を過ごすよりも、早期に被害の回復に努める方が基本的に得策であるといえます。
(2)示談すれば不起訴や減刑の可能性もある
たとえ窃盗罪という過ちを犯してしまっても、早期に適切な対処を行えば処罰を免れる可能性はあります。
被害者に対して、被害届を提出する前に犯行を申し出て真摯に謝罪し、被害弁償をするなどして示談を成立させれば、刑事事件とならず穏便な解決も期待できるでしょう。
被害届が提出された後でも、示談が成立していれば、検察官が起訴猶予の判断をして不起訴処分となる可能性もあります。
仮に起訴されたとしても、量刑の際に示談の成否が考慮されることが多いので、低額の罰金刑や執行猶予付き判決などの比較的軽い処分が期待できることも多いでしょう。
(3)自首によっても不起訴・減刑の可能性が高まる
窃盗罪の場合、被害者が誰なのかが分からないという場合もあるでしょう。
そんなときは、捜査機関に対して自首することが考えられます。
法律上、自首は裁判所の裁量による刑の減軽事由とされていますので(刑法第43条1項)、仮に起訴された場合でも、自首が成立していれば軽い処分となる可能性があります。
それだけでなく、自首をすれば逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないと判断されやすいので、逮捕を回避することにもつながるでしょう。
また、自首することによって反省の態度を示すことにもなるでしょう。
自首した後、警察官または検察官から被害者の連絡先を教えてもらうことができれば、示談交渉を始めることができます。
示談が成立すれば、不起訴処分又は起訴後の減刑の可能性がさらに高くなります。
配信: LEGAL MALL