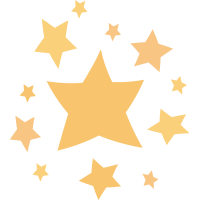3、具体例でみる「養育費算定表」を使った養育費の計算方法

(1)夫婦共に給与所得者、子ども1人の場合
この場合は、子どもが0歳~14歳であるか、15歳以上であるかによって使う表が異なります。
子どもが0歳~14歳であれば、「子1人表(0歳~14歳)」を使い、15歳以上であれば「子1人表(15歳以上)」を使います。
子どもが10歳であるとして、義務者の年収が500万円、権利者の年収が100万円であるとすると、下の図のように、「4万円~6万円」の枠の上の方になります。
この場合には、おおむね、5万円~6万円程度が養育費として相当ということになります。
(2)夫婦の一方が自営業者、他方が給与所得者、子ども2人の場合
まず、子どもの年齢を確認します。
仮に、上の子(第1子)が15歳、下の子(第2子)が10歳であるとすると、「子2人表(第1子15歳以上、第2子0歳~14歳)」の表を使うことになります。
次に、お互いの年収を確認します。
仮に、義務者が自営業者で、養育費の算定の基礎となる年収が500万円、権利者が給与所得者で年収100万円であるとすると、義務者の年収は養育費算定表の「自営」の欄を、権利者の年収は「給与」の欄を見て、交差する部分を確認します。
義務者の「自営」の欄をみると、500万円に対応する数字がありませんが、「512万円」と「496万円」の間と考えられますから、そこから横に線を伸ばし、交差する部分を見ます。
そうすると、下の図のように、「10万円~12万円」の枠の上の方になります。
この場合には、おおむね、11万円~12万円程度が養育費として相当ということになります。
(3)妻(又は夫)が専業主婦(主夫)、子ども1人の場合
一方が専業主婦(主夫)の場合、年収を0円として計算すべきでしょうか。
ケースバイケースではありますが、0円として計算することは少なく、パート程度の見込み収入(100万円~120万円)があるものとして、計算されることが多いです。
仮に、子どもの年齢が15歳、義務者が給与所得者で年収700万円、権利者が専業主婦(主夫)であるとすると、「子1人表(15歳以上)」を使って、下の図のように、「8万円~10万円」の枠の中くらいになります。
この場合、おおむね、9万円~10万円が養育費として相当ということになります。
(4)養育費計算ツールを使う
養育費算定表は、使い方が分かれば、ある程度、誰でも使うことができます。
ただ、表の選択や、給与の見方(給与所得者か自営業者か)を間違えると、間違った結論に至ってしまうという難点もあります。
また、わざわざ表をダウンロードして、線を引いてみてといった作業自体、面倒ということもあります。
現在では、子どもの人数、年齢、お互いの年収、給与所得者と自営業者の別を入力すると、養育費算定表上の養育費の枠が自動的に計算される便利なツールがあります(養育費計算ツール|弁護士による離婚相談ならベリーベスト法律事務所 (vbest.jp))。
こうしたツールを使って計算すると、簡単に、養育費の額を計算することができます。
4、「養育費算定表」からの修正が必要なケース

(1)住宅ローンを支払い続けるケース
たとえば、住宅ローンで自宅を購入した後、離婚することになり、権利者が子どもと一緒に自宅に住み続けることが予定されているとします。
他方、住宅ローンの名義は義務者であり、義務者が住宅ローンの支払を続けることが予定されているとします。
義務者が住宅ローンの支払を続ける場合、義務者は、権利者の生活費の一部を負担していることになります。
養育費算定表は、お互いが、お互いの生活費を負担することを前提に作られていますから、修正が必要です。
修正の方法は幾つか考えられますが、よく用いられる方法は、権利者の年収に応じた住居費相当額を、養育費の額から差し引くという方法です。
たとえば、3の(1)で挙げた、子どもが10歳、権利者・義務者共に給与所得者、義務者の年収が500万円、権利者の年収が100万円であるとすると、おおむね、5万円~6万円程度が養育費として相当ということになります。
次に、養育費算定表では、年収に応じた住居費を次のように考えています。
年収
住居費
~199万円
2万2247円
~249万円
2万6630円
~299万円
3万5586円
~349万円
3万7455円
~399万円
4万5284円
~449万円
4万6562円
~549万円
5万5167円
・・・
・・・
100万円に対応する住居費相当額は2万2247円ですから、約2万円と考えて、上記の5万~6万円から2万円を差し引き、3万~4万円が養育費として相当ということになります。
(2)生活費の一部を負担しているケース
たとえば、離婚をした後も、義務者が、子どもの携帯代や権利者の自宅の電気水道代を支払続けるという場合があります。
同居中に、子どもの携帯代や、自宅の電気水道代の引き落とし先を義務者の口座にしている場合には、引き落とし先口座を変更する手間などから、こうした取り決めをすることが少なくないようです。
このように、義務者が権利者の生活費の一部を負担している場合には、養育費算定表で計算された養育費の額から、その実額を差し引くという処理をすることが多いです。
たとえば、3の(1)で挙げた、子どもが10歳、権利者・義務者共に給与所得者、義務者の年収が500万円、権利者の年収が100万円であるとすると、おおむね、5万円~6万円程度が養育費として相当ということになります。
そして、義務者が、子どもの携帯代月額5000円を毎月負担しているとすると、上記5万円~6万円から、5000円を差し引いた4万5000円~5万5000円が養育費として相当ということになります。
(3)私立大学の学費や留学費用が問題となるケース
養育費算定表では、標準的な公立高校の学費までは考慮されていますが、私立大学の学費や留学費用は考慮されていません。
そこで、私立大学や留学費用など、算定表を超える学費が必要となる場合、上乗せを検討することになります。
上乗せの計算方法については、様々な考え方がありますが、比較的簡単なものは、標準的な公立高校の学費を超過する分について、双方の基礎収入割合で分担するというものです。
たとえば、義務者の年収が800万円、権利者の年収が100万円、子どもが19歳で私立大学に進学しており、私立大学の学費が年間100万円必要であるとします。
まず、養育費算定表には19歳の表がありませんが、子どもが18歳であるとして計算します。
養育費計算ツール(養育費計算ツール|弁護士による離婚相談ならベリーベスト法律事務所 (vbest.jp))を使って計算すると、10万円~12万円が養育費として相当という結果になります。
次に、双方の基礎収入についてみます。
基礎収入とは、簡単にいえば、年収の中で生活にあてられる金額のことをいいます。
養育費算定表では、基礎収入を、年収に応じた割合(基礎収入割合)で計算する方法を採用しています。
給与所得者の場合の基礎収入割合は次の表のとおりとなっています。
収入(円)
割合(%)
0~75
54
~100
50
~125
46
~175
44
~275
43
~525
42
~725
41
~1325
40
年収800万円と年収100万円の基礎収入についてみると、年収800万円の基礎収入は800万円×40%で320万円、年収100万円の基礎収入は100万円×50%で50万円と計算できます。
最後に、超過分の分担を計算します。
養育費算定表では、標準的な公立高校の学費として年間約26万円が考慮されています。
そこで、超過分は、私立大学の学費100万円-26万円=74万円です。
そして、これを双方の基礎収入割合で分担します。基礎収入比は、義務者:権利者=3.2:1ですから、おおむね、義務者:権利者=56万3800円(月約4万7000円):17万6200円(月約1万4680円)となります。
したがって、義務者の上記10万~12万円に、私立大学の学費の分担額である4万7000円を加算した、14万7000円~16万7000円が養育費として相当と計算できます。
配信: LEGAL MALL