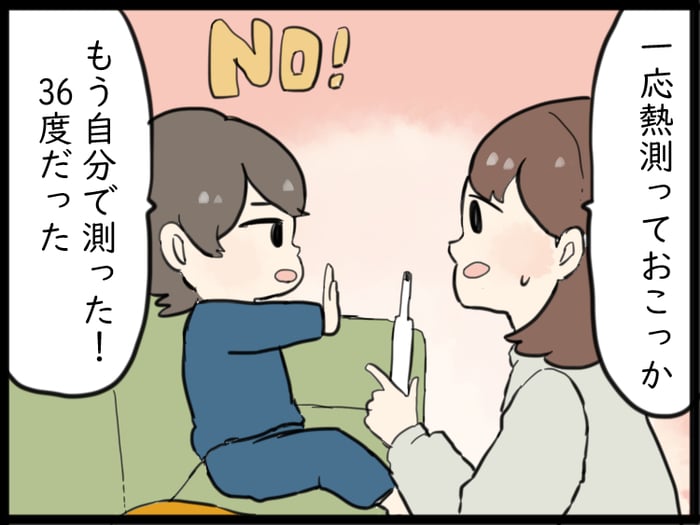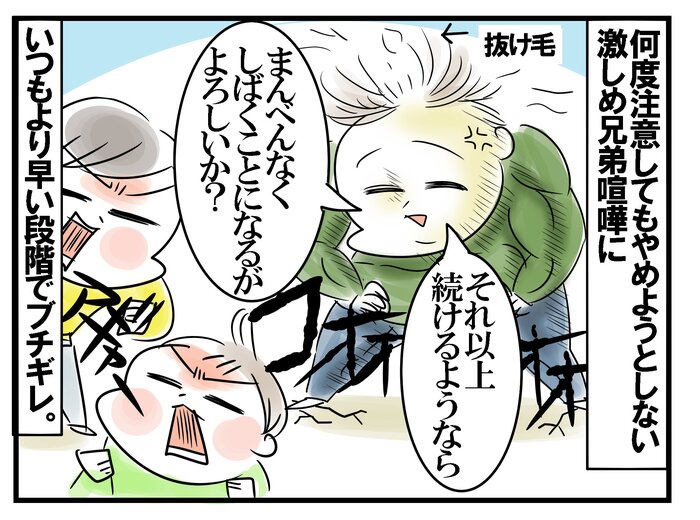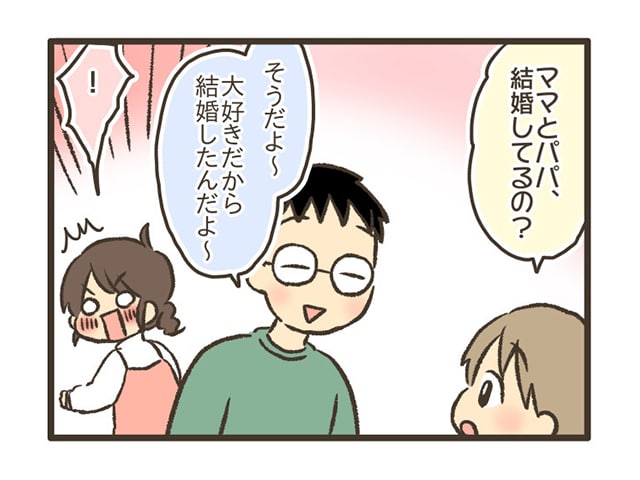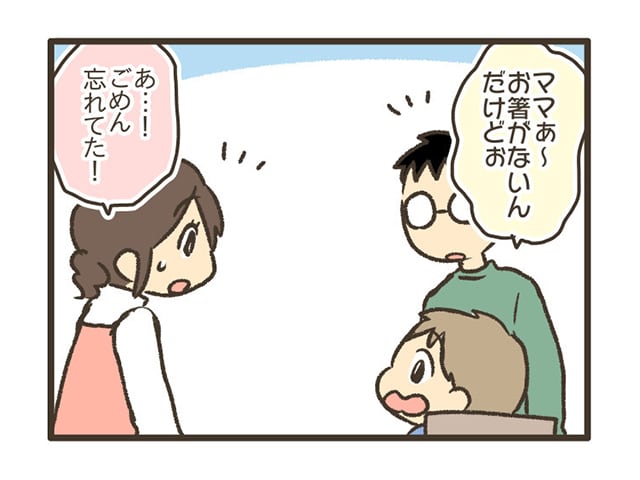1998年5月、私たち家族が暮らしていたインドネシアで大暴動が起きた。死者は千人を超え、激しい略奪と破壊が街を襲った。
「戦争が起きたのかい?」
日本でニュース映像を見た母親が大慌てで国際電話を掛けてきた。
ガソリンスタンドが爆発して黒煙を上げ、確かに戦争みたいだ。在留邦人は先を争うように日本へと緊急帰国していく。臨時便が何便も飛び、さらに自衛隊機による邦人輸送すら検討されていた。
そんな異常事態だったが、私たち家族はインドネシアに留まることにした。
「インドネシアは私の愛する母国。こんな酷い状態だからこそ、私は残りたい。母国を見捨てて外国に逃げることなどできない。」
インドネシア人である妻の愛国心を尊重したかったからだ。また、私たちの住む郊外までは暴動は及ばないという妻の判断を信じることにした。

公開 2019年01月10日
海外で暮らす家族を襲った暴動。沈むわたしを救ってくれた子どもの歌声<第二回投稿コンテストNo.43>
5,295 View1998年、道産子さん家族が暮らすインドネシアで大規模な暴動が勃発。生命の不安、経済的な不安を感じながら時間だけが過ぎていく日々でしたが、一方でパパと一緒に遊べることに大喜びの子どもたち。そんな子どもたちと過ごすことで、見失いかけていた大切なことを思い出したそうです。
出典:http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10272002069
※ この記事は2024年10月06日に再公開された記事です。
#キーワード

連載「第二回 記事投稿コンテスト 『驚いたこと』」
#43
 コノビー記事投稿コンテスト
コノビー記事投稿コンテスト
 コノビー記事投稿コンテスト
コノビー記事投稿コンテスト
おすすめ記事