
「ある男」「マチネの終わりに」ほか映画化作品も多い小説家・平野啓一郎が今から地続きの少し先の将来を舞台にした小説「本心」が、石井裕也監督×池松壮亮主演で映画化された。
大雨で氾濫する川べりに立っていた母(田中裕子)を救出しようとして、1年間昏睡状態に陥ってしまった朔也(池松壮亮)。目が覚めると母は亡くなっており、生前に“自由死”を選択していたと告げられる。母の本心をどうしても知りたい朔也は、幼なじみの岸谷(水上恒司)の紹介でVF(ヴァーチャル・フィギュア)開発者の野崎(妻夫木聡)と出会い、「AIの母を作ってほしい」と依頼する。そのデータ集めの一環で、生前の母の友人だったという三好(三吉彩花)と知り合う朔也。ほどなくして“母”が完成するが、自分の知らない一面を見せ始める彼女に朔也は困惑し‥‥。
テクノロジーの急速な進化で、AIの脅威が現実のものとなった2024年。池松壮亮と三吉彩花に、作品の舞台裏やこれまでに観賞してきた映画作品を通して感じる、「テクノロジーと私たち人間」について伺った。
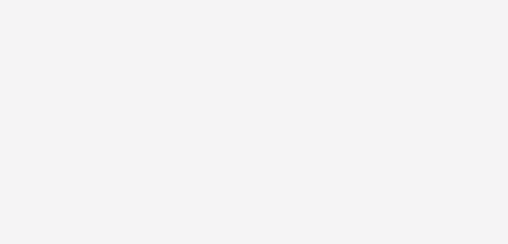

――池松さんは本作に対して「なるべく早く映画化しないといけないと思った」と仰っていましたよね。改めて、その理由を伺えますでしょうか。
池松 2020年に原作に出合った時は、まだ少し先の未来として距離のある場所から読めている感覚がありました。その後ChatGPTの世界的な普及があり昨年はAI元年と呼ばれる年になりました。テクノロジーが急速に進化し、化学的なところからぐっと我々の生活的なところ、日常に寄ってきているような体感がありました。このままいくと「2040年はもっと違う世界になっているんじゃないか」となり、2022年の末に映画の時代設定が「2025年前後」と変更になりました。完成してからもAIやバーチャルに関する専門の先生方に今作を観ていただいたところ、原作共に的確に未来を予測していて、今年公開がベストなタイミング。来年の今頃だと少し遅いかもしれないという声をいただきました。
三吉 原作を読んだ際、テクノロジーの部分はもちろん、現実空間の描かれ方としてもものすごくしっくりきて「こういう風に思う部分はたくさんある」と感じました。今の日本でいうと「自由死」のように自分で選択する部分の実感はあまりないかもしれませんが、世界で見たときに決して荒唐無稽なものではありませんし、2025年以降の今後5年の社会を想像した際、いまこの映画を世の中に向けて公開していくことが突発的には思えませんでした。このタイミングで実写化することに、非常に意味がある作品だと感じます。


――AIと俳優でいうと、2023年にはハリウッドでストライキが発生しました。その争点の一つが「AIによる権利侵害や活躍の場が奪われることへの対処」でしたね。
池松 AI普及に対するルール化が追いついていない中で、米俳優組合はとても勇気ある決断でストップをかけました。AIの脅威だけが問題ではなく、資本主義のシステムにおいて、競合がそれをやれば同じことをやる以外に手がなくなるということがどんな問題においてもこの世界の掟だと思います。そのことがAIよりも厄介だと思います。ルール化や法整備が何より必要ですし、当然このことはアメリカだけでなく全世界的な問題なので、同じ危険が迫っていると感じています。日本には俳優やスタッフの権利を守る組合のようなものはないので、議論がなされず各々の考え方で、目の前の利益重視に進んでしまわないか心配です。俳優だけではなく、AIの進化によって人間の身体性が脅かされていくことについても心配です。AIと人間がどう共存していくのか、これからの時代につきまとう問題だと思っています。
三吉 一方で、自分が普段からAIというものに日常的に触れてきてしまっている実情もあり、ポジティブに活用される場合もあるため難しいですよね。私自身はこの作品と出合うまでどこか他人事のような意識もありましたが、原作や脚本を読んだり、現場で演じていったりするなかで向き合い方が変わってきました。



――劇中、おふたりがVRゴーグルをつけてAIの母と対話するシーンがありますよね。実際に演じられて、どのような感覚を得ましたか?
池松 本作ではVRの対比として「禅」を取り入れていますが、それに近い感覚で、非常に自分に向いている行為のようにも感じました。AIもそうですが、つまるところは人間の欲望の歴史だと思います。自分だって脳内で何回も亡くなった大切な人を蘇らせています。目の前に蘇った母が出現するシーンに関してはあまりに純粋な喜びと、それが本物の母ではない自分が創ったものというあまりに複雑な感情で心が震えるようでした。そうしたこれからの人間の欲望や哀しみに触れるような体験でした。
三吉 本作は三好にとって「人に触れられない」状態から一歩踏み出していくさまを描いた作品でもあり、私自身も自分の本心と向き合い、撮影期間中ずっと自己探求を続けながら臨んでいました。そうした意味では、いま池松さんがおっしゃったように、想像の中の世界で三好として演じてはいますが、すごく自分に向かっていたように思います。一方で、セリフの言い方や動作一つにしても繊細に意味が含まれてしまうように感じて、VRゴーグルをつけるシーンではより感覚を研ぎ澄ませていました。








――身体性や肉体性は、リアル・アバターほか本作の大きなテーマの一つでもありますね。
池松 撮影は2023年でしたが、僕にはまだ実存する肉体があり、自分の手で世界に触れていくことができます。ただこの先、テクノロジーの進化によって人間が肉体を手放していく可能性も否定できません。そうした長い歴史の現在地にある人間という生きものの記録を今作に閉じ込めるべく、テクノロジーの対比として、生身の身体から生まれる感情の余白でスクリーンをいっぱいに埋めていくことを目指したいと思っていました。朔也として、残された自身の身体にすがりながら生きることを選択しているような感覚がありました。
――自分自身、『A.I.』や『her/世界でひとつの彼女』のような映画を観ていくなかでこれからのテクノロジーや未来について学んできたのですが、おふたりはいかがですか?
三吉:私は『本心』の前に『レディ・プレイヤー1』を見返しました。あの作品はもっとファンタジー色が強く、仮想空間上のゲームで競い合って‥‥というものですが、経済格差や上下関係を描いてもいて、仮想空間のなかでの喜びや虚しさとどんどんかけ離れていく自分自身の本心であったり、アバターを通してでなく実物に会いたいと思う部分がリンクするようにも感じます。
ちなみに、私が普段観ている映画はアクション映画が多いです。そして、女性がカッコよく自立している作品。ヒーローでもダークヒーローでも、魅力的な女性がドンと立っている作品は観てしまいます。元々はクリステン・スチュワートが大好きで、『チャーリーズ・エンジェル』はお気に入りの一つです。そのほか、衝撃的すぎてものすごく強い女性に見えたのが『ミッドサマー』のフローレンス・ピューです。レイトショーで一人で観に行き、後味が悪すぎてどうしようと思ったほどでしたが、フローレンスの演技力もあって、奇妙な世界観の中で彼女がどんどん変化していく姿が強烈に印象に残りました。


池松 AIを描いた映画として近年最も記憶に残っていたのは『her/世界でひとつの彼女』です。いまから10年前に「AIが恋人になる」を描いた点で画期的でしたが、そこから時が経ち生命の根源的な存在にあたる“母”を“蘇らせる”ところまで来たというのは時代の流れとしても興味深く、その意味でも今作の描いていることは凄いなと感じます。
AIや近未来というものに関しては自分も題材としてとても興味があった、探していたような感覚があります。人間を見つめる上で、過去や未来を通っていまを語ることは映画や物語にできる特別な表現だと思っています。
――池松さんは本作の宣伝クリエイティブにおいても多くのアイデアを出されていたと伺っていますが、改めて想いを伺えますでしょうか。
池松:自分の思い通りにというつもりはありませんし大抵そうはなりません。宣伝に関してそこまで意見しているつもりはありませんが、システマチックなものや大きな声を持つ者の総意で決定するものの中にも誰かがしっかり考えて話し合って出さなければならないことは絶対にあります。そのことは観客に必ず伝わるものだと思います。誰かがやってくれる、自分には関係がないではなく、映画を作ることも伝えることも同じくらい大切なことなので、思ったことはちゃんとお伝えするようにしています。
これは宣伝に限らずですが、「伝える」ということがあまりにも雑に扱われていると感じています。映画を作ることと映画を伝えるという行為は本来同義であるはずです。目の前の人にも大衆にもですが、伝えるということの中に映画や現代社会が失ってきたことはあるような気がしています。
三吉:今回、池松さんと初めてご一緒してお芝居以外の部分でも一つひとつ丁寧に、大切にコミュニケーションを図って構築されていく姿を目にしてきました。それは石井監督もそうですし、様々なキャストが丁寧に向き合った部分が反映されている作品だと感じます。そうしたクリエイティブへの向き合い方を、本編を通して少しでも感じ取っていただけたら嬉しいです。
文 / SYO
撮影 / 岡本英理


映画『本心』
工場で働く青年・朔也は、同居する母から仕事中に電話が入り「帰ったら大切な話をしたい」と告げられる。帰宅を急ぐ朔也は、途中に豪雨で氾濫する川べりに母が立っているのを目撃。助けようと飛び込むも重傷を負い、昏睡状態に陥ってしまう。目が覚めたとき母は亡くなっていて、生前“自由死”選択していたと聞かされる。また、ロボット化の波で勤務先は閉鎖。朔也は、唯一の家族を失くし、激変した世界に戸惑いながらも幼なじみの岸谷の紹介で「リアル・アバター」の仕事を始める。仮想空間上に任意の“人間”を作る「VF(ヴァーチャル・フィギュア)」という技術を知った朔也は、「母は何を伝えたかったのか?どうして死を望んでいたのか?」を解消したい気持ちから、なけなしの貯金を費やして開発者の野崎に「母を作ってほしい」と依頼するが‥‥。
監督・脚本:石井裕也
原作:平野啓一郎「本心」(文春文庫 / コルク)
出演:池松壮亮、三吉彩花、水上恒司、仲野太賀、田中泯、綾野剛、妻夫木聡、田中裕子
配給:ハピネットファントム・スタジオ
©2024 映画『本心』製作委員会
公開中
公式サイト happinet-phantom.com/honshin



