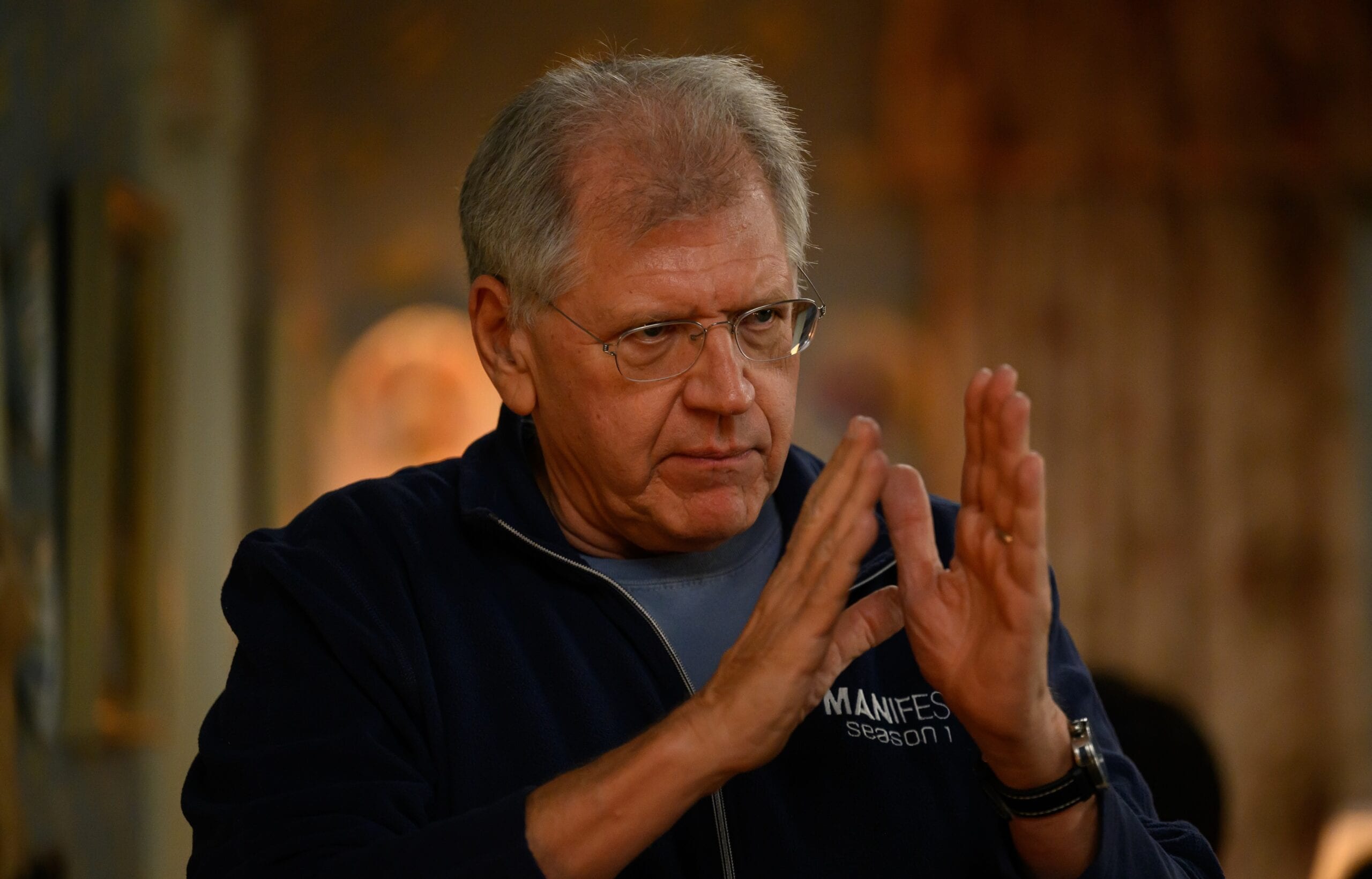昆虫よりも近い!?クマムシの親戚は“有爪動物”だった
クマムシ(緩歩動物)といえば、しばしば虫やクモといった節足動物の一種と誤解されがちですが、実は分子系統解析を総合すると、オンシフォラ(有爪動物)のほうがより近縁だとする説が有力です。支えとなるのが、先述の「タクトポダ(Tactopoda)仮説」。
クマムシとオンシフォラが先に分岐し、その後になって節足動物が大型化と多様化の道を進んだと考えられています。
クマムシとオンシフォラには節足動物とは異なる相似点も複数報告されています。
たとえば、胚発生の初期段階や、体節形成を制御する遺伝子の発現パターンが比較的類似しており、両者がパナルトプロダの中でも近い位置にあることを示唆しているのです。
これに対して、節足動物は外骨格や関節構造の発達など、クマムシやオンシフォラからは遠ざかった形質を多く獲得してきました。
昆虫やクモなどの節足動物は身近で目につきやすい一方、オンシフォラは主に熱帯・亜熱帯の森林に生息し、体長が数センチに及ぶ柔らかい“ベルベットワーム”のような姿をしています。日本では自然分布がほとんど報告されていないため、一般にはあまり馴染みがない生き物です。
しかし、「有爪動物のほうが実はクマムシに近縁だった」という事実は、進化の意外性を象徴する話題でもあり、さらにオンシフォラは独特の粘着液を射出して獲物を捕らえる狩りの方法など、とても興味深い生態を持っています。
クマムシとオンシフォラの意外な関係を知れば知るほど、エクディソゾアという脱皮動物の多様性に驚かされることでしょう。
(広告の後にも続きます)
奇妙な化石が語る“パナルトプロダ”の正体:クマムシとオンシフォラの起源
クマムシ(緩歩動物)とオンシフォラ(有爪動物)、そして節足動物をまとめて含むグループが「パナルトプロダ(Panarthropoda)」です。
これはカンブリア爆発期(およそ5億数千万年前)に多様化したエクディソゾアの中でも、体節や脚の形成など、より複雑な構造を獲得した一群と考えられています。
化石記録によれば、「ロボポディアン(Lobopodian)」と呼ばれる柔軟な体と複数の短い脚を持つ生物が、パナルトプロダの初期段階を映し出している可能性が高いとされ、Hallucigenia(ハルキゲニア)やAysheaia(アイシア)などはその代表例です。
これら初期のパナルトプロダは、硬い外骨格や関節足を獲得する以前の姿で、柔らかい体と短い脚が特徴的でした。クマムシは極端な小型化とシンプル化を経た結果、原始的かつ柔軟な構造をさらに突き詰め、極限環境へ適応する独自の進化路線を進んだとみられています。
一方、オンシフォラは森林や落葉層で“スライムガン”とも呼ばれる粘着液を使った捕食行動に特化し、節足動物は頑丈な外骨格と多数の関節による高い運動性能を武器に海・陸あらゆる場所へ爆発的に多様化しました。
このように、カンブリア期の爆発的な進化の中でパナルトプロダという枠組みが生まれ、それぞれが大きく分かれていったわけですが、クマムシの驚異的な耐久力も、こうした古代から続く遺伝的基盤があってこそ磨き上げられたと考えられます。
極小ながら驚くべき生命力を持つクマムシが、実は古代の化石生物と繋がるルーツを持っていると知ると、進化の不思議さとロマンを改めて感じずにはいられません。