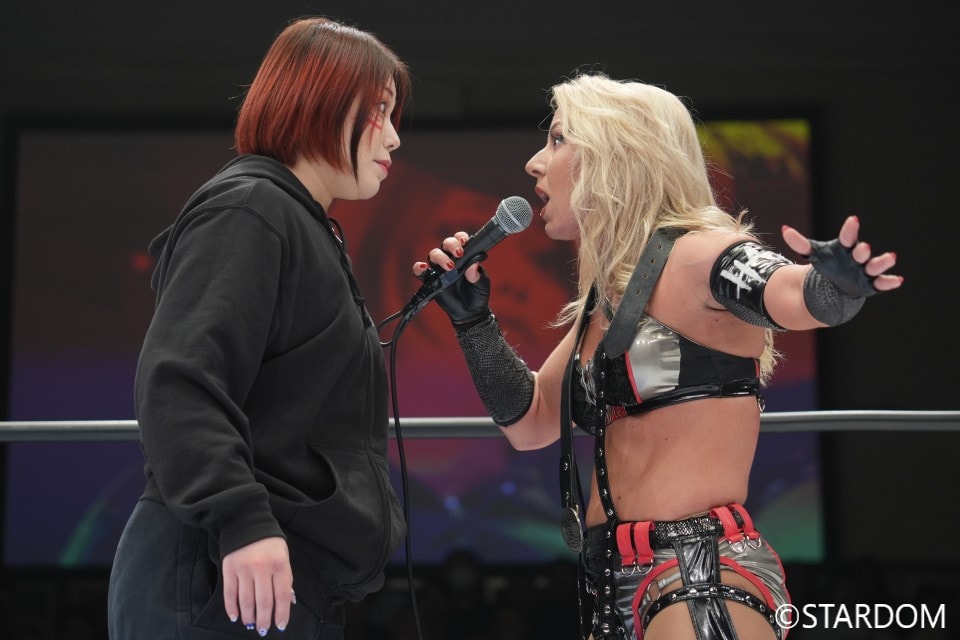スーパーGTの今季2度目の公式テストとなる富士テスト。2023年のGT300クラスチャンピオンである埼玉Green Braveにとっては、今季初見参となった。というのも彼らは、2週間前の岡山テストにエントリーしなかったのだ。
その理由について近藤收功エンジニアを直撃すると、「簡単に言うと、カウルが間に合いませんでした」と苦笑する。GRスープラ GTの車両開発に遅れがあったとのことだが、さらに詳しく話を聞いた。
「主に変わったのはカウルですが、変わっていないのはルーフとドアくらいですかね」
そう語った近藤エンジニア。元々は、今季からひとまわり小さくなるフロントタイヤ(※GT300規定車両を対象に、タイヤサイズが330/710 R18から300/680 R18に)に合わせた周辺の開発のみを進める予定だったというが、昨年9月のSUGO戦、雨の公式練習でクラッシュして車両が大破したことにより、計画を改めることになった。
「フロントのチンスポイラー、カウルから、リヤフェンダー、ディフューザー、トランク、ウイング……全部損傷してしまいました」
「スペアパーツのあるものはスペアに交換したのですが、そうなるともう1セットスペアを作る必要がありますよね。その時点で翌年の小径タイヤ変更に伴う(車両フロント周りの)風洞実験をやろうとしていたのですが、前から後ろまで全部壊れてしまったのであれば、今一度見直しをして全部(風洞実験を)やっちゃおうということになりました。(当時の仕様は)年数も経っていましたから、お金をかけてもう1セット作るのであれば新しいものを作ろうと」
このように、全面的な風洞実験によって開発期間が伸びることになったGreen Brave。これまでは自社ブランド“Syms”でモータースポーツ活動も展開する矢島工業の風洞を間借りしていたが、同社の風洞が移転することに伴い当面使えなくなってしまうというハプニングも相まって、パーツの納期はさらに遅れることになった。なお、現在は別の風洞施設を使っているという。
今後のBoP(性能調整)を気にしてか、近藤エンジニアはアップデートのコンセプトや期待されるパフォーマンスについては積極的に言及しなかった。いずれにしても、岡山テストを欠席したことで、タイヤサイズ変更の影響を確かめられていない。そういう意味でも、「だいぶ後れをとっている」と語る。
「(一般論的には)タイヤが小径化すると面圧が強くかかるのでウエット路面でのグリップやウォームアップが良くなるというメリットがありますが、接地面積が減りタイヤの摩耗が厳しくなるというデメリットもあります。ただうちは何のデータも取れていないので、このコメントにも意味があるかどうか……」
「タイヤのたわみも変わってしまうので、ブレーキ性能やセットアップにも影響が出てきます。そこら辺をしっかり掴んでいく必要がありますが、だいぶ後れをとってしまっています。ジオメトリーやアンチダイブ、アンチリフトの設定、ロールセンター等の設定など、しっかりベースを決めて、開幕までに戦えるクルマにするのが目標です」
近藤エンジニアが言及した通りタイヤサイズの変更でタイヤへの攻撃性が変わる可能性があるため、Green BraveをはじめとするGT300のブリヂストン勢が得意とするタイヤ無交換作戦にも影響が出る可能性がある。そのため、昨年はタイヤ無交換勢が猛威を振るった開幕戦岡山における作戦も、レースウィークの練習走行が終わるまでは全くの白紙になりそうだ。
「ブリヂストンさんにもできることをやってもらっていますし、チームとしても耐摩耗性に対してセットアップでできることはします。その上でタイヤ交換にメリットがあるのであれば交換するし、無交換しなきゃいけないシチュエーションなら、無交換でいきます」
「ただ(戦略の判断は)簡単じゃないですね。タイヤのデグラデーション(性能劣化)、無交換のピットストップでどのくらい後ろに回るのか、あとはコース上での抜きやすさ、クリーンエアで走れるかどうか、色々なところを考えて組み立てないといけません」
「今までは過去の実績を基に『今回はもう無交換だろう』とある程度の予測ができたのですが、今はそれが全くありません。作戦が決まるのは岡山戦の練習走行の後になるでしょうね」