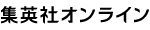新宿駅から2駅、駅から徒歩4分という好立地にもかかわらず、相場に比べて格段に安価なマンションがあった。マンション自治を行なう理事会のメンバーは約25年間ほとんど変わらず、増え続ける謎のルール、彼らの独裁体制は年々強化され、一部では「渋谷の北朝鮮」とも呼ばれ…そんな状況からマンション自治を取り戻すため、立ち上がった住民の4年にわたる闘争を取材しまとめた『ルポ 秀和幡ヶ谷レジデンス』が刊行された。著者でノンフィクションライターの栗田シメイさんに話を聞いた。
フライデーで最初に取材するときは乗り気ではなかった
「東京・渋谷区の一等地にとんでもないマンションがある」
全ては栗田さんが受けた一本の電話から始まった。
“ネタ元”でもある業界の裏事情に詳しい不動産会社の高田(仮名)は「独裁的な管理組合の謎ルールの数々に、住民が困り果てている」「不動産業に関わる者として、この手の話は許せない」と言ってきた。
警察や消防署、都議会議員や弁護士、行政などあらゆる機関に相談してもまともに取り合ってくれない。その状況を打破するために高田はマンションの住人や管理組合に取材した記事を書いてほしいと栗田さんに依頼してきたのだった。
住人から話を聞くと、マンション敷地内には54台の防犯カメラが設置されており、「24時間行動を監視されているようなもの」と語る者もいた。
また「理事長を筆頭とした特定の理事たちが、過半数の委任状を盾に総会での議決を独占してやりたい放題している」とも言われ、実際に管理規約にはない彼らが定めた、以下のような謎ルールがどんどん追加されていた。
・身内や知人を宿泊させると転入出費用として、10,000円を支払わなければならない
・平日17時以降、土日は介護事業者やベビーシッターの出入りを禁じるできない
・給湯器はバランス釜のみで、浴室工事は所有者でもさせてもらえない
・引越しの際に荷物をチェックされる
これらは謎ルールの一部にすぎないが、他の同ブランドマンションと比べると、その相場は格段に安価だった。これは“何か”あると思い、栗田さんは取材を進めることになる。
そして2020年8月14日発売号の写真週刊誌「FRIDAY(フライデー)」に「渋谷区の一等地マンションで、住民vs.管理組合の信じられないトラブル勃発中」というタイトルがついた記事が出た。
「フライデーで最初に取材したときは訴訟リスクもありましたし、住民と管理組合のどちらかに寄った記事になってしまう可能性が高い。くわえて労力もかなりかかるということもあって、はじめは前のめりではなかったです。
僕自身は極力書き手の色とか意思を消した方がいいと思っていて、取材して書くということは何かを断罪するとかではなくて、事実や起きていることを提示すべきという考え方です。
このレジデンスで起きていたことが常軌を逸していたので、できるだけ素材を活かしながら、会社や組織の中にいる人にも共感しやすいように、普遍性を持たせることを意識しました」(栗田シメイさん、以下同)
(広告の後にも続きます)
どの組織にもいる話の通じない人
同レジデンスの竣工は1974年。地上10階建て、300戸の大型マンション。穏やかだったその様相が一変したのは約30年前だった。管理組合の理事長に吉野(仮名)が就任したことが契機となる。
吉野理事長が就任当時は特にトラブルの声は聞こえてこなかった。しかし、20年ほど前に排水管工事が実施されるというアナウンスがあったが、工事業者はすでに指定されており、見積もりをとったのも1社のみだった。それに意義を唱えた住民たちも多く、不信感が強まっていった。
反・管理組合として「友の会」という団体の活動が始まった。その甲斐もあり、結果的に工事費は当初の予定だった金額から半額以下となったが、吉野理事長のどこか不満そうな表情がそこにはあったという。
大規模修繕の事案が落ち着くと「友の会」の活動は減少していったが、活動に加わった人たちがマンションの中で理事会メンバーに会うと嫌味を言われたり、変な噂を流されるなどのいやがらせを受けるようになっていった。そんな風にして管理組合による独裁体制はゆっくりと進行していった。
実際に取材した栗田さんに理事長はどんな人物なのか聞いてみた。
「管理への執着を除けば、理事長は特別おかしな人とは感じませんでした。例えば、世襲の中小企業のワンマン社長さんや、地方議員さんなどに近い印象です。思い込みが激しく、なかなか話が通じないというような。
ただ、エネルギーはすごくある人ですね。あそこまで厳格に管理をするというのは面倒ですし、普通の人にはなかなかできない。そもそも管理組合とか役員って回ってきたらやりたくない人が多いじゃないですか。そこに関心を持ちました。
じゃあ彼は理事長をやることで、大きな恩恵を受けていたかというと僕はあまりなかったのではないか、と思っています。
本書では、吉野理事長のような人とそれに従う人って、それこそあなたの周りにもいませんか、というメッセージも込めています。どこか日本社会の縮図を感じる取材でもありました」