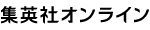「淋しい熱帯魚」「愛が止まらない 〜Turn it into love〜」などで80年代末のアイドルシーンを牽引したWink。そのメンバーの“さっちん”こと鈴木早智子さんが、コロナ禍を期に介護職員として働くようになった。そのなかで経験した介護の現場の「厳しさ」とは。〈前後編の後編〉
過酷な現場で精神状態をフラットに保てたワケ
――介護職員による入所者への暴言・暴力などが報じられることがあります。あってはならないことですが、介護職に就く方々のさまざまな面における不安定さを象徴しているように感じます。
鈴木早智子(以下同) そうしたニュースがあるたび、本当に心を痛めます。介護の現場は常に人手不足で、しかも忙しく重大な責任の伴う仕事であるにもかかわらず、一般に言われているようにお給料も多いとは言えません。そうしたなかで、精神的に病んでいく介護職員を私もみてきました。
――具体的に、現場において人手不足を実感するときは、どんなときでしょう。
たとえば排泄の介助をしているとします。ところが別の入居者さんから呼ばれることがあります。別の職員が対応できればいいですが、人数がいないため必ずしも対応できる場合ばかりではありません。当然ですが、こうした場合は、生命に関係する方に注力することになり、排泄の方は少し待ってもらうことになります。
新しい職員が入ってきても、すぐに辞めたりといった状況の改善が難しいのが現状です。
――介護職における大変さは、時間的な制約がきついことや体力的に摩耗することだけではないということですね。
おっしゃるとおりです。それらの大変さがあることは大前提で、精神的な負担が大きいこともあげられると思います。
介護職員は入居者様たちをケアする立場ですが、「ケアをする人のケアをどうするか?」という問題を真剣に考えなければならない局面にきていると感じます。
――そうした環境のなかで、鈴木さんがご自身の精神状態をフラットに保てたのは、どうしてだと思いますか。
入居者様の笑顔で自分も逆に元気を与えてもらっていたことが大きいと思っています。
もう一つ、強いて言うならば、芸能界で生きてきた経験も、関係するのかもしれません。日々さまざまなことが起きるなかで、自分を保つためには、しっかりと目標を定めてブレずに進み、自分の精神は自らで律しなければなりませんでした。
介護業界においても、「入居者様のお気持ちに少しでも寄り添えたら」を第一に考え、少しでも入居者様が安心出来る環境を整えられたらいいな……と心から思いました。
(広告の後にも続きます)
入居者とのコミュニケーション、職員とのコミュニケーション
――ミキサー食の味を実際の料理のようにつくる研究をしたり、すれ違う一瞬でのジャンケンのコミュニケーションなどをうかがいましたが、鈴木さんの“工夫”には入居者ファーストの姿勢があるのですね。
介護業界全体のことは語れないけれど、私が関わったひとりひとりとのドラマは大切にしていきたいという思いが強いのかもしれません。
たとえば、「この方は話すことができないし、ひらがな表でのやり取りも厳しい」と言われていた方も、ずっと話しかけ続けつつコミュニケーションを取っていたら、私が施設を去る最後のほうに「あー、うー」などと声を出してくれたことがありました。
ご本人も、ご家族も、たとえそれが意味のある言葉ではなくても、やはりうれしいものなんですよね。
業務に忙殺されれば時間はすぎていきます。それでも過酷な仕事をしているのだから、立派なことなのだとも思います。でも私は、やるべき業務をこなすだけにせず、入居者様個々にとってどんなコミュニケーションのアプローチがあるかを探りながら、試していきたいと思って実践してきました。
また、やるべき業務を耐えながらこなすだけになると、精神的にも参ってきてしまうと思います。自分から「こんな介護がやりたい」と仕掛けていったほうがモチベーションにもなるし、職員同士のコミュニケーションについても、工夫しながらチーム一丸でやろうとする思いが強くなっていけば気持ちだけでも改善に近づくのではないかなと。
――最後に、ご自身の介護職生活を振り返って、どんなことを思いますか。
私には微々たる力しかありません。介護業界が抱える問題について、思うところはさまざまありますが、すぐに変えられる力もありません。けれども、現状を知り携わった人たちに笑顔が増えたらいいなと思って奔走してきました。
ケアする側のケアについて、必要性は感じますが解決の糸口は見えません。けれども、精神的に改善した先に、介護職員がチームとなって入居者様たちのことを共有し語り合える未来があるといいなと思っています。
#1 はこちら
取材・文/黒島暁生 写真/本人提供