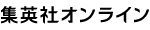アイドルとして一世を風靡し、“さっちん”の愛称で現在も親しまれている、アイドルデュオWinkのメンバー、鈴木早智子さん。そんな彼女だが、コロナ禍まっただなかの2021年から2024年にかけて介護職の現場に身を置いたという。彼女はなぜ、過酷と言われる介護の世界に飛び込んだのか……。〈前後編の前編〉
「最後まで、正体を言ってくれなかったね」
――介護職員になるきっかけについて教えてください。
鈴木早智子(以下同) ちょうどコロナ禍、訪問看護事業を手掛ける知り合いから頼まれたことがありました。それは、現場で奮闘している職員の方々とリモートで繋いでもらって、メッセージや歌を届けてほしいということでした。
当時、未曾有の感染症に世の中が怯えるなか、介護職員や看護職員の方たちは前線に出て闘っていました。その姿を自分の目で見たことがきっかけだったかもしれません。
また私自身、芸能の仕事だけを長く続けていたこともあり、一般社会のことについて無知だという自覚がありました。なのでコロナ禍をきっかけに、そこに飛び込んでみたいという気持ちもあったと思います。
――長くいた芸能の世界を離れて、一般社会、それも過酷といわれる介護業界に飛び込むのは不安ではなかったですか。
もちろん不安でした、世間知らずだとも思ってますし。生活の中心が車移動だったこともあって、最初は電車の乗り方もよくわからなかったりして(笑)。
でも全部自分で調べて、解決するようにしました。たとえば就職先も誰かの斡旋ではなく、最初から検索して履歴書を送るところからのスタートでした。
――有名人なので困ることも多そうですが。
3年間の介護職員生活のなかで、それぞれ1年間ずつ別々の施設で経験を積ませていただきました。そのいずれも、施設の責任者にはきちんとこれまでの経歴をお話して採用していただきました。
しかし一緒に働く職員に対しては、私がどのような経歴かは介護の現場に関係のないことなので、伏せて仕事をしましたね。
――バレなかったのですか。
やはり皆さん大人なので、詮索されるようなことはありません。ただ、施設を辞めるときに「最後まで(正体を)言ってくれなかったねー」と言われたりもしましたが(笑)。
私はいち介護職員として真剣に向き合い学びたいという想いが強かったので、そんな気持ちを察して、ときに厳しくも優しく指導して下さった同僚の方達にはとても感謝しています。
(広告の後にも続きます)
ジャンル、歌唱、ひとりミュージカル
――介護職は厳しい現場だと聞きます。実際に働いてみて、いかがでしたか?
過酷ですし、どのような言葉を尽くしても足りないのではないかと思えるほどに大変でした。今でも覚えているのは、1年目の休憩のとき、疲れすぎて気がついたら無意識に「ヘロヘロ」と紙に書いていて同僚に笑われたことがありました(笑)。
1年目はグループホームで働きました。ここは初めての体験尽くしの場所でした。私は介護の資格を持っていなかったので、働きながら学校に通って資格を取ることができました。
思えば初めて自分の名刺を手に入れたのもこの施設でしたね。社会人1年目の気持ちで、とにかくさまざまなことを吸収したいと動き回ってました。
思い出に残っているのは料理でしょうか。入居者様たちのほとんどは認知症を患っていて、その進行具合は個々で違います。食べられる料理の形状も異なるため、「この方はお粥+刻み食で、この方はミキサー食、こちらの方は常食」などすべて頭に入れて提供しなければなりません。誤嚥などを引き起こせば生命に関わる事なので。
私は料理をする事が好きではありましたが得意ではなかったので、ミキサー食であってももとの味に近づけるためにはどうすればいいか、あれこれ考えて工夫しました。
――2年目以降、施設を変えたのはなぜでしょう。
一言で介護職員といっても、働く場所はさまざまな形態があります。施設を変えることは、また一からという大変さがありましたが、なるべく広い範囲でそれぞれ環境の違う現場をみておきたいと考えていたからです。
2年目は夜専(夜勤専門)のサ高住(サービス付き高齢者住宅)を経験し、3年目は特養(特別養護老人ホーム)の日勤勤務として働かせていただきました。やはりそれぞれ違った大変さがあります。
2年目の夜専は、基本的に朝までは一人体制になるので、気を抜けない時間でもありました。夕方から深夜、朝にかけては、特に忙しい時間になります。雑務から、お薬の管理、排泄介助、入居者様を食堂へ移動させていただく――などスムーズに行う必要があります。アクシデントが起こらない保証はないので、スムーズに行かない現実がありますが。
――現場の慌ただしさが伝わってきます。そうしたなかで、鈴木さんはどのような介護を心がけていましたか。
私は介護職員としては新人であり、偉そうに物を言える立場ではありませんが、自分なりの工夫は見つけられた気がします。
例えば、入居者様とすれ違う一瞬の隙にジャンケンをしたり。ほんのわずかなコミュニケーションですが、笑顔になってくれるんですよね。たまに歌を歌うこともありました(笑)。一緒に歌ってくれる人もいれば、歌うのは嫌だけど聞くのは好きという人もいて、みんな身体を揺らしたり楽しそうにしてくれました。
童謡をややオーバーな振付でやってみることもありました。ひとりミュージカルですよね(笑)。私がバカになることで入居者様達が笑ってくれるなら、とことんやりたいと思っていました。
そんなわずかな時間であっても、隙をみつけて入居者様と触れ合っていくことの大切さをしみじみ感じた空間でした。
#2 に続く
取材・文/黒島暁生 写真/本人提供