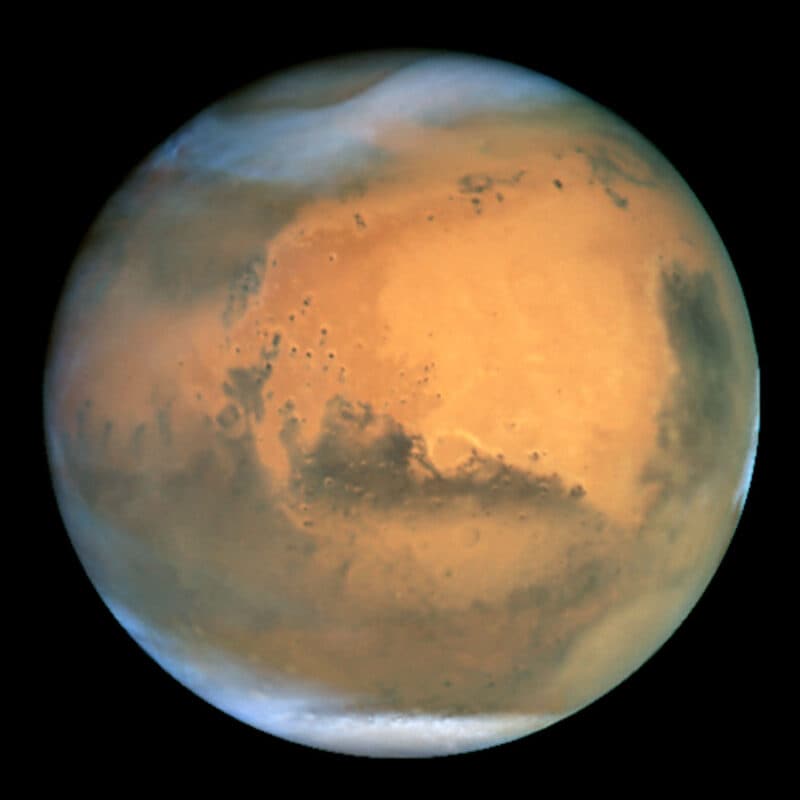Credit:canva
「引きこもり」は現代社会において、精神的・社会的に孤立する人々の象徴として、世界中で問題視されている現象です。
過度なプレッシャーや人間関係のストレス、失業、不登校、うつ病など、さまざまな要因から社会との接点を絶ち、自宅にこもる人は国を問わず存在します。
しかし、その中で日本の“引きこもり”は世界と比較してかなり特殊な状況にあるとされています。
現在、日本には200万人を超える「引きこもり」がいると推定されています(内閣府調査2023年)が、中でも最も多いのは、40代〜50代の中高年層。しかもその多くは10年以上も社会と断絶したまま暮らしています。
「そんな人、他の国にもいるんじゃないの?」と思う人もいるかもしれませんが、実のところこれほど引きこもりが長期化し、高い年齢層に偏っている国は、日本だけなのです。
これは日本の引きこもり問題は、世界と方向性が異なっていることを示しています。なぜ日本は特殊な“引きこもり大国”になってしまったのでしょうか? 何が他の国とは違うのでしょうか?
目次
日本社会に埋め込まれた“引きこもり”の種支援が届かない日本“構造的な無関心”の連鎖
日本社会に埋め込まれた“引きこもり”の種

Credit:canva
日本の引きこもり問題の特異性を語るには、まず他国の状況と比較して考えていく必要があります。
欧米諸国でも、不登校や若者の社会的孤立、いわゆる「ニート(NEET)」と呼ばれる就学・就労していない若年層は存在します。 また韓国や中国にも、社会に出ることを避けて自宅にこもる若者が一定数いることが報告されています。
しかし、それらの多くは「一時的な状態」であり、数年以内に再び社会とつながるケースが大半です。しかも年齢層は若年に集中しており、40代以上で10年以上引きこもっているような例は極めて少数派なのです。
例えば、単純な引きこもりの数を比較した場合、国民に対する引きこもりの割合は
日本:約1.2%
韓国:約2.3%
香港:約1.9%
イタリア:約1.2%
と別段日本が特別高い値を示しているわけではないとされています。むしろ韓国や香港の方が数の上では深刻に見えます。
しかし、内閣府の調査(2016年)によれば、日本の15歳~39歳の引きこもり経験者の約35%が7年以上引きこもり状態にあると報告されており、さらに40歳以上の中高年層の引きこもりが増加傾向にあるといいます。
佐賀県の調査(2017年)では、引きこもりと認識された644人のうち、40歳以上が全体の70%以上を占めていました。
一方で、韓国の引きこもりの平均年齢は20代前半であり、長期化するケースは少ないとされています。イタリアでも引きこもりは未成年者が主な対象であり、長期化や高年齢化の問題はあまり報告されていません。
つまり、日本の引きこもり問題は、年齢・持続期間において“世界でも異常”といえる状況にあるのです。
では、なぜこのような差が生じたのでしょうか? その答えを探るには、日本に特有の“社会構造の癖”を見ていく必要があります。
まず、背景にあるのが高度経済成長期に形成された成功モデルの固定化です。
1950年代から70年代にかけて、日本は世界が驚くような経済発展を遂げました。そして社会に根づいたのが「良い学校に入り、安定した企業に就職し、定年まで勤め上げる」という1本道の人生ルートです。
このルートを外れた者は、「失敗者」「社会不適合者」というレッテルを貼られがちになり、やがて社会的な沈黙を選びます。
つまり、日本は世界的にも稀な“奇跡的な成功”を体験してしまったがために、人々の人生における「やり直し」や「別ルート」を選択するという社会構造を失ってしまったのです。
さらに、欧米が宗教的な倫理観や個人の良心をベースにした「罪の文化(内面の反省)」なのに対し、日本では「他人にどう見られるか」が行動規範となる「恥の文化」が土台となっています。
これは、古代から続く日本の“村社会的構造”に根ざしたものだと言えます。
日本は自然災害が多く、稲作中心の生活を維持するためには、近隣住民との協力と秩序が不可欠でした。 この環境では、集団との調和=生存条件であり、「周囲から浮かない」「迷惑をかけない」ことが重要視されてきました。
その結果、社会的ルールやモラルは「法律」よりも「周囲の目」によって維持されるようになり、他人の視線を常に気にする行動様式が文化として定着したのです。
これにより、人前での失敗や社会からの逸脱は「恥」とされ、社会から一度外れると再び外に出ることが難しくなる心理を強化してしまいます。
加えて、日本社会には“家”を単位とする家族主義が色濃く残っています。
江戸時代から続く「家制度」では、家業を長男が継ぎ、家族が同じ屋根の下で暮らし続けることが当然とされてきました。
現代でもその名残は強く、親が成人後の子どもを支えることが当たり前という文化が引きこもりを長期化させる要因となっています。
対照的に欧米諸国では、18歳を過ぎれば子どもは親元を離れ、経済的・生活的に自立することが一般的です。親もまた、「子どもは独立すべき存在」と捉えており、成人後も親が生活を全面的に支えるという発想自体が非常にまれです。
そのため、引きこもりのような状態が日本ほど長期化しにくいのです。
このように、高度経済成長期の成功モデル・恥の文化・家制度という三つの要因が、日本社会において「引きこもり」という現象を助長する構造を作ってしまっていると考えられるのです。
(広告の後にも続きます)
支援が届かない日本“構造的な無関心”の連鎖

Credit:canva
もう1つの大きな問題が日本では、引きこもりへの社会的支援が届きづらいということです。
その理由は、個人の問題ではなく、制度と文化の構造に起因しています。
まず、日本の福祉制度は「自助・共助・公助」という戦後モデルに基づいています。
「自助」とは、まず本人や家族が自分たちの力で問題解決を図る段階を指します。 「共助」とは、地域社会や近隣の支え合い、民間団体の助けなど、非公的な支援を意味します。 そして「公助」は、最後の手段としての行政や政府による支援を指します。
この3段階のうち、日本では「まず自助と共助でなんとかしてください」という姿勢が強調される傾向にあり、これは一見バランスが良さそうに見えますが、実際には「まずは家庭でなんとかしてください」という家族依存型の福祉です。
このため、当事者や家族が限界に達するまで行政が動きづらく、結果として“重症化した後”でないと支援が始まらないという遅れが生じるのです。
さらに、日本の行政は典型的な「縦割り構造」になっており、教育(不登校)なら文科省、医療(精神的支援)なら厚労省、他にも福祉(生活支援)・労働(就労支援)など、すべてがバラバラに機能しています。
引きこもりはこれらすべてにまたがる複合的な問題であるにもかかわらず、総合的に支援できる窓口が存在しないのです。
加えて、引きこもり当事者は社会的にも「見えない存在」であり、選挙など政治的な場面で“票にならない層”として軽視されがちです。
本人も社会から距離を置いており、声を上げる術も持たないため、政策において存在が可視化されづらく、日本の支援をさらに遅らせているのです。
なぜ海外では“同じ問題”が深刻化しないのか?

Credit:canva
では、なぜ欧米諸国では、日本と同様に引きこもり予備軍が存在するにも関わらず、深刻な社会問題にならないのでしょうか?
そのカギは「支援が“ある”かどうか」ではなく、「支援が“届くように設計されているか”」にあります。
北欧諸国では、「福祉は恥ではなく、当然の権利」という価値観があります。
教育・就労・生活支援に公的制度を利用することに抵抗がないため、当事者や家族が早期に支援にアクセスできます。
一方、日本では先に述べた文化的背景により「福祉=最終手段」「支援を受けるのは甘え」という空気が根強く、利用そのものに罪悪感や恥がつきまとうため、支援が活用されにくいのです。
また欧州では、学校や地域にソーシャルワーカーが常駐しており、家庭や本人に変化があればすぐに支援の手が差し伸べられます。
教育・医療・福祉・労働が一体となったケースマネジメント体制が一般化しているため、制度の隙間に落ちにくいのです。
日本はこれとは逆に、「問題が起きてから相談してください」という事後型対応が主流です。
最後に、欧州諸国では、福祉政策の成果(若年層の就労率、孤立の減少など)が政党の評価に直結します。
そのため、支援対象が社会的に“声を上げづらい存在”であっても、代弁する制度や職種(オンブズマン等)が整備され、政策として支援が届きやすくなっています。
このように、支援の“構造的な届きやすさ”の差が、日本と海外での引きこもり問題の重みを決定づけていると考えられます。
引きこもりは“個人の病”ではなく“社会の鏡”

Credit:canva
日本の引きこもり問題は、単なる個人の問題ではなく文化、制度、歴史的な家族構造、そして支援の設計思想などが絡み合って、“引きこもり”から抜け出しにくい社会構造を作り出しています。
そのため引きこもりを単純に個人の問題、家族の問題にはできません。
そして、ここまで見てきてもわかるように問題解決の大きな障害の1つは、日本人特有の気質として、当人たちが引きこもり状態を恥と感じ、積極的な支援や社会復帰を避けてしまう点にあります。
また日本の親が、成人後の子どもを家庭で養うことに抵抗感が薄いことも問題の1つでしょう。
社会構造の問題をすぐに解決することは難しいかもしれませんが、日本の引きこもりが世界的に見ても異常な状態になっているのは、人々の意識の問題に起因するところが大きいようです。
引きこもりを甘えや楽しているという人もいるかも知れませんが、好きで引きこもっている人は少数でしょう。
そのためまずは、引きこもりを恥ずかしい状態と考えることをやめて、「失敗してもやり直せばいい」という考えを定着させていくことが、この日本固有の社会現象を解決する足がかりになるかもしれません。
参考文献
内閣府「令和5年版 孤独・孤立対策白書」
https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/zenkokuchousa/r5.html
NEET Youth in the Aftermath of the Crisis
https://www.oecd.org/en/publications/neet-youth-in-the-aftermath-of-the-crisis_5js6363503f6-en.html
The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture
https://amzn.to/3FCfXKr
元論文
「ひきこもり」に関する文献的考察
https://doi.org/10.24503/jasmh.5.0_75
日本社会における「ひきこもり」の承認論的考察
https://ci.nii.ac.jp/naid/500001674273
ライター
相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。
編集者
ナゾロジー 編集部