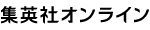異物混入騒動を受けて、3月31日より全店一時閉店となった大手・牛丼チェーン『すき家』。そのショッキングな事件とは裏腹に、SNSではすき家を熱心に応援・援護する声が相次いでいる。その裏には、陰謀論が大きく関与しているという説まででてきているようだ。
「みんなおかしいと思わないか?」SNSで広がる陰謀論
3月22日、すき家はSNSで拡散された「みそ汁にネズミが混入している写真」について事実だと認めたうえで、謝罪のコメントを発表した。ネズミ混入は1月21日に発生したもので、その場で従業員が目視をして確認していたのだが、問題発生から約2か月を過ぎるまで、公式で発表されることはなかった。
〈当該店舗については発生後すぐに一時閉店し、衛生検査の実施と、異物混入に繋がる可能性のある建物のクラックなどへの対策を講じるとともに、商品提供前の目視確認など、衛生管理に関して改めて従業員に対する厳格な教育を行いました。また、発生当日の段階で所管の保健所にも相談しています。なお、当該店舗は発生2日後に保健所のご担当者様に現地確認をいただいた上で営業を再開しました〉
と、すき家はその後の対応も発表しているが、そもそもの発表が遅れたことで大きな不信感を買い、大炎上につながってしまった。
そして3月29日には、28日にすき家 昭島駅南店で客に提供した商品に異物(害虫)が混入していたことを発表。これを受けてすき家は、ショッピングセンター内などの一部店舗を除く全店を、3月31日午前9時から4月4日午前9時までの間、害虫・害獣の外部侵入、および内部生息発生撲滅のための対策を行なうために、一時閉店することを決定した。
しかし“食の安全”がゆらぐほどのこの大問題に対して、SNS上では「すき家を守ろう」とする動きが活発化している。
たとえばXでは、「すき家は国産米を使用しているため、外国米を使わないことに不満を持つ勢力にハメられてしまった」「何者かが工作をして、すき家の評判を下げている」などといったウワサがまことしやかに流布されているのだ。
〈日本を大事にする企業は嫌がらせされる。みんなで国産米を使ってくれているすき家を守ろう!〉
〈こんなでっかいネズミが入ってたら普通気づくと思う。すき家さんも国産米しか使わないからってよ潰そうとしないでよ〉
〈すき家叩いてる人、偏った報道しかしない日本のメディアが一斉に報道するという事は政治的背景がある事を知りましょうね〉
〈みんなおかしいと思わないか? 国産米使ってるすき家をみんなで助けようぜ。日本人一致団結するときだ。すき家を応援する人はみんな「いいね」してくれ。拡散してくれ〉
(広告の後にも続きます)
陰謀論好きの人には陰謀論が届く仕組みに
すき家をハメたと主張する主要なポストは、軒並み5万以上の「いいね!」がついて広く拡散されており、今もなお、さまざまな“すき家擁護”のポストが拡散され続けている。
現在のXではもはや、すき家は被害者のようにも見えるほどだ。
なぜこのようなウワサがSNSでここまで多く広がっているのか。ITジャーナリストで、情報リテラシー教育を専門とする成蹊大学客員教授・高橋暁子氏に話を聞いた。
「SNSにはアルゴリズムによって、ユーザーの興味関心や好みに合った投稿を積極的に表示する仕組みがあります。たとえば陰謀論好きな人には陰謀論に関する投稿を表示する可能性が高いことが分かっています。それによって、それだけが真実と思い込む“エコーチェンバー現象”※が働くというわけです。
(※自分と似た意見や思想を持った人々の集まる空間やSNS内などでコミュニケーションが繰り返され、自分の意見や思想が肯定されることによって、それらが世間一般においても正しく、間違いないものであると信じ込んでしまう現象)
検索する場合も検索結果はフラットではなく、やはりユーザーの興味関心を反映させた結果が表示されます。見たい情報しか見えないようになっている“フィルターバブル”状態になっているのです。
このような特性によって陰謀論を信じるユーザーたちがSNSで投稿したことで、現状の状態となっていると思われます。一部のユーザーの推論や願望が投稿されたことで、そうあってほしいユーザーがそこに乗っかり、拡大していったのではないでしょうか」(高橋暁子氏、以下同)
陰謀論に乗ってデマを拡散してしまった場合は逮捕されるケースもあるが、今回は、そのような陰謀論によって“企業を守ろう”としている。これはどのように扱われるのだろうか。
「過去には、誤った推論によって、無実の方を犯人扱いするなどの風評被害も起きています。今回はすき家をかばう論調のため、名誉毀損罪などで訴えられることはないでしょう。しかし、陰謀論がいきすぎて、異物混入を投稿したユーザーを嘘つき呼ばわりなどした場合は、名誉毀損罪などで訴えられる可能性があります」
たとえ何かを守るためであっても、デマの拡散は許されるものではない。何気なく押した「いいね」「リポスト」のボタンにどれほどの重さがあるのか、改めて考えるべきだろう。
取材・文/集英社オンライン編集部