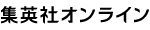親子で趣味を一緒に楽しむことができる家庭では親の認知症予防ができ、子どものIQがぐんぐん伸びる……まさに一石三鳥のこの状況は、脳科学の観点から説明ができるという。
脳科学者瀧靖之氏の著書『本当はすごい早生まれ』より一部を抜粋・再構成し、「単純接触効果」と「ミラーニューロン」という2つの脳の働きについて解説する。
ワクワクすると記憶力が高まる脳の仕組み
好奇心が高いと、なぜ成績が良くなるのか。
その理由の一つは、好奇心は記憶力を高めるからです。これはグラフからもわかります*1。
好奇心のレベルが高い人は、記憶を担当する脳の中の海馬や、報酬系に関わる領域(腹側被蓋野、側坐核、中脳黒質等)の活動が活発になります。
問いへの正答率も、好奇心のレベルが高かった人の方が高いのです。好奇心が高い人というのは、「〜を知りたい」「〜をしたい」と、ワクワクしながら物事に取り組める人です。このようなワクワク感が記憶力を高めるのです。
注意しなければならないのは、イヤイヤ行う勉強です。ここには「扁桃体」というアーモンド型をした脳の領域が関わってきます(扁桃はアーモンドのことです)。上のイラストのように、記憶を担当する海馬の隣には、ストレスや不安に関わる「扁桃体」という領域があります。
これらは機能的に、しっかりと連携しています。ストレスや不安があると、扁桃体が海馬の活動にマイナスの影響を与えてしまうのです。
感情と記憶力に、密接な相関があるのはそのためです。
(広告の後にも続きます)
好奇心は、将来の認知症リスクを下げる可能性がある
好奇心は、どの世代にとってもとても大事な「サプリ」です。
私たちが「東北大学加齢医学研究所」で行った研究で、知的好奇心レベルが高いと、高次認知機能を担う領域である「側頭部頭頂部」の萎縮がより抑えられるということを明らかにしています*2。
好奇心が高い人ほど、脳の健康が保たれることが、科学的に証明されたのです。
私自身も多くの趣味を持っています。種々のスポーツ、楽器演奏や自然観察、芸術鑑賞、車、読書、かなりのことを仕事の合間にしています。これらは脳の可塑性(かそせい)を高める上でも、主観的幸福感を高める上でも、会話のエッセンスとしても、非常に重要で、いずれも脳の健康の維持や将来の認知症リスクを下げる上で重要なものです。
趣味は何でもいいのです。好きを突き詰めるだけで、皆さんの脳は元気に保たれるからです。みっちりとした脳を保つために、好きなことを続けていきましょう。