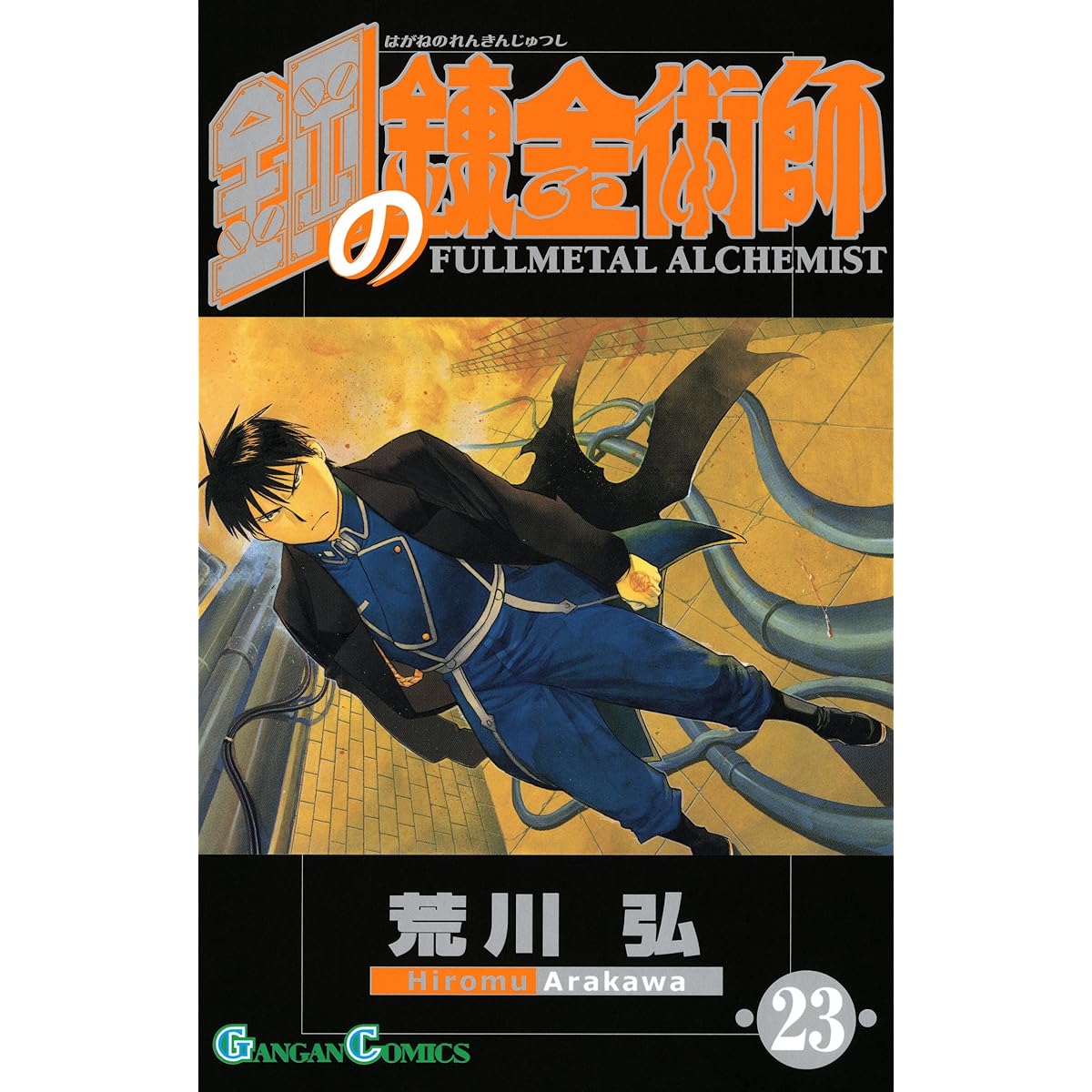初代PlayStationの時代には、挑戦的なゲームが多数、発売されていました。当初は評価がいまひとつだったものの、のちの大ヒット作につながったタイトルや、カルトゲームとして令和のいま高額取引されているタイトルを見ていきます。

令和のいまカルトゲームとしてその名を馳せる『LSD』(アスミック・エース エンタテインメント)
【画像】そんなのあったっけ? こちら初代プレステ背面の「謎の端子」です
初代PlayStation時代の奇跡(?)のようなゲーム
かつて「クソゲー」の烙印を押されたゲームが、後に評価がひっくり返るのはよくあることです。理不尽の固まりと見られていた『たけしの挑戦状』も、いきなり社長を殴れる自由度の高さが、世界的オープンワールドゲーム『GTA』(グランド・セフト・オート)の先がけとも呼ばれるようになりました。
そうした逆転は、初代PlayStation(以下、PS)用のタイトルで多めです。ソニー初のゲーム機として開発者に広く門戸を開いたこと、そして本格的3Dゲーム時代の黎明期だったために「何でも試された」事情が大きいのでしょう。
そのうしたゲームのひとつが、1994年12月16日に発売された初代『キングスフィールド』です。もともと業務用アプリ開発を手がけていたフロム・ソフトウェアにとってのゲームデビュー作であり、冒険にも程がある第一歩です。
当時2Dのゲームに慣れていた日本のプレイヤーにとって、3Dリアルタイム戦闘は非常に異質でした。ろくにチュートリアルもなく、スタート直後は貧弱な装備で所持金も少なく、操作もモッサリと重く、セーブや回復ポイントも自力で探せという突き放し方です。
が、一部ゲーマーはシビアかつダークな雰囲気に魅せられていきました。さらにフロム・ソフトウェアは続編を次々と発売し、ゲームボリュームやグラフィックを改善することで人気を確立したのです。こうした流れは後の『Demon’s Souls』(デモンズソウル
)や「DARK SOULS」((ダークソウル)シリーズに受け継がれて「死にゲー」ブームへと繋がります。時代が追いついたといえるでしょう。
より遊ぶ人を選ぶのが、1998年10月22日にアスミック・エース エンタテインメントが発売した『LSD』です。「LSD」は幻覚剤を意味する言葉であり、挑戦的すぎる一作です。
ジャンル名は「ドリームエミュレータ」であり、開発スタッフが10年間、書き留めた実際の夢日記を元にしています。一人称視点で3Dフィールドを歩き回るだけで、移動と視点変更のほかのアクションは存在せず、ガチに「他人の夢を追体験する」という内容です。
壁やキャラクターなどにぶつかることで別の場所にワープしたり、テクスチャが不意に変化したり、「エレベーター内の金魚鉢」など実写ムービーが流れたり、プレイヤーは戸惑うばかりでした。キャッチコピーでうたう「こんなのゲームじゃない」は本当だったのです。
が、夢の不条理な世界を自由にさまようこの内容が、「体験型アート」として再評価されています。また発売本数の少なさから超高額なプレミアム価格が付いており、今では90万円近い場合もあります。
最後に『クーロンズゲート』ほど、評価が乱高下したゲームもないでしょう。初代PS本体と同時に登場すると見られていたのに、2年以上遅れた1997年2月28日発売となり、実際のプレイ体験も唖然とさせられたからです。
プレイヤーは「超級風水師」として、この世と対をなす「陰界」から現れた九龍城に乗り込み、世界の崩壊を防ごうとします。前例なき東洋サイバーパンク・アドベンチャーであり「常識は、今のうちに捨てておいてください」とのキャッチコピーも心を高鳴らせました。
が、登場人物はほぼ全て奇天烈なルックスのうえに専門用語を連発し、うねるような「JPEGダンジョン」は酔いやすく、同じ場所を行ったり来たりしてフラグを立てる単調さ、戦闘も「敵の属性に勝てる属性をぶつける」だけです。しかもゲームオーバー時は、主人公は冷蔵庫など家電になります。さらに発売日が国民的RPG『ファイナルファンタジーVII』の翌月であり、余計に「奇ゲー」の印象を強めてしまいました。
とはいえ、モノに執着した人間が成りはてる「妄人」など唯一無二の世界観や、現実世界で香港から消え去った九龍城の思い出を色濃く留める作品でもあり、愛する人にはとことん愛されました。なにより、ゲームが「誰にとっても面白くなければならない」義務からも解き放たれた、初代PS時代の自由な空気が詰まっているのです。