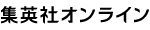なぜ日本において学歴社会・学歴主義はなくならないのか。誰のために存在するのか。その背景にあるのは、「頑張れる人」を求める企業と、その要望に応えようとする学校の“共犯関係”なのかもしれない。学歴がすべてではないと言われても、やはり学歴を気にしてしまう社会について考える。
『学歴社会は誰のため』より一部抜粋・再構成してお届けする。
「労働=企業」という企業中心社会
学歴論争とは一言で言うと、学歴の価値、意味付けを巡る論争です。価値や意味を見出す・見出さないの話について、ロジカルに精査しようとするならば、その価値や意味を決める(付与する)側の言い分を考える必要があるでしょう。
つまり、学歴は要るだの、要らないだの、やんや言われる様を前章で見てきたうえで、問うべきは次の2点なのです。
(1) 大学に行ったかどうかや、名門校に行ったかどうかの「意味付け」、すなわちは学歴の「評価」を直接的に行なってきたのはいったい誰か?
(2)誰が学歴に良し悪しという「価値」を植えつけたのか?
この2つの問いを考えるに際して、「労働=企業による雇用」ではない事例から考えてみるとスムーズです。どういうことでしょうか。
企業などに勤めに出るのではなく、特定の職能を活かして独立独歩で仕事をする姿を想像してみましょう。学歴はその人の将来のパフォーマンスを予見する材料になるでしょうか。たとえば、ある15歳の青年が「僕は寿司職人になりたいんだ」と意気込んだときを思い浮かべてみます。「それなら東大に行くんだぞ!」と叱咤激励する人は……いるか? という話です。
調理師免許を取り、魚をはじめさまざまな食材の知識をつけ、「修業」というかたちで実地で学んでいくことでしょう。美容師なども同様です。昨今で言うと、データサイエンティストになるのが小学生のころからの夢だという子に、「東大に行かなきゃなれないよ!」というアドバイスをするのもだいぶ的外れです。
求められる技能が明確で、その職業に就く道筋も特定の技能の有無やレベルによって明らかなとき、学校から職業のトランジションにおいて、なにも「学歴」という情報をありがたがってかませる必要は必ずしもないのです。
しかし、別の15歳が「国内最大規模の商社で世界をまたにかけたビジネスをやりたい」と言ったらどうしましょうか。名門商社の総合職には大卒資格がいまのところは必須ですし、学歴のみならず学校歴としても、上位校とされるところでないと選抜を潜り抜けることは難しいかもしれません。
現にある就活情報サイトに、2023年度の三井物産の採用大学ランキングが掲載されていたので見てみます。おっと……。慶應義塾大学、早稲田大学、東京大学、京都大学、一橋大学……これなら「大学、それも『いい大学』に行くんだぞ!」とのアドバイスはなんら的外れではないことになります(良し悪しの話はまったくしていません)。
(広告の後にも続きます)
採用において─企業研究サイトの現状
要するに、企業で行なわれず、専門性や職務要件が明確な仕事─スポーツ選手や、いわゆる資格制度のあるような専門職─に就くための切符は何か? という選抜要件は、明確なのです。学閥という考えは一部にありますが、まずはその職業的専門性の試験をパスしていることなのです。
先の寿司職人や美容師の例のほかにも、たとえば理学療法士などを思い浮かべてもいいでしょう。「企業研究」サイトにあるような、学歴の話題はほぼないでしょう。学校ごとの国家試験の合格率ランキングなどの情報は出てはいるものの、それも就職先の病院を企業組織に準じるものとした場合、学閥の影響がありやなしやという程度の話です。
したがって、学歴という情報をありがたがるのは、企業への就職という前提があってのことなのです。しかも、企業のなかでも、現場社員というより人材の選抜や登用に携わる経営陣や人事にとってです。企業は業績を上げるために存在していますから、そこに参画することで利益をもたらし得る人材がほしいのはもっともとも言えます。
というわけでここからは、企業が学歴という情報をいかに扱ってきたか? について、人材フローに沿って見てみましょう。
企業に就職する際に、労働する前の教育の履歴を参照して、その人(の能力)を見立てようとすること。これが企業社会における労働の登竜門=就職プロセスの1つであることは周知の事実でしょう。ある最大手人気商社への就職を狙う人の多くが、次のような「企業研究」サイトの情報を事前にチェックするのはもはや常識とも言えます。
ちなみにこちらのサイトには、役員面接に備えて、役員の出身大学一覧もご親切についています。(「“三井物産の採用大学レポート”学歴フィルターとTOEIC点数を公開。採用をもらうための最低条件とは?」(大手の“学歴と年収”リサーチ、2022年11月21日))
加えて、この「学歴と年収の研究室─面接官のホンネ 大手の“学歴と年収”リサーチ」サイトは無償でオープンな情報提供ですが、こうしたサイトを運営する大手は、より情報商材化している場合もあります。
たとえば就活情報サービスなどを展開するワンキャリア社のサイトでは、会員登録しないと「〇〇社 採用実績徹底解剖」(「【140名の狭き門】三井物産の大学別採用実績を徹底解剖:三井物産編」(ONE CAREER))というシズル感のあるコンテンツを見ることができません。個人情報と引き換えに、やっと手に入れる「機密情報」なのです。
実績という「過去」の他人の情報を見たところで、「いまの」自分ができることは限られているわけですが、人気企業への就職が狭き門である(選抜的である)以上、その企業の選別傾向(評価軸)を知っておくことは、選んでもらわなきゃならない個人側にとって合理的な行動と言えましょう。