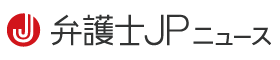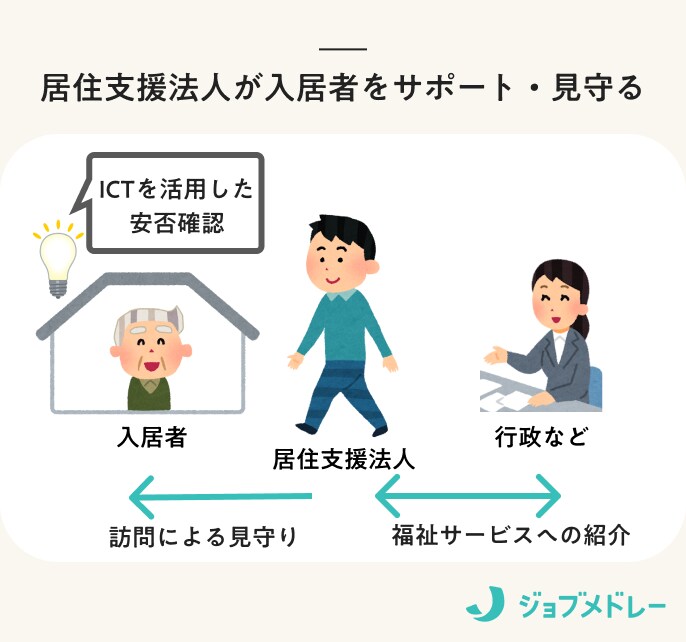内閣府が2019年に実施した世論調査によれば、死刑制度について「やむを得ない」と回答した人は80.8%で、「廃止すべきである」の9.0%を大きく上回っています。
しかし、国民は「死刑」の詳細を、どのくらい知っているのでしょうか。死刑執行当日の拘置所に流れる異様な雰囲気、刑務官たちの重すぎる心的負担、死刑囚の心のケアを行う教誨師の苦悩…。
死刑執行に携わるさまざまな立場の人たちへのインタビューをもとに、いわば“ブラックボックス化”したまま継続されている「死刑制度」の実態に迫ります。
(#3に続く)
※【#1】「すごいですよ、ピリピリして」“死刑執行”当日に元受刑者、元拘置所幹部が感じた“異様な雰囲気”
※この記事は共同通信社編集委員兼論説委員の佐藤大介氏による書籍『ルポ 死刑 法務省がひた隠す極刑のリアル』(幻冬舎)より一部抜粋・構成しています。
刑場までの道
房から刑場までの道のりは、拘置所によって異なる。法務当局は、刑場の位置について「保安上の理由」(法務省)から公開していないが、関係者の証言などから、東京拘置所や名古屋拘置所のように地下にある場合もあれば、別棟にある場合もあることがわかっている。
いずれの場合も、刑場の入り口には「死刑執行場」などと明記されてはおらず、拘置所内でも一部幹部や職員にしか詳しい場所が明かされていないことが多いという。東京拘置所の場合も、それは同じだ。
東京拘置所の関係者の話を総合すると、11階など上層階に収容されている確定死刑囚は、房から出された後は1階までエレベーターで運ばれる。連行の際、普段は洗濯物の回収や食事の配膳などで忙しく動き回っている衛生夫はすべて廊下に出ることを禁じられ、確定死刑囚と連行する刑務官ら関係者以外、人の動きは一時的にストップする。
映画や小説に出てくるような、同じフロアの確定死刑囚たちとの別れの挨拶をすることはなく(集団処遇を認めておらず、普段から被収容者同士のコンタクトは禁じられている)、臨時に設けられたパーテーションで作られた「道」を、刑務官に急かされるようにして歩いていく。警備隊員も等間隔で立ち、万一の事態に備えている。
エレベーターから降りた後も、同様にパーテーションの「道」ができており、普段は使われない別通路の入り口までつながっている。その扉を開けると地下道のような傾斜になっており、そのまま廊下を歩いていくと刑場の入り口につながる。別通路や刑場の入り口には、盛り塩と香炉が置かれているという。
確定死刑囚がまず連行されていくのは「教誨室」だ。テーブルを挟み椅子が2脚置かれ、ここで普段から面会を重ねてきた教誨師と会うことができる。壁には仏壇(宗教によって祭壇にするなど体裁を変える)があり、線香がたかれるなか、教誨師とともに確定死刑囚は心を落ち着かせようとするが、なかには最後まで教誨を拒み、この部屋を「素通り」する者もいるという。

刑場までの道は限られた人にしか明かされていないことが多いという(ykokamoto / PIXTA)
最期の時間の作法
教誨を終えた確定死刑囚は教誨師とともに、入ってきたところとは別のドアから出て10メートルほどの短い廊下を歩き、金色の仏像が壁にはめ込まれた部屋に入る。縦5.8メートル、横4.2メートルのやや大きめの部屋。天井までは3.8メートルと高い。そこは「前室」と呼ばれ、連行されてきた確定死刑囚は、ここで拘置所長から正式に死刑執行を告げられる。
前室には拘置所長のほか、立ち会いの検事、検察事務官、拘置所の総務部長、処遇部長、医官、刑務官が集まっている。拘置所長が死刑執行の命令書を読み上げると、確定死刑囚は幹部たちと最後の会話を交わす。また、最後の祈りを捧げることもでき、被害者や残された家族への祈りのほか、教誨師から最後の説教を施される。祭壇には簡単な供え物があり、茶菓子を勧められるが、一般的に手をつける者は少ないという。
最後に遺書を書くことが認められるが、時間は5分程度と短い。気が動転している場合も多く、確定死刑囚のなかにはあらかじめ遺書をしたため、最後に一筆書き加える者もいる。刑務官らへの別れの挨拶や、遺言を遺すことも可能だ。
そうした「儀式」が終わると、刑務官たちには緊張が走る。間違いの許されない「迅速且つ正確な執行」(元幹部)に向けて、刑務官たちはそれぞれの担当に向かう。部屋には厚いじゅうたんが敷かれ、刑務官たちの足音は聞こえない。
まずは確定死刑囚をガーゼで目隠しし、後ろ手に手錠をかける。それと同時に、前室の横にあった青のカーテンが開かれる。その先にあるのは、天井の滑車からロープが垂れ下がっている「執行室」だ。
だが、目隠しをされた確定死刑囚には、その様子は見えない。前室と同じくらいの大きさの執行室には、中央に110センチ四方の正方形の赤枠があり、その内部には90センチ四方の「踏み板」がある。
3つのボタン「全員に苦悩を与えているだけ」
執行室には刑務官3人と保安課長が確定死刑囚とともに入室し、保安課長は執行室の奥にある「ボタン室」の前に進み、中にいる刑務官3人から見える位置に立つ。ボタンを押せば踏み板が外れる仕組みになっているが、実際に踏み板と連動しているのは1つのボタンだけで、2つはダミー。すこしでも刑務官の精神的負担を軽減しようとする「苦肉の策」というわけだ。しかし、元刑務官は「3人の刑務官全員に苦悩を与えているだけ」と話しており、その効果は定かではない。
刑務官3人は、確定死刑囚を赤枠の中に立たせると、1人が素早く両足をひもで縛り、2人がロープを首にかけて、首の左側に結び目が来るようにして軽く締める。こうすると、体が落下して首に衝撃がかかった際、体が正面を向き、立会人に対して頭を下げているような姿勢になるという。
それが終わると、保安課長はボタン室の3人に指示。3人が同時にボタンを押すと、踏み板が外れて確定死刑囚は地下に落ちていく。確定死刑囚の首にロープがかけられてから踏み板が外れるまでは、わずか数秒程度。「この時間をすこしでも短くしてやることが、我々が死刑囚にしてやれる精一杯の施し」と、執行に立ち会ったことのある刑務官は話す。
確定死刑囚が執行室に移動すると、拘置所長や検察官などの幹部は「立会室」に移り、ガラス越しに執行の様子を見守る。確定死刑囚の体が落下すると、地下では刑務官2人が待機し、1人が抱きかかえるようにして受け止める。こうしないと、確定死刑囚の体は反動で大きく揺れ、ロープのねじれで体がぐるぐると回ってしまう状態となり「立会人に対し、残酷な場面を見せることになる」(元刑務官)からだ。その後、もう1人の刑務官が確定死刑囚の体を立会人の方に向かせて、静止させる。
この「受け止め役」は死刑執行に立ち会う刑務官のなかでも最も敬遠される仕事で、拘置所幹部から指名された際、泣き顔になりながら「勘弁してください」と懇願したベテラン刑務官もいたという。
確定死刑囚の体から痙攣(けいれん)などの動きが止まると、医官が死亡を確認し、死刑執行は終了する。確定死刑囚の体が落下してから死亡確認までは15分ほど。その後、確定死刑囚はロープから外されて湯灌(ゆかん)を施され、棺桶に納められる。立ち会いの検察官、検察事務官と拘置所長が「死刑執行始末書」にサインと捺印をし、一連の手続きは終わる。
拘置所側は、事前に確定死刑囚から申告されていた、肉親など死刑執行時の連絡先に電話を入れる。知らせを受けた肉親は、すぐに遺体を引き取りに来るケースもあれば、引き取りを拒否して無縁仏として供養されることもある。
(第3回目に続く)