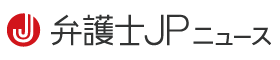ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の通訳を務めていた水原一平氏が4月11日、銀行詐欺容疑で訴追された。水原氏が捜査当局との間で、被疑事実を認める代わりに刑を軽くする「司法取引」に応じる可能性があると報道されている。司法取引の制度は日本では2018年に導入されているが、実際に利用されたのは4件にとどまっている。司法取引とはどのようなものか。日本でアメリカと同様の司法取引を導入するにあたっての課題は何か。
司法取引とは?
司法取引は厳密には「自己負罪型」と「捜査協力型」の2種類がある。このうち、日本では2018年6月から「捜査協力型」が導入されている。両者の違いはどのようなものか。これまでに8件の無罪判決を勝ち取った実績があり、日本とアメリカの両方の刑事司法制度に詳しい川﨑拓也弁護士(藤井・梅山法律事務所、京都大学法学部・法学研究科客員教授)に聞いた。
「まず『自己負罪型』は、自らの犯罪事実を認める代わりに量刑を軽くしてもらうというのが基本です。今回の水原氏のケースがこれにあたりますが、日本では制度として採用されていません。
これに対し、『捜査協力型』は共犯者等、他人の犯罪に関する情報を提供した場合に自分の処分(不起訴処分等)や公判での求刑を軽くしてもらえるというものです。アメリカでは『スニッチ』といって、対象となる被疑者・被告人と留置施設等で同房となった者が情報提供者となり、捜査協力型の司法取引に利用されます。
日本で導入されているのはこの『捜査協力型』ですが、現状、対象となるのは一定の組織犯罪、財政経済犯罪、薬物犯罪、銃器犯罪等に限られています。また、弁護人の同意が要求されるなどの一定の縛りがかけられています。
これまでに実際に利用された例は、元日産会長のカルロス・ゴーン氏の金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)のケース(※)など、4件にとどまっています。」(川﨑拓也弁護士)
※ゴーン氏の「役員報酬隠し」に関与した元役員らが、ゴーン氏への捜査に協力した見返りとして不起訴処分となった。
日本で自己負罪型の司法取引が導入されるべきでない理由…「取り調べ依存」の実態
このように、日本では「捜査協力型」のみが認められ、かつ実際に行われた件数も少ない。これに対し、司法取引の本場ともいえるアメリカでは、水原氏のケースをはじめ、司法取引が頻繁に行われている。なぜか。
川﨑弁護士によると、アメリカと日本の刑事司法制度における被疑者・被告人の権利保障の違いが関連しているという。
「アメリカでは、日本ほど身柄拘束や取り調べが重視されていません。また、被疑者の権利、たとえば黙秘権や弁護人の立ち会いを求める権利が強力に保障されています。
まず、身柄拘束については、今回の水原氏のケースを思い出してください。被害額がきわめて大きいにもかかわらず、保釈金2万5000ドル(約380万円)と設定されるのみで身柄拘束から解放されています。
また、被疑者が黙秘権を行使すると言ったら、あるいは弁護士の立ち会いを求めたら、その時点で取り調べがストップします。捜査機関はその場合、他の方法で証拠を収集することになります。被疑者の権利保障が強く、捜査機関と対等に近い関係が形成されているのです。」(川﨑拓也弁護士)
つまり、アメリカでは、被疑者の権利がかなり強く保障されているという。アメリカで司法取引がよく行われている背景には、このような前提がある。
では、日本ではどうか。川﨑弁護士は、日本の刑事司法制度においては被疑者の防御権の保障が十分ではないと指摘する。
「日本では昔から、被疑者の取り調べや身柄拘束が重視・多用されています。被疑者の身柄を拘束し、取り調べをすることで、自白を引き出すのです。
被疑者には一応、憲法上の権利として黙秘権が保障されています。しかし、被疑者が黙秘権を行使しても取り調べは終わりません。『説得』という名目の下、取り調べ自体は続けられます。
また、取り調べの際、弁護人の立ち会いを求める権利が保障されていません。つまり、被疑者は孤立無援の状態で取り調べを受け続けなければならないのです。
さらに、日本の刑事司法制度は『人質司法』とよばれます。自白しなければ、保釈にならない、つまり自白するまで身柄拘束が続いてしまうのです。それが自白の偏重につながり、冤罪を生むというリスクが指摘されています。
このように、日本では身柄拘束を伴う取り調べに依存する度合いが高くなっているのです。」(川﨑拓也弁護士)

「身柄拘束を伴う取り調べ」への依存は冤罪を生むリスクをはらむ(※写真はイメージです。Hellohello/ PIXTA)
日本で「自己負罪型」の司法取引を導入する上での問題点
これらの違いが、司法取引のあり方にどのような影響を及ぼすのか。まず、アメリカでは、司法取引が被疑者・被告人と捜査機関の間で、文字通りの「取引」として機能するという。
「アメリカの場合、前述の通り、被疑者の地位は強く保障されています。被疑者が黙秘権を行使したらその時点で取り調べは終わるし、保釈もあっさり認められます。
保釈金の支払いさえ必須ではありません。法廷で宣誓させるだけで済ませることもしばしばです。宣誓しておいて逃亡したら法廷侮辱罪に問われますが。
また、公判の前に捜査機関から証拠を開示してもらえることがあります。日本における勾留判断と同様の場面(Initial Appearance)で、すでに一定の証拠開示があり、それをもとに身柄拘束継続の可否が判断されます。
そして、柔軟に保釈を認める結果、被疑者・被告人は自由の身になった状態で、争うか争わないか、司法取引に応じるか否かを決めることができます。弁護士の感覚としては、和解に応じるか否かを弁護士と共に判断する民事裁判とそれほど変わりません。
いわば、捜査機関と対等・フラットな立場で、文字通りの『取引』ができるということです。」(川﨑拓也弁護士)
川﨑弁護士は、日本で今回の水原氏のような「自己負罪型」の司法取引を導入するのは、現状ではきわめてリスクが大きいと指摘する。
「日本では被疑者は事実上、取り調べの対象(客体)として扱われています。また、保釈も自白と引き換えというのが実情と評価せざるをえません。
このような状況で『自己負罪型』の司法取引を導入したら、大変なことになります。捜査機関は延々と取り調べを行い、それでも自白がとれなければ、司法取引を持ちかけるでしょう。無実であっても、身柄拘束が継続していれば、どんなに不利な条件でも飛びつきたくなるのは当然です。昔から、虚偽の自白を誘発するおそれ、黙秘権を侵害するおそれがあると指摘されています。
これらのリスクは、被疑者・被告人の立場が強く保障されているアメリカでさえ指摘されているのです。
もしも今後、日本で『自己負罪型』を導入するならば、少なくとも『人質司法』の問題が解消されること、黙秘権の実効的な保障と弁護人立会権の導入が最低条件です。
現行の刑事訴訟法をはじめとして、刑事司法制度自体を大幅に改める必要が生じます」(川﨑拓也弁護士)
水原氏の事件で司法取引がクローズアップされたことは、期せずして、日本の刑事司法制度が抱える危険性を、改めて強く認識させることになったといえそうである。