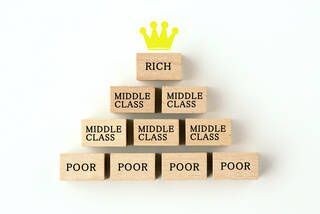1ドル=100円で説明する時代から1ドル=150円で説明する時代へ?
メジャーリーグで大活躍をしている大谷選手の年俸はもちろんドルベースです。これを日本で使う場合は当然、円に交換しなければなりません。海外のお金の話をするとき「○○ドル(日本円で○○円)」「○○円(1ドル○円換算)」のように表記することがあります。
10年位前だと、1ドルを100円で換算して表記することがよくありました。実際には1ドルが90~110円くらいであっても、換算が簡単で分かりやすいからです。1万ドルと言われるより「100万円(1ドル100円として)」のように書かれる方がピンときます。
最近は円安傾向にあることは皆さんもご存じのことでしょう。最近はこの為替レートが1ドル=150円で表記されることが多いようです。円安の傾向が顕著になっており、またその状態で落ち着き始めていることが一因のようですが、同じ1万ドルも「150万円(1ドル150円として)」となってくるとまったく違うインパクトになってきます。
1ドル=100円が150円までシフトしたということは、日本円では50%もの変化が生じたことになります。こうした為替の変動、ライフプラン3.0世代にとっては初めてのことでしょう。
私たちの生活やマネープランにおいて、こうした為替の変動はどう考えていけばいいでしょうか。
(広告の後にも続きます)
円安時代、輸入される商品の値上がりはもう避けられない

円安はまず生活を直撃します。近年の値上げの多くは、原材料が輸入に大きく依存している商品が該当しているからです。一昨年、iPhoneの値上げが発表されたとき、19%位の値上げ幅ということが驚きでしたが、実はそのほとんどが円安要因です。
日本の食料品の多くは原材料を輸入に頼っていますので、この数年で値上げが行われました。国内で生産される食料品についても、原油高や飼料の値上がりなどの影響により値上げする例が増えています。食パンのように、海外での小麦価格の上昇もあいまって、同一年に2回値上げをした例もあります。
電気代、ガス代、ガソリン代などが大きく値上がりしている背景も、円安の影響によります。エネルギー資源を大きく海外に依存していることが利用料金の値上げにつながっているわけです。公共料金については値上げ幅の上限を設定し、日常生活への影響を最小限度にする仕組みもありますが、今度は電力会社などが赤字になってしまい(値上げしてもなお!)、値上げ幅の再引き上げ申請に至っています。
このように、為替が円安に推移していることは日常生活に大きな影響を及ぼしています。為替の変動と同様には、日本国内の給与は増えていきませんから、節約の意識をしっかり持っておかないといけません。「今までと同じように買い物をしていると、今までより月5000~1万円くらい出費が増えている?」となっていたとしたら、それは円安による値上げのせいなのです。
なお、為替の影響だけではなく、海外の原材料費は高騰の傾向にあり、さらに海外の人件費も高騰していますので、今後為替の変動以上の値上がりもあり得ると考えておく必要があります。