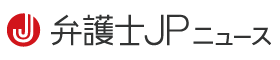今年4月、現職の裁判官、しかも津地方裁判所民事部のトップの裁判長(部総括判事)が、国を相手に「違憲訴訟」を提起する意向を表明し、話題になっている。
竹内浩史判事(61)。元弁護士で市民オンブズマンを務めた経歴があり、弁護士会の推薦により40歳で裁判官に任官し、かつ、自らブログで積極的に意見を発信する「異色の裁判官」である。
本連載では、竹内判事に、裁判官とはどのような職業なのか、裁判所という組織がどのような問題点を抱えているのか、といったことついて、自身の考え方や職業倫理、有名な事件の判決にかかわった経験などにも触れながら、ざっくばらんに語ってもらう。
第3回のテーマは、裁判官のイメージの「ウソ・ホント」。裁判官というと我々一般人が真っ先にイメージする人物像は「世間知らず」「笑わない」「外へ飲みに行かない」「自分の意見を自由に表明できない」「没個性」など、面白み・人間味に欠けるものが多い。しかし、竹内判事はそのようなイメージは実像とは言い難く、むしろ裁判官自身が「演出」している面さえあるという。どういうことか。竹内判事が裁判官の「実像」を赤裸々に語る。(全6回)
※この記事は竹内浩史判事の著書「『裁判官の良心』とはなにか」(弁護士会館ブックセンター出版部LABO刊)から一部抜粋・構成しています。
裁判官は「世間知らずのフリ」をしている?
私が他の裁判官と合議体を組むなどして同僚として接触した限りでは、裁判官は頭の回転が良いことを除けば、「ごく普通の人」たちである。
裁判官が「世間知らず」というのは、世間の側の誤解だと思う。
私のように、弁護士をはじめとする外部との交際を続け、地元新聞のみならず、テレビも毎日長時間見て、世間の情報を仕入れている裁判官は、やや異端かも知れないが、裁判官室ではごく普通に世間話をしている。
私の場合は、司法修習生から「裁判官は人事と天気の話しかしない」「政治的な話を決してしない」などと言われるのが悔しいので、政治批判も避けないし、私のブログでも政治的話題をあえて除外していない。
しかし、私のように口にしなくても、話をしていれば、それぞれが平均的な日本人よりかなり優れた政治的見識や人権感覚を持っていることは分かる。大学法学部以外やロースクール卒業生も含めて、文系の最高学府を出てきた人たちだから、当然だろう。
裁判官の「中立公正」とは?
裁判官は、その意味で「政治的に中立公正」とは言えない。他方で、裁判も大局的には三権分立による国政の一環であり、事案によっては政治性を帯びることは避けられない。
だからこそ、裁判官は積極的に政治運動をすること(裁判所法52条1号)を控え、「公正らしさ」を装わなければならないのである。
裁判官の「公正らしさ」論については、次のような論争が続いてきた。
①裁判官は「公正」だけでなく「公正らしさ」が必要である。
②裁判官である自分は「公正」だから「公正らしさ」は必要がない。
しかし、私は、両方とも間違っていると思う。
③裁判官個人は「公正」ではあり得ないから、「公正らしさ」を装う。
というのが正しいのではないか。
私は、自信をもって自分が公正・中立であると言い切る人を信用しない。
現に、①「公正さ、公正らしさが両方必要」説を吹聴した石田和外(かずと)最高裁長官は、退官して、後の日本会議の結成に加わり議長になった。また、愛媛県靖国神社玉串料訴訟の最高裁大法廷の違憲判決に対し、合憲とする反対意見を書いた三好達(とおる)最高裁長官も、日本会議の会長や靖国神社崇敬者総代になった。
②「公正さのみ必要、公正らしさは不要」説を吹聴する人については言うまでもないだろう。
裁判官が「人事」を気にする理由
裁判官が人事の話題を好むことは否定しない。しかしそれは、私に言わせれば単に「面白い」からである。
あの高裁長官は65歳の定年まであと何年だが、それまでに最高裁に入れるだろうか(最高裁判事の定年は70歳である)といった雲の上の話題も、誕生日のわずか1日の違いで運命が分かれる例もあるので、なかなか面白い。
身近なところでは、次の自分の部の裁判長にはいつ、どこから、誰が来るかという予想は、陪席裁判官には死活問題なので、関心が強い。
これらのことは、程度の差はあっても、官庁や民間企業でも同様だろうと思う。
裁判官は当事者を「だます」こともある?
私は、頭の良い裁判官たちは、むしろ「世間知らず」という誤解を利用しているように思う。
裁判官の見識は、なるべく当事者に知られないほうが有利だ。裁判官が世間知らずで、簡単に言いくるめられると思い込んで、悪人が調子に乗って言い放題に嘘を言い、墓穴を掘ってくれるからである。
大物の悪人(なぜか教育関係者に目立つ)の中には、裁判所は自分の味方をしてくれると信じ込んでいる者もいる。そういう場合は、黙って結審に持ち込んで、バッサリ斬ればよい。裁判官は全てお見通し。判断は極めて容易となる。世間の方こそ、ゆめゆめだまされないように。
ただし、最高裁の有名な「わいせつ」概念の判例のごとく、裁判官が確たる根拠も示さず「社会通念」を認定するのは、好ましくないと思っている。これは「世間知らずの社会通念」と言われても仕方がない。
現代であれば、世論調査の手法の工夫や回数も重ねられており、偏りが生じにくい公正な方法でやれば、かなり正確な意見分布を知ることができる。
世論は時々刻々と変わり得る。裁判所は、当事者双方に調査結果の証拠提出を求め、場合によっては統計関係の官庁に調査嘱託するなどして、世間一般の平均的意見すなわち社会通念を証拠により認定する努力をすべきであろう。
たとえば、「選択的夫婦別姓」の立法化への最近の支持率や、「生活保護受給者に自動車の保有・使用を認めるべきではない」というのが現時点でも国民の多数意見なのかどうかなど、裁判官としても知りたいところである。
裁判官には落語家なみに「芸風」の違いがある
日本の司法は「名もない顔もない司法」(ダニエル・H・フット)と言われる。日本の裁判官にあまりにも個性が見られないからだろう。「金太郎飴」とも揶揄される。
最高裁判事でさえも、一般的には無名である。かつては最高裁判事が新たに就任する際には、全国紙の「ひと」欄で取り上げられるのが通例であったが、最近は目にしなくなった。保守派とリベラル派が熾烈に対立しているアメリカ連邦最高裁判事とは違って、誰でも同じと思われているからだろう。
安倍政権成立以降の最高裁判事指名の結果、裁判官が保守派に偏り、全員一致判決が激増していることも原因だろうか。
しかし、下級審の裁判官の審理方法に個性がないと思われているとしたら、それは大いなる誤解である。常日頃接している地元の弁護士にアンケートを取れば、裁判官に対する評価は大きく分かれるのが普通である。
私は、裁判官には「芸風」があると、司法修習生に教えている。落語家のように、裁判官ごとに入廷時の「出囃子」を変えても面白いと思う。

裁判官はそれぞれ落語家並みに「芸風」を持っている?(※写真はイメージ。photok/PIXTA)
たとえば、古くから裁判官が「判決派」と「和解派」に分類されることがあるが、そんなに単純ではない。地方裁判所・家庭裁判所での裁判の多くは裁判官一人で審理から判決まで担当する「単独事件」である。裁判官は単独事件では他の裁判官の法廷を見る機会がない。したがって、自然と訴訟指揮には大なり小なり個性が出てくる。
証人尋問で、裁判官が積極的に「補充尋問」をするかどうかというのも、極端に意見が分かれるところだ。
補充尋問とは、当事者双方による尋問が終わったあとで、裁判官が必要に応じて尋問することをいう。
私はもともと弁護士で、弁護士会の推薦を得て裁判官に任官した。私が「弁護士任官」に前向きになったきっかけは、弁護士任官の先輩である田川和幸さんの『弁護士裁判官になる 民衆の裁判官をこころざして』(日本評論社、1999年)という名著を読んだことである。しかし、尊敬する田川さんと大きく意見が食い違ったのは、この「補充尋問」の点についてであった。
田川さんは、裁判官は補充尋問をして勝敗を逆転させるようなことはすべきではないとおっしゃっていた。能力不足の弁護士は敗訴させ、依頼者に解任させて、控訴審で交代した有能な弁護士に逆転させるのが筋ではないかと言う。
しかし、私はそうは思わない。そもそも、私の考えでは、裁判官も良い裁判をしたいと考える「プレーヤー」なので、民事訴訟法に規定された裁判官の権限の行使を控える必要はない。
裁判官の立場としても、疑問点はなるべく解消して、すっきりした判決をしたいのである。私が裁判長の法廷では、裁判官3人全員が補充尋問をすることが多くなった。おそらく、かなり珍しいと思うが、合議体全員が真剣に尋問を聞いて考えていることが当事者にも分かってもらえるので、とても良いことだと思う。
他方で、田川さんは『小さな歴史家をめざして~私の弁護士時代』(日本評論社、2014年)という本で、法律家は「小さな歴史家」であるとも書いている。こちらは私も全面的に賛成である。
すなわち、市井の小さな事件であっても、双方の主張のうち、どちらのどの部分が真実に近いか、証拠に基づいて推理し認定するのが裁判官の仕事である。
このように、どこまで証拠調べ(証人・本人尋問)をして解明するかも、裁判官の流儀の大きな分かれ目である。