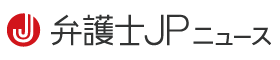14日、介護中だった妻(当時85)の首を絞めて殺害し、殺人の罪に問われている吉田友貞被告(80)の証人尋問および被告人質問が東京地裁で行われた。
事件当時、妻は目がほとんど見えておらず、精神疾患による被害妄想なども悪化。被告は献身的に介護していたが、興奮すると手を付けられなくなることもめずらしくなかったといい、限界を迎えた末の犯行だった。
公訴事実に争いはなく、裁判は争点を量刑に絞り審理が進められている。
朝食には必ず3種類のフルーツ
勾留中から被告と面会し、「更生支援計画書」を作成した刑事司法ソーシャルワーカーは被告の性格について「責任感が強く、他人に面倒を掛けてはいけないと考えているようだ」と説明する。
面談を通じて垣間見えた介護生活のなかでも、特に負担が大きいと感じたのは食事の用意。妻はこだわりが強く、朝食には必ず3種類のフルーツと決まったメーカーの牛乳、トーストを用意していた。その他の食事も、主菜のほかに数種類のおかずを用意しなければならず、買ってきた総菜は煮直す、刺し身は鮮魚専門店で購入するなどの“ルール”もあったという。
被告は当時から、友人や家族に「食事の用意が大変だ」とこぼすこともあったそうだが、それでも「妻の希望は極力かなえたい」との思い、また元来の性格から来る「家族のことなんだから当たり前」という考えから、“苦痛”とまでは感じていなかったようだ。
こうした被告の“心根の優しさ”は、妹たちの証言からも感じられた。
上申書を提出した長妹は「兄は小さいときからおとなしく、真面目で物静か。乱暴しているのも見たことがない」「逮捕後、留置施設で泣きながら『申し訳ない』と言っていた」と証言。次妹は法廷で「おとなしくて優しい性格。きょうだいげんかも記憶にない」「自分のなかで追いつめられてしまったのだと思う」と述べた。
妹たちの証言を聞きながら、被告は口元を震わせ、必死に涙をこらえているように見えた。
妻の“拒否”で介護サービスは利用せず
“たられば”の話にはなってしまうが、被告の“異変”に周囲がまったく気づかなかったわけではない。
事件が起きる1か月ほど前、被告ら4人きょうだいの長姉が亡くなり、被告と妹ふたりは葬儀で顔を合わせていた。その際、妹たちは被告について「ずいぶん痩せちゃったな」と感じたという。
しかし、当時は亡くなった長姉の夫も寝たきりの生活だったため、妹たちは香典返しなど葬儀の後始末で手一杯だった。被告もそれを分かっており、さらには「きょうだい唯一の男である自分が弱音を吐けない」との思いから、助けを求めることはなかったという。
なお、妻は事件当時「要介護1」に認定されていたものの、「(家の中へ)他人に入ってきてほしくない」と言ったため契約しているケアマネジャーやヘルパーはおらず、被告がほぼワンオペで介護を行っている状態だった。精神疾患についても通院や入院による治療が必要だったが、本人の拒否により実現しなかったという。
被告はかつてシルバー人材センターで週に数回仕事をしており、その仲間との付き合いも楽しみのひとつだった。しかし、妻の病状が悪化し徘徊(はいかい)なども始まったため退職。これによって社会的孤立に陥ったと考えられる。
法廷で被告は「本人が嫌がっても介護サービスを利用するべきだった」と語ったが、それが簡単でないことは、当事者になったことがない人にも容易に想像がつくのではないだろうか。
「こんな結末は夢にも思わなかった」
今、妻に対して思うことについて聞かれた被告は「本人は一生懸命生きようと思って、薬も欠かさず飲んでいた。それを奪ってしまって申し訳ない」「妻は怒っていると思う」と、時に言葉に詰まりながら述べた。
妻が元気だった頃、ふたりで「豊かでなくても、穏やかな年寄りらしい老後を過ごそう」と語り合っていたという。「こんな結末は夢にも思わなかった」と、被告は声を震わせる。
現在、被告は保釈されており、次妹の自宅で生活している。朝は次妹がお茶をふたつ用意してくれて、自室で妻に謝りながら、“妻と一緒に”お茶を飲んでいるそうだ。
被告の口から妻への不満は一切出てこず、深い自責の念と、妻への愛情が言葉の端々から感じられた。高齢化が進む今、どうすれば事件を防ぐことができたのか、社会全体で考えていく必要があるのではないだろうか。