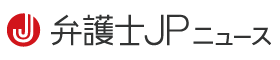東京都の銭湯の入浴料金が8月1日から30円値上げされ、550円になった。これで4年連続の値上げ。1か月を30日として毎日通うと1万6500円かかる計算になる。燃料費の高騰が理由でやむを得ないことではあるが、市民の生活にとって大きな負担となる。
もはや銭湯は「ぜいたく品」と化しつつあるともいわれ、ただでさえ減ってきている銭湯の経営がさらに危うくなるのではないかと憂慮される。銭湯の経営を守るための「規制」はどうなっているのか。その歴史とともに紹介する。
公衆浴場法が定める銭湯の「距離制限」とは
銭湯の経営を守るための規制で最も基礎的なものが「距離制限」である。
銭湯を開業するには、都道府県知事の営業許可を受けなければならない(公衆浴場法1条)。そして、都道府県知事は、「公衆浴場の設置の場所が配置の適正を欠くと認めるとき」は、許可を与えないことができる(法2条2項)。
この場所の配置の基準については、都道府県等がそれぞれ条例で定めることとされている(法2条3項)。たとえば、東京23区では原則として他の銭湯から200m以上離れていることが要求されている。つまり、半径200m以内に他の銭湯が営業していたらアウトということになる(【図表1】参照)。なお、東京都の23区外では距離制限が300m以上となっている。

【図表1】東京23区の公衆浴場の距離制限のイメージ
無許可で営業した場合には刑罰があり、「6か月以下の懲役または1万円以下の罰金」に処せられる(法8条1項)。
実は、過去にこの公衆浴場の距離制限規定が「違憲」だと刑事訴訟で最高裁まで争われた、2件の有名な事例がある。
(1)最高裁昭和30年(1955年)1月26日判決
(2)最高裁平成元年(1989年)1月20日判決
いずれも、好きな場所で公衆浴場を営業できないことは、憲法が保障する「営業の自由」(憲法22条)を侵害するのではないかが争われた。
2つの判決の間に44年の月日が流れている。いずれの判決も結論としては距離制限を「合憲」としたが、その理由付けは大きく異なるものだった。背景には、銭湯を取り巻く経済状況の変遷がある。それぞれについて説明する。
昭和30年(1955年)当時は「銭湯が増えすぎて不衛生になるのを防ぐ」ため
まず、古いほうの最高裁昭和30年(1955年)1月26日判決はどのような内容のものだったか。
福岡県に住む被告人Aは、県知事の許可を得られなかったにもかかわらず公衆浴場を営業したことにより、公衆浴場法違反の罪で起訴された。Aは訴訟のなかで、公衆浴場法の距離制限規定は営業の自由を保障する憲法22条に違反し無効なので、自身は無罪だと主張した。
この事件で、最高裁は距離制限を「合憲」と判断して、Aを有罪とした。その理由を整理すると以下の通りである。
①公衆浴場の設置を業者の自由に任せると、偏在、乱立のおそれがある
②偏在すると、多数の国民が不便を被る
③濫立すると、浴場経営に無用の競争を生じ、経営が不安定になり、浴場の衛生設備の低下等につながる
④このようなことは、国民保健および環境衛生の上から、できる限り防止することが望ましい
つまり、公衆浴場の距離制限は「国民保険および環境衛生」を目的としており、「銭湯が増えすぎて競争が激化し、もうからなくなって経営が不安定になり、衛生設備が低下する」ことを防ぐための規制だとした。
1955年頃といえば、風呂のない住宅が多く、銭湯へ行く人が多かった時代である。戦後の人口の急激な増加ともあいまって、銭湯が増えていたことが推察される。
以下は全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会(全浴連)が発表している組合加入銭湯数の推移のグラフである。昭和30年(1955年)のデータはないが、銭湯の数は昭和33年(1958年)時点で9698。昭和43年(1968年)のピーク(1万7999)に向け、増加傾向にあったことがみてとれる。

【図表2】全浴連加盟組合の加入銭湯数の推移(全浴連調べ)
このような社会情勢の下では、「銭湯が増えすぎる」⇒「過当競争になる」⇒「もうからなくなり経営が不安定化する」⇒「衛生設備が低下する」という理屈にも、一定の説得力があったといえる。
過当競争がなくなっても「距離制限」は”合憲”…そのワケは?
しかし、その後、銭湯の数は昭和43年(1万7999)をピークに減り続けている。「過当競争」のおそれはなくなったといってもいい。「距離制限」は役割を終えたのではないか?
ところが、上記の判決から44年後に出された最高裁平成元年(1989年)1月20日判決は、距離制限を「合憲」とした。どのような内容だったか。
大阪市に住む被告人Bは、公衆浴場の営業許可申請が不許可となったにもかかわらず市内で公衆浴場を営業し、公衆浴場法違反の罪で起訴された。Bは訴訟のなかで、公衆浴場法の距離制限規定が、営業の自由(憲法22条)を侵害し憲法に違反するとして無罪を主張した。
この事件でも最高裁は距離制限を「合憲」としたが(Bは有罪)、その理由付けは、昭和30年判決と大きく変わっていた。整理すると以下の通りである。
①家に風呂がなく公衆浴場に依存している住民のため、公衆浴場を維持・確保する必要がある
②公衆浴場の経営が困難になっており、業者が廃業や転業をするのを防ぎ、健全で安定した経営を行えるようにする必要がある
③そのための手段として、距離制限には十分な必要性と合理性が認められる
銭湯の数が減り続けている決定的な要因は、風呂のある家が一般的になり、銭湯のニーズが減ってきていることである。銭湯業者は零細な家族経営が多く、経営体力も強くはない。経営が困難になれば廃業・転業せざるを得なくなる。
しかし他方で、風呂のない家に住む人にとっては、銭湯は依然として日常生活に必要不可欠なインフラとなっている。そして、風呂なしの家は、風呂がある家と比べて家賃が大幅に安いため、もっぱら経済的弱者が選んで住む傾向にある。
したがって、そのような経済的弱者の人々のために、銭湯が経営困難に陥らないようにして、廃業や転業を防ぐ必要があるというのだ。
現在では、この平成元年(1989年)最高裁判決が、公衆浴場の距離制限に関する一応のリーディングケースとされている。
「規制の存在意義・合憲性」は時代によって移り変わるが…
しかし、銭湯をとりまく状況は、当時からさらに移り変わっている。
1989年の東京都の銭湯の大人料金は295円(30日合計8850円)だったが、前述のように、この8月から550円(30日合計16500円)となり、2倍近くに値上がりしている(【図表3】参照)。

【図表3】令和年間(2019年~)の都内入浴料金の推移(東京都浴場組合公式HP「東京銭湯」より)
このことをさして、昨今、銭湯は「ぜいたく品」になったとさえ言われることがある。
しかし、依然として、風呂なしの家に住むことを余儀なくされている人は存在する。また、銭湯の経営難と廃業・転業の問題も解消されたとはいえない。
他方で、業界あげての必死のPRや業者の経営努力が功を奏しているケースがみられる。新たに参入する業者も現れている。さらに、若い世代を中心に、銭湯の人気が復活してきているともいわれる。
一言で「業界の衰退」「ぜいたく品」などと断じることができない現実がある。
もしかしたら、公衆浴場の距離制限にも新しい意義や機能が生まれているのかもしれない。
時代が目まぐるしく移り変わるなかで、江戸時代に花開いた銭湯の文化は根強く残り続けてきた。今年の夏休みは久しぶりに銭湯へ行き、広い湯舟にゆっくり浸かって、人生にとっての銭湯の存在意義や楽しみ方、これからの銭湯文化のゆくえに思いを馳せてみてはどうだろうか。