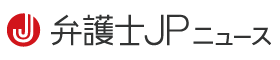長時間労働などの問題を背景に公立学校で「教員不足」が深刻化している実態を受けて、文部科学省の中央教育審議会(中教審)が27日、教員確保などに向けた総合的な方策をまとめた答申を盛山正仁文部科学相に手渡した。
答申では、教員らに残業代を支払わない代わりに月給に応じて一律に支給している「教職調整額」を基本給の4%から10%以上に引き上げるよう求めたほか、教諭ポストの上に若手教諭を支援するポストを新しく設立することも求めた。
また、教員1人当たりの負担軽減のために、現在小学校5、6年生で行われている教科担任制を3、4年生に広げる案や、終業から翌日の始業まで最低11時間を確保する「勤務間インターバル」の導入推進も盛り込んだ。
同日、現役教員ら4人が都内で会見を開き、答申に対する見解を述べた。
調整額上げても「教員の残業は減らない」
現役高校教員の西村祐二氏は「教職調整額を10%以上にするという姿勢は、文科省が現場のために頑張ろうとしてくれていると理解しています」とした上で、増額では公立校教員に残業代が支払われないいわゆる「定額働かせ放題」の問題点は解決しないとして次のように語った。
「教職調整額増額の一番の問題点は、調整額を10%以上にしたところで『教員の残業は減らない』ということです。
現在の枠組みでは、残業は教員が好きでやっていることとして扱われ、業務を課した側、つまり管理職や教育委員会、文科省の責任は問われません。上の立場の者が残業時間に対する支払いも、責任も負わないこの枠組み自体を変えてほしい。今のままでは過労死はなくなりません。
また、若手教員ほど残業が多い実態がありますが、彼らはもともとの月給が低いため調整額増額の恩恵に与れないという問題もあります」

月給に応じて調整額が支給されるため若手教員ほど恩恵は少ない(西村祐二氏による会見資料より)
さらに、若手教員を支援するポストの設立については、「東京都で先んじて導入されている『主任教諭制度』をもとに中教審では議論されてきましたが、調整額を増やすと言いながら基本給を下げるような改革をセットで行おうとしているのではないかと危惧しています」と指摘する。

東京都で導入されている「主任教諭制度」(中教審資料「第10回質の高い教師確保特別部会」2024/3/13より)
東京都では2009年、「教諭」の上に「主任教諭」というポストを設け、主任教諭に手当てをつける形で給与の増額を計った(主任教諭制度)。しかし、その一方で「教諭」の基本給は下がったといい、西村氏によれば、現在、東京都の「主任教諭」の月給と他県の「教諭」の月給がほぼ同じという現象が起きているという。
こうした事例も踏まえ、西村氏は「文科省には新ポスト設立の制度化には動いてほしくありません。もしこの制度を作るとしても、決して誰かの基本給を下げないということを約束してもらいたいと思います」と語った。
「増額してあげたんだから」仕事増加の不安も
現役小学校教員の齋賀裕輝氏は、教科担任制を広げる案については評価。教職調整額の増額についても「ありがたい」が、一方で「『増額してあげたんだから、もっと仕事をしてくださいね』となる可能性があって、不安もあります」と明かす。
「教員は残業をやりたくてやっているわけではなく、私も定時で帰って子どものために明日も元気に学校に行けるようにしたいです。
しかし、ネットなどで“なんでも屋さん”だという風に言われている通りで、事務仕事やカウンセラー的な仕事、子どもたちに何かあった時には警察のような仕事もします。子どもたちに授業をして、勉強を教えることが本来の仕事だと思っていますが、こうしたさまざまな仕事があって、授業をするための準備ができないこともあります。
これからも現場で勤めたいと思っていますが、このままだと正直不安です。文科省には給料を増やすということだけではなく、教師の仕事を減らすということに重点を置いて動いてほしいと思っています」(齋賀氏)
小室淑恵氏「教員不足が解決するとも到底思えません」
民間企業などの働き方改革を多く手掛け、公立学校でも250校のコンサルティングを行った「株式会社ワークライフバランス」の小室淑恵氏も会見に参加。
教職調整額を設定し、教員らに残業代を支払わない根拠にもなっている「給特法(教員給与特別措置法)」がある限り、教員の労働に対する対価が正当に支払われることはないとして給特法を維持させる文科省の姿勢を批判した。

答申の内容について語る小室淑恵氏(左)(8月27日 都内/弁護士JP編集部)
そもそも教職調整額は、給特法創設当時(1971年)8時間程度だった教員の残業実態に合わせて「4%」とした経緯がある。
これを踏まえ小室氏は、「教職調整額を10%に増額するということは、残業時間を20時間にするということです」と説明。
しかし、2022年の公立校教員の月間残業時間は小学校で82時間、中学校で101時間と1971年の10倍以上に膨れ上がっている。また、国は2016年から教員の残業時間の削減に乗り出しているが、2022年までの6年で20時間未満しか削減できていない。

小室淑恵氏による会見資料より
「教員の残業時間を20時間にするために、国は一体何年かけるつもりなのでしょうか。(教職調整額の)予算ありきなのか、現実的とはとても言えず、今回の答申を受けて教員不足が解決するとも到底思えません」と小室氏は指摘し、長時間労働の抜本的な改革に向け以下のように提言した。
「給特法のもとでは、残業は教員個人の責任で、管理職が指示していないことになっています。残業時間を減らしたとしても、管理職の評価の対象にはなっていないのです。今回の答申の中にも、残業を減らした管理職の評価が上がるとか、逆に残業時間の規定をオーバーさせている管理職の降格といったことは全く書かれていませんでした。
本来であれば給特法を廃止し、教員に正当に残業代を支払う。残業時間についてコスト換算し、その削減が管理職の評価につながるということが、長時間労働の解消に重要なことではないでしょうか」