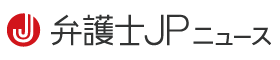「非行少年の支援は、時にやけどじゃ済まないこともある」
そう語るのは、大阪府東大阪市で非行少年たちの更生支援に取り組むNPO法人「チェンジングライフ」理事長、そしてキリスト教の牧師でもある野田詠氏(えいじ)さんだ。かつては自身も暴走族幹部として迷惑行為を繰り返し、鑑別所と少年院に収監された過去を持つ。
現在は主に、少年院や刑務所から出てきた若者に衣食住や職の支援を行っているが、手を差し伸べた者たちからの裏切りや、支援の失敗は数知れない。それでも野田さんは決して諦めず、「誰もがやり直せる」と信じ活動を続けてきた。
なぜ元暴走族幹部が牧師となり、さらに若者たちの自立を支えてきたのか。野田さんの“人生をかけた戦い”を聞いた。
暴走に窃盗、覚せい剤使用…荒れていた若者時代
野田さんは10代で暴走族に所属し、窃盗や暴力行為などで少年鑑別所に入ったのち、19歳のときには少年院送致となった。在院中に出会った三浦綾子の小説と聖書に影響を受け、生き方を変える決意をしたという。
「少年院に入るきっかけになったのは、仲間たちとの共同危険行為(※暴走族の集団走行)でした。自分たちのチームから100人が暴走に参加していて、表面的には僕が仲間をかばって代表者として逮捕された形です。だけど心の中では、『仲間をかばわないと地元に帰ったときにリスペクトを受けられない』という自己愛ばかりでした」(野田さん、以下同)
不良としての自分は格好よくありたい。そんな考えにとらわれていたある日、1冊の小説に出会う。実話を基に、鉄道事故から乗客を救うために自ら線路に飛び降りたクリスチャンの青年の生涯を描いた、三浦綾子の『塩狩峠』だ。野田さんは「読んだとき、自分の自己愛を見透かされた気がした」と語る。
「普通なら身体がすくんでしまう状況で、主人公は他人のために動いた。僕は不良の『殺すぞ殺してみろ』という虚勢の中で生きてきたから、誰かのために命を差し出せるなんて容易でないと思っていました。それで主人公の行動を後押ししたのは神の力じゃないかと、目に見えない力を信じる気になりました」
そこからキリスト教に興味を持つようになったものの、人生の迷いは晴れなかった。
「窃盗や暴走はもう卒業せなあかんなと思っていましたが、覚せい剤だけは卒業する気持ちになれていなかった。『薬物は自分の身体に入れるもんやから、人に迷惑をかけていない』と自分に言い聞かせて正当化していたんですね。でも、聖書にある『神の目には、すべてが裸であり、さらけ出されています』という一文を読んで、またしても自分の心を見透かされた気持ちになりました」
小説と聖書に感銘を受けた野田さんは、少年院を退院後、奈良県の神学校生駒聖書学院に進学。牧師の資格を取り、非行少年たちの社会復帰を支援する活動を始めた。
「同病相憐れむと言うんでしょうか。自分自身が非行や犯罪から離れられた経験があるので、加害行為から抜け出すきっかけさえあれば、非行少年でも普通に生きていけるはずだと感じていて。彼らを手助けしたいという気持ちでスタートしました」
仕事先を紹介するも裏切られ…
現在に至るまでの24年間、約150人の若者に衣食住を提供し、相談などを含めると300人以上の支援を行ってきた。就職や進学などで自立していった若者たちとは今でも連絡を取り合っているが、支援がうまくいかなかったケースも無数にある。
「6年ほど前でしょうか。紹介した仕事先で空き巣を働いた子がいました。親から虐待を受けていて、児童自立支援施設にも入っていた難しい子です。少年院から出てきたところを引き受けたんですが、僕のことを“第2のおやじ”みたいに慕ってくれていました。彼を信頼して僕の後輩の会社を紹介したものの、クビになってしまって。逆恨みするかのように、仲間と一緒に工具や機械100万円分と車2台を会社から盗み、その車で人を跳ねたんです」
恩をあだで返す行為に、野田さんは深い落胆を覚えた。「『世話になっている人やその関係先では迷惑をかけるな』という暗黙のルールがあるはずだと思っていました」と、当時の気持ちを振り返る。
「仕事の紹介先は、僕たち支援者にとってすごく貴重。仕事が決まれば人生も安定するし、その子がうまくいったら次の子も紹介できる。だから就職先というものに対して、僕は並々ならぬ気持ちがあるんです。まして、紹介先は大切な後輩の会社です。後輩に対する損害に心が折れて、彼の少年審判に呼ばれたとき、正直『もう行かんとこう』と思いました。でも僕が行かずに放っておいたら、自暴自棄になるのではないか。結局審判に行って、『ちゃんとしろ』と厳しく𠮟りました。2回目の少年院送致だったので、彼は長期という処分(処遇)になりました」
少年の退所から今年で3年。彼はまだ1度も再犯せずに過ごしている。退所後1度だけ、野田さんに会いに来たそうだ。
「10万円を持ってきて、『これ、会社の社長に渡しといていただけませんか』と。ここまで困ったケースは初めてでしたが、非行少年に仕事を紹介するというのは、やけどじゃ済まないこともあると感じた失敗でした」
ひとりの若者を通して知った「支援の連続性」
若者支援を行う中で、PTSDと同様の「二次受傷」を負ってしまったり、「何もできなかった」と悔やむことも少なくない。それでも活動を続けるのはなぜか。野田さんは忘れられない体験を語ってくれた。
「ある男の子の支援をしたときのことは、今でも心に残っています。その子は複雑な生い立ちをたどっていて、乳児院、児童養護、里親、児童自立、里親、少年院と、ずっと社会的養護のもとで暮らしていました。17歳のときに2回目の少年院に入るも引受先が見つからず、20歳になる直前まで退院できなかったんです」
少年院は引受先がなければ、20歳を迎えるまで退院できない。少年は今までの里親先で暴行や窃盗を繰り返していたため、複数の支援団体から引き受けを断られ続けていた。
「里親先での非行行動は“愛着の歪み”を物語っているので、支援団体側も『これはちょっと難しいな、無理だな』となっちゃうんですよね。彼は法務省の更生保護施設での受け入れをすべて断られて、6つのNPO団体からも断られていました。そこで、僕たちに声がかかったんです」
「行き先のない子を助けたい」との思いから、野田さんは彼との面会に行き、引き受けると決めたという。
「窃盗癖がひどいと聞いていましたが、僕たちからお金を盗むことはなかった。暴力性だけが少し残っていたけど、暴言を吐くくらいで実害もありませんでした。ただ周りからは、『あんな誰も引き受けない大変な子を受け入れてすごいね』と言われましたね。僕たちは若者を引き受けるとき、その子とよりよく関わるために、それまでの支援者に『彼を引き受けるためのアドバイスをください』と連絡します」
少年を引き受けるにあたり、それぞれの施設や過去の里親に連絡を取った野田さん。そこで2人目の里親から、こんな話を聞かされたそうだ。
「その里親さんは宗教家の方で、里親になることに自信を持っていたそうです。けど実際に引き取ってみたら、盗む、殴る、と散々で。最終的には『ちゃんとできなくてごめん。里親をなめていた』と泣いて彼を児相に戻し、それ以降は里親自体を辞めてしまった。でも、その里親さんを含めいろんな人が彼に関わってきて、彼の膿(うみ)を少しずつ吸ってきてくれたからこそ、僕たちが引き受けたときには少し落ち着いていたんだと思います」
野田さんはそれを、「支援の連続性」だと表現する。
「その子は知能が高い子だったから、やたらと勘が鋭かったんですね。彼の中で、『あんなことをしていたから引き受けてもらえなかったんだ。次は同じことをしないでおこう』と考えたんだと思います。だから僕たちのところに来たときには、窃盗癖だけは直っていた。支援者が失敗だと思っていても、長い目で見れば支援に貢献していることもあるかもしれない。だからこそ、若者たちと関わっていて傷つくことがあっても、丁寧に接しよう。僕たちが膿を吸うことで、次の支援につながるかもしれないから、と考えています」
支援の中にあるキリスト教の教え
支援活動を行う上で、野田さんは自分自身を「支援者と思っていない」と話す。
「気持ちの上では、“回復共同体の先行く者”と思っています。仲間みたいな感じですね。もちろん、そんな言葉で表現できない場面もあります。だけど心の中では仲間だと思っているから、絶対に上から目線にはならないし、『受け入れたってんねんぞ』って態度はしない。僕だったら、そんな大人のところで世話になりたくないですからね」
若者と接する際は、「特別なことは何もしないで一緒にいる。話をしてくれたらただ聞くだけ。考えを押し付けない」を大切にしているそうだ。聖書にある「あなたがたがゆるさなければ、天の父はあなたがたをお許しになりません」の一節を用い、野田さんは言葉を続ける。
「自分は若者を応援する立場だと誤解していると、心無い言葉や裏切りを許せなくなります。でも、自分自身も許された罪人だと思えば、迷惑をかけられたからといって『許さん』という発想にはならないですね。腹が立って『なんやねん』と思うことがあっても、最終的には聖書の教えに従って、会いに行く。
聖書には『あなたのパンを水の上に投げよ。のちの日になってそれを見いだそう』という言葉もあります。人に対して何かすること、応援するってことは、水の上にパンを投げているようなもので、無駄に見えるかもしれない。でも、いつかきっと実がなる。そういった教えが自分の中にあるので、『やめとこうかな、向いてないな』と思う日があっても、励まされて戒められて続けています」
他人の人生に介入し、自立を支えるのは容易ではない。時には深く傷つくこともある。取材の最後に野田さんは、「子どもたちからいろんな学びをさせてもらっている。自分も一緒に育っているような気持ちを持っています」と、今まで巣立っていった若者たちとの写真を見せてくれた。そこには、まるで家族のように笑い合う若者たちと野田さんの姿があった。