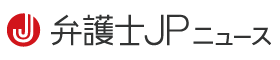10月の衆議院議員選挙で与党が過半数割れした影響を受け、政党間の政策協議をめぐり、“凍結”状態にある「ガソリン税」の税率を引き下げるしくみ「トリガー条項」を発動させることの是非が話題になっている。
しかし、そもそも「トリガー条項」が存在する前提には、1974年以降、50年にわたって継続している「当分の間(とうぶんのあいだ)税率」とよばれる課税措置がある。
「当分の間税率」はどのような内容のものか。そして、法的観点からどのような問題が指摘されるのか。YouTube等を通じて、納税者の視点から税金・会計に関する情報発信を精力的に行っている、黒瀧泰介税理士(税理士法人グランサーズ共同代表、公認会計士)に聞いた。
ガソリン税と自動車重量税の「当分の間税率」の問題
まず、ガソリン税の税率が、50年前に「暫定的な措置」として引き上げられたまま、現在も同じ税率が維持されているという問題が指摘されている。なお、「自動車重量税」にも同様の問題がある。
JAF(日本自動車連盟)等により「当分の間税率」と呼ばれている問題であり、ガソリン税の「トリガー条項」が設けられた原因ともいえる。
この点については、ガソリン税と自動車重量税の歴史的経緯を振り返る必要があるという。
黒瀧税理士:「ガソリン税と自動車重量税は、かつて『道路特定財源』といい、その使い道が道路の整備・維持管理に限られていました。
税率はもともと、ガソリン税が1リットルあたり28.7円、自動車重量税が0.5tあたり年2500円でした。
しかし、1974年に『道路整備の財源が不足している』という理由で、高い『暫定税率』が設けられました。
特例税率は、ガソリン税が1リットルあたり53.8円、自動車重量税が初度登録の年からの『車齢』に応じて0.5tあたり4100円⇒5700円⇒6300円となっています。
その後、2000年代のいわゆる『構造改革』の一環として、2009年以降『道路特定財源』が廃止され、使い道が限定されない『一般財源』に組み込まれることになりました。
大きな理由は、道路の整備水準が向上し『特定財源税収が歳出を大幅に上回ることが見込まれる』というものでした(※)」
※出典:国土交通省「道路特定財源の一般財源化について」

ガソリン価格の高騰は国民生活に重大な影響を及ぼしている(※写真はイメージ HIME&HINA/PIXTA)
「暫定」だったはずの“高い税率”が50年も維持された「理由」とは
道路特定財源(ガソリン税・自動車重量税)の税収が歳出を大幅に上回るようになったならば、理屈としては、「暫定税率」は役割を終えたということになるはずである。本来、廃止するか、あるいは一般財源に組み込むにしても、少なくとも税率を元に戻すのが筋ではなかったのか。
黒瀧税理士は、ガソリン税と自動車重量税が一般財源に組み込まれた際、税率を「暫定税率」と同じ数値で維持するにあたり、政府・与党によって「理由の差し替え」が行われたという。

黒瀧泰介税理士(税理士法人グランサーズ提供)
黒瀧税理士:「不思議なことに、当時は『役割を終えたから廃止すべき』という原理原則に則った議論はあまり行われなかったようです。
政治家の多くも、マスコミの報道も、『道路特定財源』が『道路族議員の既得権となっているのはけしからん』などの理由で『一般財源化』を支持する論調が大勢でした。また、国民の多くもそれを支持しました。
そんななか、当時の政府・与党は『厳しい財政事情』と『環境面への影響の配慮』を理由として、『暫定税率による上乗せ分を含め、現行の税率水準を維持する』としました(上記資料参照)。
そして、名称が『暫定税率』から『特例税率』に改められ、まったく同じ数値のまま引き継がれました。これが『当分の間税率』と呼ばれるものです。
つまり、法理論上は、ガソリン税・自動車重量税を存続させて『暫定税率』を実質的に維持する理由が、もともとの『道路の整備のため』から、まったく関係のない『厳しい財政事情』『環境面への影響の配慮』へと差し替えられたことを意味します」
「租税法律主義」が形骸化するおそれも
税率を高く設定する理由が失われたにもかかわらず、別の理由に差し替えて存続させる。このことには法的観点からどのような問題があるか。
黒瀧税理士:「税金のことは国民代表機関である国会が決め、コントロールしなければならないという『租税法律主義』(憲法84条)が、実質的に骨抜きになるおそれがあります。
当時の政府・与党が挙げた理由のうち、『厳しい財政事情』は単に税収を維持したいという意味にすぎず、『環境面への影響への配慮』についての説明も決して十分とはいえません。
従来の『暫定税率』とまったく同じ税率を維持する合理的な理由が説得的に示されたとは言い難いでしょう。
政府の提案で『一時的に』税率を引き上げたら、元の理由が失われても、新たに何らかの理由・名目を設けさえすれば、同じ税率を維持していいということになりかねないのです」
なお、昨今、政党間の政策協議で、ガソリン価格が所定の額を超えて高騰した場合に「特例税率」の適用が自動的にストップする「トリガー条項」が話題になっている。これは2010年に当時の民主党政権が主導して設けられた。しかし、2011年3月に起きた東日本大震災をきっかけに、復興の財源を確保するという名目で、特別法により「凍結」され、今日までに一度も発動していない。
自動車税の「環境性能割」にも「差し替え」の問題
同様の問題は、2019年9月をもって廃止された「自動車取得税」と、同年10月から導入された自動車税の「環境性能割」の関係にもあてはまるという。
黒瀧税理士:「2019年9月に廃止された『自動車取得税』は、自動車を購入した年に課税され、税率が原則として車両価格の3%(軽自動車は2%)で、『エコカー減税』により軽減されるというものでした。
これに対し自動車税の『環境性能割』は、自動車を購入した年に、車両価格の0~3%(軽自動車は0~2%)が課税されるものです。燃費性能が高いほど税率は低くなります。
『自動車取得税』は、もともとは『ガソリン税』『自動車重量税』と同じく『道路特定財源』で、一般財源に組み込まれたものです。
これに対し、自動車税の『環境性能割』は、CO2削減のために燃費の良い車を優遇するものです。
実質的にまったく同じ内容の税金を、名目上、別の制度に差し替えたものだとの指摘がなされています」
ガソリン税の「トリガー条項」の凍結を解除すべきか否かが物議を醸している。しかし、そもそもの前提として「当分の間税率」の問題がなければ存在しえなかったものである。それが設定され、今日まで継続してきた背景をみると、「租税法律主義」(憲法84条)の問題が浮かび上がる。
黒瀧税理士の指摘にもあるように、一時的なものだったはずの増税措置が長期間、しかも途中で理由がまったく別のものに差し替えられ、同じ内容で継続することは、租税法律主義の観点からは決して望ましいものとはいえないだろう。
近代国家の始まりとされる「アメリカ独立革命」「フランス革命」はいずれも、税制に対する国民の不満がきっかけで起きた。それらの原動力となった「代表なくして課税なし」という言葉に象徴されるように、租税法律主義は、わが国の憲法で規定されている以前に、近代国家の大原則といわれる。私たちは主権者・納税者として、租税法律主義が形骸化しないよう、国会、政府が適切な税制を定めているのか、絶えず監視していく必要があるだろう。