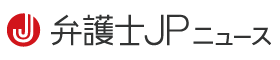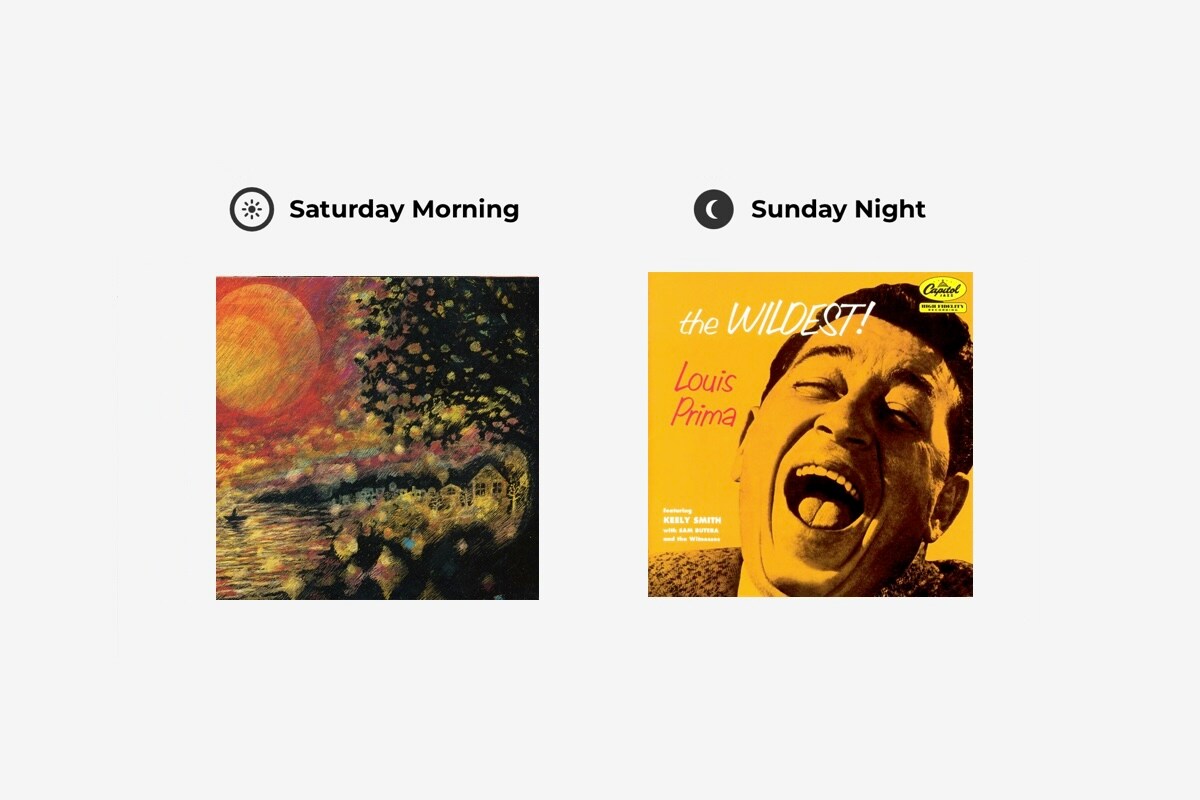11月5日に実施されたアメリカ大統領選挙では、約7466万票と226人の選挙人を獲得した民主党のカマラ・ハリス副大統領(現在)に対し、約7710万票と312人の選挙人を獲得した共和党のドナルド・トランプ前大統領が勝利した。
今回の大統領選に関しては、過去にもまして「SNSやインフルエンサーなど、インターネットが強く影響した」との主張が多く見受けられた。また、同月17日に実施された兵庫県知事選で斎藤元彦前知事(当時)が勝利したことを受けて、日本国内においても選挙とインターネットの関係が取り沙汰されている。
一方で、メディア研究者は、テレビを筆頭とする「オールドメディア」が今回の大統領選でも強い影響を与えたと指摘する。
Xでは共和党を有利にする「アルゴリズム変更」が行われた可能性
今回の大統領選については、「X(旧Twitter)」を問題視する声がとくに多い。背景には、オーナーであるイーロン・マスク氏の方針によりXが共和党支持者や保守派にとって有利な場になっているとの懸念がある。
7月、マスク氏は大統領選でトランプ前大統領(以下「トランプ」)を支持すると公言。以降、自身のXアカウントでトランプへの投票を呼びかけ、またジョー・バイデン現大統領やハリス副大統領を非難する投稿を繰り返した。
I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF
— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024
トランプ支持を表明したマスク氏の投稿
さらに、「おすすめ欄」に表示される投稿などXのアルゴリズム自体が、共和党に有利になるよう人為的に操作されているのではないかとの疑惑は、以前から浮上していた。
選挙後にオーストラリア・クイーンズランド工科大学のティモシー・グラハム助教授とマーク・アンドレイェビッチ教授が発表したワーキングペーパーによると、2024年1月1日から10月25日までにXで投稿されたアカウントの内容やエンゲージメントなどを統計的に調査・分析したところ、マスク氏がトランプ支持を表明した7月から、マスク氏や共和党支持者のアカウントの閲覧数や「いいね」の数が不自然に急増していたという。
これらの結果は、共和党に有利になるようにアルゴリズム変更が行われていた可能性を示唆する、とグラハム助教授らは指摘している。
「X離れ」やBlueskyへの移行が進むが…
上述のアルゴリズム変更の問題などもあり、選挙直後には「今回の大統領選ではXが大きな影響を与えた」との主張も散見された。
そして選挙結果を受け、「X離れ」が進んでいる。開票が進んだ11月6日には、マスク氏による旧Twitter買収後では1日最多となる約11万5000人がXのアカウントを停止したという。
一方、Xの代替として民主党支持者やリベラル派から評価されている「Bluesky」では、選挙直後の数日間には1日あたり約100万人もの新規アカウントが開設されていた。2023年1月にサービスを開始したBlueskyの利用者数は今年9月17日に1000万人を突破、そのわずか2か月後の11月20日には2000万人を超えており、利用者の急増は明らかだ。
他方で、マスメディアやインターネットの問題に詳しい、慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所の津田正太郎教授は「SNSの影響力は過大評価されやすい」と釘を刺す。
「そもそも、メディアが人々の行動や意識に及ぼした効果(『メディア効果』)を測定することは、非常に難しいのです。
たとえば、『X利用者の間ではトランプに対する支持が強かった』という統計が出たとしても、それだけでは、もともとトランプを支持していた人がXを利用しているのか、Xを利用し始めてから支持するようになったのかが判別できません。あるいは、Xの利用とトランプ支持とを結びつける第三の変数が存在しているのかもしれません。
因果関係を確定させるためには、厳密な方法に基づくパネル調査などが必要になります」(津田教授)
Xの影響力は過大評価されやすい?
Xの利用者数はアメリカが世界最多であるとはいえ、そもそも人口の多いアメリカのSNS全体においてXが占める割合は少ない。FacebookやTik Tok、InstagramのほかPinterest(ピンタレスト)や Linkedin(リンクトイン)など日本では馴染みの薄いSNSもアメリカでは利用されている。
一方、日本はXの利用者数が世界二位であり、アメリカと比べると他のSNSは活用されていない。そのため、日本では、他国におけるXの影響力が過大評価されがちだ。
ただし、Xは画像や動画ではなく文章の投稿が主であり、また比較的オープンなプラットフォームであることから、Xの投稿は他のSNSやメディアに「コピペ」されて拡散されやすい傾向がある。
また、ジャーナリストや研究者など社会的な発信を頻繁(ひんぱん)に行う人物はXを利用している場合が多い。そのため、Xで話題になっている問題が選挙の争点にもなるという「アジェンダ設定効果」が発生しやすい。
そして、トランプもXに多数の投稿を行っている。津田教授が指摘するのは、トランプの言動には「予測困難」という特徴がある点だ。
「もともとトランプの言動は予測が困難で、揚げ足を取られることを恐れて無難な発言を繰り返す政治家に比べ、ジャーナリストが思わず注目したくなるところがあります。Xへの投稿も同様で、多くのジャーナリストはつねに彼のポストに注目しています。
しかも、政治的にきわめて大きな影響力をもつ存在となったいまでは、その発言が過激であるほど、ニュース・バリューは大きくなり、彼に批判的なジャーナリストであっても無視することはできません。
結果として、報道自体は批判的であっても、トランプの意見をXの外に拡散させ、その影響力を増させることになるのです」(津田教授)
兵庫県知事選でも見られた「主流メディア」批判
トランプの選挙戦略の特徴として、テレビや新聞などの主流メディアを「敵」と位置付けることで、自身が「エスタブリッシュメント(既得権益)」に反対しているかのような印象を指示者に与える点がある。
先の兵庫県知事選でも、斎藤知事を側面から応援していた立花孝志・「NHKから国民を守る党」党首や、斎藤知事を応援するネットユーザーなどが主流メディア批判を行っていた。
トランプは前回(一期目)に大統領に就任してから、徐々に主流メディア批判を強めていき、2018年には自身に批判的な記事を「フェイクニュース」と非難して、一部のメディアを「国民の敵」とまで断じた。
また、2020年の選挙で敗北した際にトランプは「選挙不正があった」と主張し、その主張を信じた支持者たちが2021年1月6日に米国議会議事堂を襲撃した際には、現場にいた記者も「敵」と見なされ攻撃の対象になったという。
津田教授は、トランプや斎藤前知事に限らず、日米における「主流メディア」批判は、具体性を伴わず恣意(しい)的であると指摘する。
「実際の報道の問題を具体的に指摘するよりも、『主流メディア』という仮想敵を作ることのほうが重視されます。
『主流メディア』をエスタブリッシュメントの一部とし、そこから抑圧されている自分という構図をつくることで『われわれ』対『彼ら』の対立軸を演出します。そのことが支持者への求心力を増すことにつながるのです。
また、アメリカの場合には、ニューヨークタイムズ、CNN、ABC、CBSなどが『主流メディア』と認定され、日本では新聞から民放、さらには週刊誌までもが『オールドメディア』とまとめられて批判されています。
一方で、保守派のケーブルテレビ局であるフォックスニュースは多数の視聴者を抱えるにもかかわらず、『主流メディア』とはみなされません。
具体的にどのメディアのどこが悪いといった議論よりも、『偏向したメディアが一体となってわれわれを攻撃している』というイメージをつくることが重要なのです」(津田教授)
また、近年ではアメリカの右派は「大学」もエスタブリッシュメントに位置付けて攻撃の対象にしている。とくに人文系の学問を修めた高学歴者には、民主党支持者が多いためだ。
一方で、理数系やビジネス系の学問では、支持政党の偏りは小さい。批判者はこの事実を無視して「大学」全体を攻撃の対象にしており、主流メディア批判と同様の恣意性が見受けられるという。
保守系メディアは虚偽やデマを拡散しやすい
IT法を専門にする研究者のヨハイ・ベンクラー教授(ハーバード大)は、アメリカのメディア環境は「リアリティチェック・ダイナミクス」と「プロパガンダ・フィードバックループ」の二種に分かれる、と論じている。
大半のマスメディアは前者に位置しており、あるメディアが間違った情報を発信した場合には、別のメディアが情報を修正することが多い。一方、後者に位置するメディアは虚偽の情報やデマが修正されず、拡散され続ける。
津田教授は「党派的な話に聞こえるかもしれないが…」と前置きしたうえで、民主党支持者が接触するメディアは「リアリティチェック・ダイナミクス」に、共和党支持者が接触するメディアは「プロパガンダ・フィードバックループ」に位置付けられると指摘する。
ただし、その理由は「左派の人はリテラシーが高い」「右派の人はデマにだまされやすい」などといった個人の能力や特性の違いにあるのではない。民主党支持者のあいだでも、自分たちに都合のよいデマが流通することはあるからだ。
むしろ重要なのは、アメリカにおけるテレビやラジオなどマスコミュ二ケーション・メディアをめぐる環境の時系列的な変化であるという。
「公平原則」の廃止が右派メディアを台頭させた
日本を含めた多くの国には、放送業者に対して程度の差はあれ「政治的公平」を義務付ける法律がある。しかし、アメリカにはない。アメリカにも過去には「公平原則(フェアネス・ドクトリン)」が存在したが、ケーブルテレビの普及やメディアの多様化などの要因から、共和党のレーガン政権時代の1987年に廃止された。
公平原則の廃止により、フォックス放送やタレントのラッシュ・リンボー氏によるラジオ局など、右派のメディアが台頭した。これらの右派メディアは、意見と事実との区別を曖昧にしたトークで人気を博す一方、既存メディアの「偏向」を攻撃することで自らの政治的プレゼンスを向上させていった。結果として、既存メディアは「中立」を保っていても、右派メディアと比較されて相対的に「左寄り」と見なされることになった。
遅れて左派のメディアも立ち上がったが、先に右派メディアが台頭し、既存メディアとの対立軸が形成されていたがゆえに、大きなプレゼンスを獲得することはできなかった。民主党支持者は、右派のメディアや政治家の虚偽を批判する既存メディアに満足していたためだ。
以後、共和党支持者は新興の右派メディアを、民主党支持者は既存メディアを情報源とする構図が続く。さらに、インターネットの発達に伴う新興ニュースサイトやソーシャルメディアの登場はメディア環境の分断をよりいっそう進めることになった。
しかし、既存メディアは、事実を重視する規範をもつため、民主党支持を明言していたとしても、同党に有利な虚偽やデマを意図的に報道することはまれだ。また、仮にある既存メディアが民主党にとって有利な虚偽を報道したとしても、前述の「リアリティチェック・ダイナミクス」により別の既存メディアに修正される。
一方、右派のマスコミを中心としたメディア環境では、共和党にとって有利な虚偽は修正されづらい。また、既存メディアが修正を行っても、「既存メディアは左寄りだから信用できない」などのレッテルを貼られてプロパガンダ・フィードバックループの内側では無視されるため、虚偽の修正が共和党支持者にまで伝わらなくなる。なお、この環境には「Breitbart(ブライトバート)」などのインターネット上のニュースサイトも含まれている。
結果として、今回の大統領選でも、トランプは共和党を支持するテレビやラジオ、インターネットサイトを通じて自身に有利な虚偽やデマを全国に発信することができた。選挙の背景では、既存メディアと新興メディアとの非対称な構図が影響していたと津田教授は指摘する。
日本でも「放送法4条」は問題視されているが…
日本民間放送連盟(民放連)が掲げる「報道指針」の2条「報道姿勢」では、「われわれは取材・報道における正確さ、公正さを追求する」と宣言されている。
一般的にも、マスコミやジャーナリストが守るべき報道倫理においては、間違いや虚偽のない報道を行う「正確性」と、政治的に中立な観点から報道を行う「公平性」とが同時に求められる。
しかし、アメリカの現状は「正確性」と「公平性」の両立が困難になる場合があることを示しているという。右派・左派のどちらか片方が虚偽を繰り返し発信している場合、それを放置すると「正確性」が侵害されるが、修正した場合には「公平性」が侵害されてしまうためだ。
「前回も今回も、大統領選テレビ討論会において、トランプは不正確な発言や虚偽の発言を大量に行いました。今回のケースで話題になったのは『ハイチ系の移民が住民のペットを食べている』です。
一回目のバイデンとトランプとの討論会の司会者は、公平性を優先して虚偽を放置したことで民主党支持者に批判されました。二回目のハリスとトランプとの討論会では、司会者は正確性を優先して討論会の最中に介入し、虚偽を訂正したことで共和党支持者に批判されました」(津田教授)
なお、今回の討論会ではハリス副大統領も不正確な発言を行い、司会者はその発言を修正しなかった。後日、トランプは「討論会は不正操作されていた」として、主催したテレビ局(ABC)の放送免許取り消しを求めたが、却下された。また、虚偽の数も度合いもトランプの方が大幅に上回っており、この一件をもってABCが民主党側に肩入れしていたとは認定できないという。
The Rhetoric, Lies, as exemplified by the false statements made by Comrade Kamala Harris during the rigged and highly partisan ABC Debate, and all of the ridiculous lawsuits specifically designed to inflict damage on Joe’s, then Kamala’s, Political Opponent, ME, has taken…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2024
討論会の「不正操作」を訴えるトランプ前大統領
もともと、アメリカの既存メディアの「偏向」批判は、左派の側が積極的に行っていた。既存メディアは営利企業であり、広告主の意向も働くため、資本主義を補完する役割しか果たせないという認識があったからだ。
ところが、ニクソン政権のころから右派の側で既存メディアに対する「リベラル偏向」批判が目立ち始め、そのさいには左派によるメディア批判の論理を取り込んでいったという歴史がある。
また、日本では放送法4条によって「政治的に公平であること」が定められているが、この条文の解釈をめぐってたびたび議論が起こっている。
従来、放送法における政治的公平は「局」単位で判断されてきた。つまり、あるテレビ局が放送する番組全体に偏向が見受けられない限り、一つの番組で特定の政党を批判するなどの行為は報道・表現の自由の範囲内として許容されてきた。
しかし、2015年5月の参議院総務委員会にて、高市早苗総務大臣(当時)は「一つの番組でも、極端な場合は政治的公平を確保しているとは認められない」と答弁。翌年2月の衆議院予算委員会でも高市大臣は「番組」単位で判断する旨の答弁を行い、安倍晋三総理大臣(当時)も高市大臣の見解を許容したことから、東京弁護士会が抗議の会長声明を発表した。
現在でも総務省の公式見解は「番組」ではなく「局」単位の判断としているが、日本の報道関係者や左派のあいだには「放送法4条を根拠にして、政府が報道に対して恣意的な介入を行うのではないか」との警戒が根強く残っている。
一方で、公平原則を廃止したアメリカではマスコミを通じて虚偽が蔓延(まんえん)し、国民の政治的対立が深まる結果となった。
「難しい問題ですが、放送法4条の廃止はパンドラの箱を開いてしまう可能性があり、慎重に考えたほうがよいでしょう。
この条項はあくまで倫理規範でしかなく、むしろ選挙期間中にはもっと踏み込んだ放送が求められているほどです。それでも、廃止された場合には、多くの人が思い描いているのとは全く異なるメディアが出現する可能性があると思います」(津田教授)