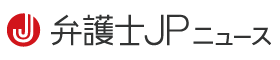医療や福祉の現場で働く労働者らからなる日本医療労働組合連合会(医労連、加入人員数約16万人)は2月17日、都内で会見を開き、「2024年 介護施設夜勤実態調査」の結果を発表した。
この調査は特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホームなどの介護現場で働く職員の夜勤状況を全国規模で把握するため、毎年実施しているもので、今年が12回目。
医労連で介護対策委員会事務局長を務める寺田雄氏は「長時間労働や出勤回数など、介護現場での夜勤状況が全く改善されていないことは明らか。過酷な状況がずっと続いている」と訴えた。
約40%が“指針超えて夜勤”
介護施設での夜勤形態は、大きく分けると3交代制勤務での夜勤(3交代夜勤)と2交代制勤務での夜勤(2交代夜勤)の2種類がある。3交代夜勤の場合は8時間の勤務が基本で、2交代の場合は16時間前後の勤務になる。
調査の結果、2交代夜勤を実施している施設が全体の88.4%を占めており、そのうち84.8%の施設では、16時間以上の長時間勤務が行われていることがわかった。
さらに、2交代夜勤の場合、1人の職員で夜勤を担当している職場が67.1%あり、寺田氏は「2階建ての建物で、2人が夜勤をしているように見えても、実質的にはそれぞれが1フロアずつを担当していて、1人夜勤が行われているケースもある」と説明した。
介護には夜勤回数に関する上限規制がないものの、看護師の場合は、月の夜勤日数を8日以内(2交代夜勤に換算すると4回以内)とする国の指針がある。この指針を今回の調査結果に当てはめた場合、2交代夜勤で働く人のうち約40%が指針を超えて夜勤に従事していることになるという。
加えて、回答のあった施設のうち、32.7%の施設には仮眠室が無く、特に看護小規模多機能型の施設では60%が設置無しという結果になった。
ほかにも、利用者の生活リズムにあわせるため、職員の勤務シフトの種類が平均で5.1通り、もっとも多いところでは9通りとなっていることなどが明らかになったという。
これらの調査結果を踏まえ、日本医労連では3月中に厚労省に対する要請行動を予定していて、寺田氏は「複数人体制での夜勤を原則とすることや、休憩をしっかりとれる体制の整備を求めたい」と話した。
「帰宅時に意識もうろう」
この日の会見には、オンラインで各地の労働組合関係者も出席。次のような詳しい実態が語られた。
「1フロアを1人で見ているので、何かあった時にすぐ反応するため、トイレに行くときにも扉を開けたままにしなければならない」
「16時間勤務後、帰宅する際に意識がもうろうとしてしまい、帰路の途中で事故を起こしそうになったという報告を一定数以上うけている」
「いったい誰が、介護職をやりたいと思うのか」
また、会見に参加していた東京医労連の松﨑美和書記次長も以下のようにコメントした。
「基本的に私たち人間の体は夜は寝るようにできていますが、介護の現場では夜間であっても働かなければならず、当然眠たくもなりますし、パフォーマンスも落ちます。
なぜ、普通に日勤で働く場合は8時間の労働なのに、夜勤になると突然、16時間以上の労働が横行するのでしょうか。
これはグループホームで働く方からよく聞く話ですが、グループホームには基本的に休憩室がなく、廊下に布団などを敷いて“仮眠にもならない休憩”をとることがあるそうです。
ケアが必要な人のために働いている、介護職員への待遇がこのような状態で良いのでしょうか。
みなさんには、『自分の健康も管理できない状態に追い込まれている人々に、面倒を見てもらいたいですか』と問いかけたいです。
2人で夜勤をしている場合であっても、片方が休憩時間に入ると、結局1人で全体を見なければならなくなります。
確かに“1人”ではありませんから『何かあれば、もう1人を起こせばいい』と思うかもしれません。ですが、極力休ませてあげたいと思い、1人で頑張る場合も多いですし、起こしに行っている間にまた別のトラブルが発生することも考えられます。
『夜勤の時間帯は利用者が寝ているから職員の人数を減らして大丈夫』と考えるのではなく、日勤帯で必要としている人員と、同じ数の人員を夜勤にもあててほしいです。
また、夜勤で働く場合、基本的には手当がつきます。ですが、それでも介護職の賃金は全産業平均よりも7万円以上低いと言われています。
夜勤によって、精神的にも体力的にも負担がかかるからこそ、手当がついてもなお、全産業平均より賃金が低い状況で、いったい誰が、この先介護職をやりたいと思うのでしょうか」