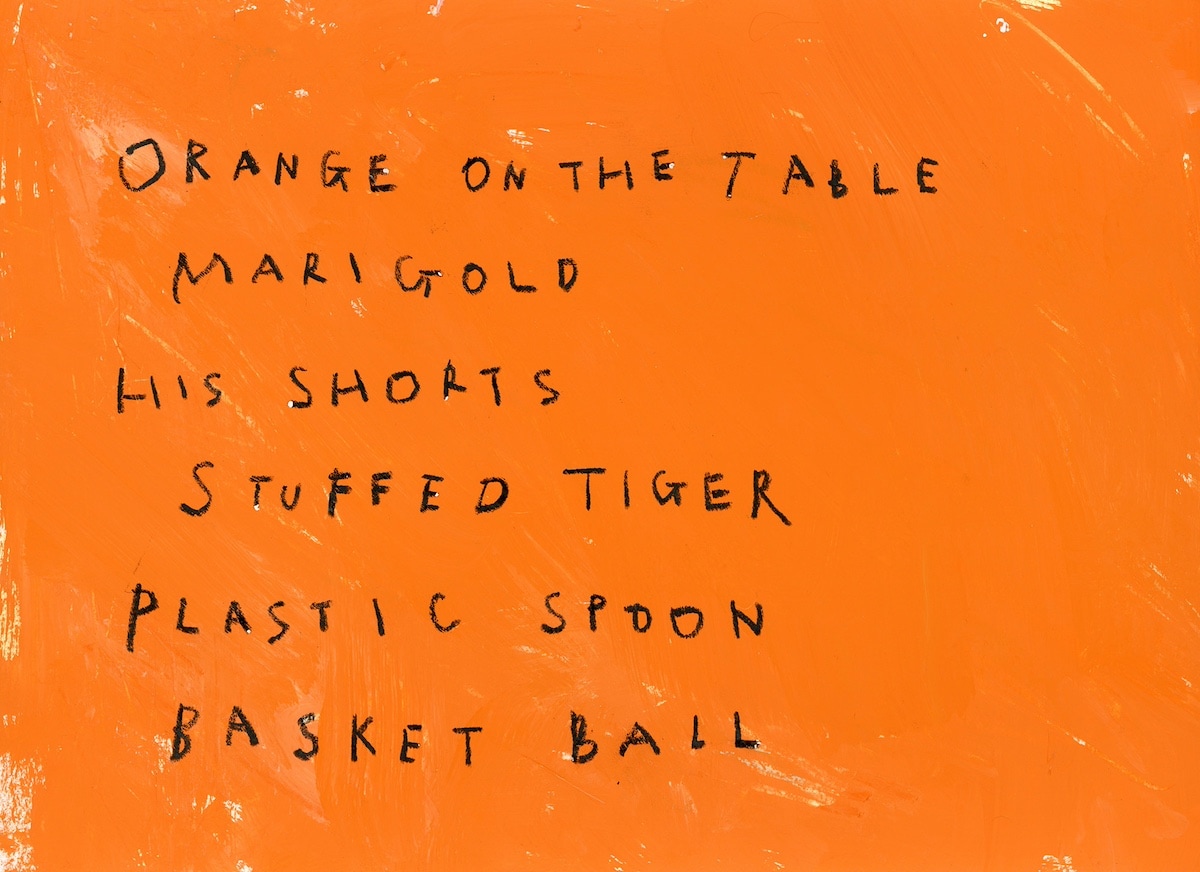港区・西麻布で密かにウワサになっているBARがある。
その名も“TOUGH COOKIES(タフクッキーズ)”。
女性客しか入れず、看板もない、アクセス方法も明かされていないナゾ多き店だが、その店にたどり着くことができた女性は、“人生を変えることができる”のだという。
タフクッキーとは、“噛めない程かたいクッキー”から、タフな女性という意味がある。
▶前回:32歳女が、抱える秘密。高校時代からの親友に言えずにいる「あの夜」のこととは
Customer 1:富崎小春(とみさきこはる・32歳)【親友の恋人を愛した女】
「店長さんは、誰かの結婚式に…出たくないなって思ったことはありますか?」
客である富崎小春にそう聞かれた店長のともみは、ないですね、とだけ短く返した。
ただし正確には、“女友達がゼロなので結婚式なんて招待されたことすらない”というのがともみ・28歳のリアルだが、小春は、普通はそうですよね、と自分を責める口調で続けた。
「私は今日…逃げたいと思ってしまったんです。大好きな先輩の結婚式なのに…」
数時間前に小春を親友と呼んでくれる結衣からかかってきた電話。『結婚式の日取りを決めたいんだけど小春には親友としてスピーチをお願いしたいの。だから小春の都合も聞きたくて』と、式の候補日として数日を提示されたのだ。
結衣が長年の恋人である良太のプロポーズにイエスと言ってからまだ2週間ほどしかたっていないのに、もう結婚式の日取りの話とは。良太が早く入籍したい、結婚式の日取りも決めたいってはしゃいじゃって困るの、と言いつつ結衣の声はうれしそうだった。
なんとか平静を装い「スケジュールを確認してまた連絡するね」と電話を切った瞬間、小春は、もうこれ以上はダメだと震えた。
結衣に対する裏切り、後悔、罪悪感、そしてきっと未練。それらにどう決着をつければ…と感情がぐちゃぐちゃになったとき、この店のことを思い出したのだ。
「ショップカードに…一歩踏み出したいとき、あなたの決断をお手伝いしますって…」
書いてあったのは本当ですか?…と小春が続けようとしたとき、あっ!と声がした。声の主は、小春が座るカウンター席の逆端でグラスを磨いていた、フワフワとしたパーマヘアを一つにまとめたもう一人の店員だった。
店長と小春の視線を受けた彼女は、てへっ、という感じの笑顔で続けた。
「お話始まっちゃったところで申し訳ないんですけど、店長、お客様に契約書をお見せしないと。まだですよね。取ってきます?」
― 契約書…?
頭にハテナが浮かんだ小春をよそに、店長はハッとした顔になり、ごめんルビー、お願いしてもいい?と言った。
この女性はルビーさんという名前なのか…などと小春が思っている間に、その“ルビーさん”は店の奥の部屋に消え、何かを手にして戻ってきた。
手にしていたのはクリアファイルで、それを受け取った店長が、その中から数枚の紙を取り出した。
「こちらを見ていただけますか」
カウンターの上を滑らせるように、小春に差し出されたそれは。
「…秘密…保持契約書…?」
驚いた小春のその呟きに、はい、と答えて店長は続けた。
「お客様がここでお話されたことは絶対に洩れません、というお約束を契約として交わすために弁護士の方に作っていただいたものです。もちろん私たちスタッフはこの契約書がなくても、ここで見聞きしたことを他言することなどありませんが…」
まずは読んでいただいて…という店長の説明を聞きながら小春はその書類に目を通していく。
小春の仕事はアメリカに本社がある大手スポーツ用品メーカーの営業職だ。日本独自の商品開発などに関わることも少なくないので、NDAとも呼ばれるこの手の秘密保持の契約書は見慣れたものではあるのだが、秘密を持つ側ではなく、共有される側が契約書を作るということは珍しいのではないだろうか。その上…。
「損害賠償、1,000万円」
万が一、店側の責任で客の情報が漏洩したと明らかになった場合、その損害賠償として最低でも1,000万円がその客に支払われると書かれていた。その金額設定が破格であることは法律の素人である小春にもわかるし、具体的な損害賠償額を契約書に書き込むなんて普通はありえないことだろう。
「…ここまでする理由は…?」
小春の疑問に、そう思いますよね、店長が笑いながら何かを取り出した。
「うちって変なお店でしょう。このショップカードには店の住所も連絡先も載せていないですし」
店長が取り出して見せたのは、小春があの日、SneetというBARでもらったものと同じショップカードだった。書かれているのは店名とQRコードだけ。そしてQRコードを読み込むと。
【BAR TOUGH COOKIES】―心が壊れそうな夜。踏み出す勇気が欲しい夜。そんな夜には当店へ。あなたの決断をお手伝いします―
あの文章のページへ飛ぶようになっている。そしてその文章の下に、ご来店ご希望の方はお電話をと電話番号が記されていて、電話をかけ住所を聞いた小春は今ここにたどり着いているわけだが。
「あの文章を読んで、この店に来たいと思うお客様ってほとんどいらっしゃらないと思うんです。警戒される方の方が多いかと。詐欺とか怪しい商売への勧誘が溢れかえっている世の中ですしね」
苦笑いした店長に、そうだと小春も思い出した。あの日一緒にこの店の紹介文をみた結衣は、変な勧誘の文章みたいで気持ち悪いと言って興味をもたなかったのだから。
「あのメッセージ読んでこの店を訪ねてくださる方には“何か”がある。うちはそんな“何か”がある方々のために作られた店なんです」
「何か、ですか…?」
「はい。あのメッセージが響くような“何か”…心が壊れそうな“何か”や、現状を変えたい“何か”。行き場のない葛藤、誰にも言えない秘密に苦しんでいらっしゃる方とか」
「でも、私の話は…そんな…」
確かに小春も今まで誰にも話せずにきた“秘密”は抱えている。それが苦しくてここに来た。
けれどこんなに本格的な契約書を見せられるほどのことでは…と気が引けた小春の不安を破ったのはルビーの「あ~もう、ちょっとちょっと~」という声だった。
「店長の話し方がカタいからさぁ~、お姉さん…じゃなくて富崎さんが困っちゃってるじゃぁん。っていうか富崎さん、下のお名前なぁに?」
ルビー、失礼でしょ!という店長の静止も聞かずに、ルビーは小春の隣によいしょと座ってから、もう一度、下のお名前は?と聞いた。
「…こ、小春、です」
「じゃあ、小春ちゃんって呼んでもいい?」
「え?あ、は、は、い、大丈夫です…」
「ルビー、今すぐ立ちなさい。お客様の席に座るなんて…」
「私はルビー。本名だよ♡で、この店長さんはともみさん」
「ルビーやめなさいってば!…うちの子がすみません、富崎さん…」
「い、いえ、大丈夫です」
「まあまあ、ともみさん落ちついて♡」
店長が怒り、小春が呆気にとられるなか、ルビーはニコニコと続けた。
「この契約書、持ってきておいてなんなんだけど、別に絶対サインしなきゃいけないわけじゃないんだよね。
一応うちの店のルールで最初にお見せすることになってるんだけど、万が一の時の保険が必要なお客様用というか…私はこんな約束までしてもらわなくて大丈夫ですって思う人はサインしなくていいんだよ。サインしなくても秘密は守られるんだし。ね!ともみさん」
ふぅ…という小さな吐息は店長…ともみのもので、その後、申し訳なさそうに
「はい、もちろんサインするかしないかはお客様の自由です。そのこともこれからご説明するところでしたが……いらぬ乱入が…お騒がせしてすみません、富崎さん」
「い、いえ」
「ということで、小春ちゃんはサインなし、ってことでオケ?」
ルビーの軽さに小春は救われたような気持ちになり、はい、と頷いた。
「オッケー!じゃ、改めて、小春ちゃん、お話の続きをど~ぞっ♡あ、ともみさん、私にもお酒を何か一杯くださぁ~い」
「あなたにお酒は出しません。富崎さんすみません、この子のことは気にせずよかったら…」
お話の続きをどうぞというともみの穏やかな笑顔と、どうぞどうぞ~というルビーの明るい声に、小春は緊張が徐々に解けていくのを感じ…これまで誰にも打ちあけることができなかったこと、今日ここに来ることになった…その続きを話し始めた。
◆
「結婚式のスピーチを頼まれた結衣先輩とは…高校時代からの付き合いで…」
結衣と小春が所属していた都内の高校のテニス部は、強豪校として知られていた。背が高くボーイッシュなルックスの結衣は、後輩たちからは高嶺の花的存在のキャプテンで、小春もただ遠くから憧れている1人に過ぎなかった。
けれど小春が結衣と同じ大学に進みテニス部に入ったことで共に過ごす時間が増えると、背格好も似ていたせいか、姉妹なの?と言われる程に2人の距離は縮まった。
小春にとっての結衣は、人間関係も学業も、将来の進路も…迷ったらいつも導いてくれる、大好きな先輩、眩しい太陽のような存在で。
大学を卒業して結衣は広告代理店に、小春はスポーツ用品メーカーに就職してからも週に1度は会い、時には小春が結衣の相談にのることも…という関係になった。
「小春って本当に頼りになる。大人になってからの親友ってありがたいな~」
いつしか結衣に親友だと呼ばれるようになったことが、小春はとてもうれしく誇らしかった。
結衣に良太を紹介されたのは…今から3年前のことだった。医師として海外のNPOで働いていた幼なじみが帰ってきて、食事に行くから小春も一緒にいかない?と誘われたのだ。
ケニアから帰ってきたばかりだという良太の日焼けした笑顔と穏やかな語り口に、今思えば小春は、出会ったその日から好感を持っていたのだと思う。けれど。
良太が結衣を好きなことはすぐにわかった。その優しい瞳が常に結衣を追っていたから。
「良太さんって…結衣先輩のこと好きなんですか?」
3人での何度目かの食事を終えた帰り道、結衣の当時の恋人が結衣を迎えに来て、それを2人で見送った後で小春は良太に聞いた。
「うん、好き。実は、中学生の頃から何回か告白してるけど…その度にふられてる。でも何回ふられても一番は結衣なんだ。他の女の子とも付き合ってみたけど、やっぱりダメで…ずっと好きなんだよね」
あっさりと認めて、爽やかな笑顔でそう言った良太の、その笑顔に胸が痛んだことで、小春は良太への恋心を自覚してしまった。
けれどその時の、“他の女の子と付き合ってもダメ”という言葉と、自分が結衣に勝てるわけはないという思いで、気持ちを伝える勇気がないまま時が過ぎて。
「私と良太、付き合うことになったよ」
照れ臭そうな結衣、そしてこの世の全てを手に入れたかのような喜びにあふれた笑顔の良太にそう報告されたのは、小春が良太と出会って半年が過ぎた頃、3人でお花見に行こうと結衣に誘われた日だった。
「傷心の結衣に付け込んで、ついに長年の片思いが報われました!」
ピースを作った良太の誇らしげな報告に、何その言い方と突っ込む結衣のそのやりとりを笑うことができた自分に小春はホッとした。
ショックを受けなかったわけではない。
でも、長らく付き合っていた恋人にふられて傷ついていた結衣が良太の優しさに癒やされたのだと思うと、素直に良かったと思えたし、何より小春は2人が大好きだったから。
2人が幸せな姿を見せ続けてくれたなら、自分の片思いなんてそのうちに消えていくのだろうと思っていたけれど。
「良太にプロポーズされたんだけど…断っちゃった…」
それは今から2年程前。結衣と良太が付き合い始めて10ヶ月ほどが経った冬の日のことだった。
良太は本当に優しいけれど、結婚となると彼でいいのか確信が持てないという結衣に、小春は結衣と出会って以来初めての苛立ちを覚えてしまったのだ。
「…どうしてですか?あんなに結衣先輩のこと大切にしてくれる人は他にはいないと思うんですけど」
口調が強くなった小春に結衣は少し驚いたような顔をしながら、それはわかってるし、良太といると安心できるんだけどさ、と言って続けた。
「幼稚園の頃から知ってるからかな…良太に雄みをイマイチ感じられていないというか、男性としての良太を愛せてるのか…っていう迷いが再燃しちゃって…」
― 何、それ…!?
その苛立ちは良太への心配に変わり…。
『大丈夫ですか…?結衣先輩から話を聞きました』
連絡をして、初めて2人で会うことになった良太はとても弱っていた。
「結衣にふられることには慣れてるはずなんだけど…プロポーズを断られるって思ったより堪えるね」
その苦笑いが切なくて小春は、関係がダメになったわけじゃないんですから…と慰めたけれど、良太は弱々しく首を横に振った。
「…たぶん、オレじゃダメなんだよ。今はまだ結婚とか考えれないだけって言ってたけど…ほら結衣ってさ、今までもっと色気のある、オレについてこいってタイプとばっかり付き合ってたでしょ」
オレとは真逆だよねと自虐的にワインをあおった良太が、今回はもう本当にダメかもしれないなぁと笑った。
「ずっと一緒にいるのに、結衣の好きは全然増えないというかさ…。そんなこと片思いの時は全く気にならなかったのに、付き合えたからって欲張りになっちゃって…ダメだな~オレ」
「ダメじゃないです」
小春は思わず、声を荒らげていた。
「好きな人に欲張りになるのは当たり前です。結衣先輩がズルいんです」
「…小春ちゃん?」
心配を含んだ良太の視線に小春は、初めて結衣の悪口のようなことを言ってしまったことに気づいてうしろめたくなった。でも。
「良太に雄みをイマイチ感じられていないというか、男性としての良太を愛せてるのか…」
そう言った結衣の言葉を思い出すと、もう止まれなかった。
「良太さんは素敵です。人としても、男性としても」
勢いで言い切った小春に良太は驚いて、同情でもうれしいよと笑った。その笑顔に胸が締め付けられて、小春は飲めない酒をあおるように流し込んだ。
◆
「…うわ、なにその…ありがちな展開…このあと、やらかす未来しかないよね?」
呆れたようなルビーの突っ込みを、うるさいよ、とともみが制して、小春に続きを促してくれた。
「…ほんとに…あの日はどうかしてたんです。今日はとことん付き合いますってことになって、飲み続けることになったんですけど、私も良太さんもアルコールにそんなに強くないから、気がついたら…」
「一緒に寝てた?」
またも突っ込んだルビーに小春はおずおずと頷いて、でも、と続けた。
「最初は良太さんの家でただ眠っていただけだったんです。たぶん2人とも酔っ払い過ぎて、なんとか帰宅したけど、すぐ意識を失ったって感じで。
でも…夜中にベッドに並んでいる状態で目が覚めて。良太さんは私に背中を向けて眠っていたんですが、この時を逃すともう2度と告白できないって思って、その背中に抱きつきました。酔いも残ってて、あの…お酒の力を借りてしまおうって」
「…あ~アタシ、酒の力で何とかしようとする女って大っきらぁい~。あ、でも続きをどうぞ?」
ルビーの反応はトゲトゲしいものなのに、どこか優しくて小春はそれをありがたく思った。
「良太さんの背中に抱きついて、好きですって言いました。そしたら…彼…振り返って抱きしめてくれて。私、舞い上がっちゃって。抱きしめ返したらキスしてくれて。その後、なだれ込むように…行為に…でも…」
思い出すと後悔しか浮かばず、小春は顔を歪ませながら懺悔の思いで言葉を探す。
「途中で…結衣、オレも大好きだよ、って言われたんです。彼はかなり酔っぱらっていましたし、寝ぼけていたのもあって間違えたんだと思います。私と結衣先輩を。
最初はそれでもいいって思っちゃったんです。結衣先輩の代わりでもいいって。でも…何度もうわごとみたいに、結衣大好き、大好きだよ結衣、って繰り返されるから…耐えられなくなって。言っちゃったんです。私は、結衣先輩じゃないよ、って」
すると良太はゆっくりと自分の腕の中をのぞきこみ、そのぼんやりとした瞳の焦点を合わせ始めた。そして。
「彼、ハッとして。えっ!?って驚いて。ベッドから転がり落ちちゃったんです。ごめん、小春ちゃん、ごめんって何度も謝って。でも私…許しませんでした」
そう、許さず逃がさなかった。小春は…ずっと好きだったと伝えたのだ。でも。
オレは、結衣が好きで、結衣だけなんだ、ごめん、と。苦しそうに返された良太の言葉に、小春は…服のはだけた状態でそれを聞く自分がとてもみじめに思えて、感情が爆発してしまった。
「どうして?って。なんで何度もふられても結衣先輩がいいの?って。結衣先輩は、良太さんのことを男性として愛せているか不安だって言ってたよって。そんな人より私の方がずっと、良太さんの良さがわかるのに、って言ってしまったんです。
…絶対に…伝えてはいけなかったのに」
「うわぁ…最悪じゃん」
ルビーの呟きに、本当に最悪ですよね私、と返しながら小春は忘れたくても忘れられないあの時の良太をまた思い出す。良太は傷ついた顔をしながらも小春を気遣い、ごめん、とまたつぶやいたのだ。
小春はすぐに後悔した。なんてことを言ってしまったのだろう。良太を傷つけるつもりはなかったのに。どうして、どうしてこんなことに。
ぐちゃぐちゃに混乱して、ベッドの上に座り込んだまま涙があふれて止まらなくなった小春を良太がそっと抱きしめてくれた。
ごめんと繰り返しながら背中を撫ぜ続けてくれる温もりが、自分の告白への拒絶なのだと知りながらも、その温もりに酔い甘えが出た。それはずっと…恋焦がれた温もりだったから。
「結衣先輩には絶対内緒にするから…今日だけ…今夜だけ抱きしめて眠ってほしい」
良太は何も答えなかった。それでも小春を抱きしめたままやがて良太は眠りに落ち…一睡もできなかった小春が、一度だけ…良太の唇に触れるだけのキスをしたことにも、朝まで気づくこともなかった。
◆
「なにそれ~。つまり、セックスは途中でやめたけど、そのあと抱っこしてもらって眠ったと。小春ちゃんもだけど、その男も最悪ぅ~。いい大人がセックスなしで抱きしめ合って眠るだけとか、むしろガッツリ浮気セックスされるよりイヤじゃない?結衣さんって人かわいそぉ~」
「ルビー…。あなたうるさすぎるから今日はもう退場ね。奥で在庫確認でもしてなさい」
ともみに叱られ、はぁ~い、と素直にルビーは立ち上がった。その後ろ姿が奥に消えるのを待って、ともみは申し訳なさそうに眉を寄せた。
「スタッフが本当に…大変申し訳ありませんでした。もうご気分を害されてしまったかもしれませんが…でも、もしよろしければ…続きをお伺いしても?」
強要を感じないその穏やかな声に、小春は思わず涙がこみあげそうになり。それをごまかすように、また話し始める。
「…翌朝、良太さんに、気持ちが伝えられたからもう諦めると。吹っ切れたと伝えました。
私は新しい恋を探すし、今日のことは絶対に結衣先輩には言わないので、良太さんも、結衣先輩のことをあきらめないでって伝えました。そしたらありがとうって言われて。それで握手をして別れました」
「そのことは…結衣さんという方は今もご存じないんですか?」
「もちろん知りません。私が無理やり良太さんを押し切ったので、彼が浮気したわけでもありませんから。
あの後、結衣先輩が良太さんに別れ話をしたり…色々あったんですけど…良太さんはずっと…結衣先輩に愛を伝え続けて…そのうちに結衣先輩の方が良太さんに夢中かもっていうくらいになって。
私も…後ろめたさは抱えながらも、2人を応援できていたつもりでした。でもつい最近…2度目のプロポーズが大成功して…」
「…いざ結婚式と聞いたら、出席したくないと?」
「…怖くなったんです。裏切った私が、親友としてスピーチなんて許されるのかと…」
「どうしてですか?」
「…え?」
「私が小春さんなら必ず結婚式に出て、絶対にスピーチもしますけど」
その言葉に戸惑ったように顔を上げた小春は、ともみの眼鏡の奥の瞳の、その光の強さに射貫かれたようにひるんだ。
「だって、小春さんは、そんなに悪いことをしたとは思えないんですよね」
「…え?」
悪いことをしていない…?そんなわけはないと小春は反論する。
「だって、私は…良太さんに告白して体の関係を持とうとしました。拒絶された後も、抱きしめて眠ってもらって、それに結衣さんが、良太さんのことを男として見れないって言っていたことも告げ口のように伝えて…」
「でも、そんな小春さんの、卑怯で体当たりな告白にも良太さんの気持ちは揺るがなかったわけですよね?それどころかその後諦めずに結衣さんに愛を伝えて、その愛を実らせ結衣さんと良太さんはこれから幸せになろうとしている」
つまり…とともみが続けた。
「小春さんが過ちだと思っているその裏切りとやらは、結衣さんと良太さんの人生になんら影響を与えていないんですよ。むしろ良太さんにとっては、小春さんの行動が結衣さんを諦めないきっかけになったかもしれない。
小春さんは良太さんに、結衣さんのことを諦めないでと伝えたわけでしょう?」
と、ともみは笑った。小春の脳裏に、握手をして良太の家を出たあの朝の光景が蘇ってくる。
「でも…私が大好きな結衣先輩のことを裏切ってしまったのは事実なんです。それに良太さんへの想いが今も…」
良太にふられてから、恋はしようとしたし、他の男性とも付き合ってきた。なのに…結婚が決まったと結衣から報告された時、小春は、まざまざと良太への未練を思い知らされたのだ。
「つまり…あなたは壊したいんですか?2人の今の幸せを」
「…そんなことはありません……でも、一生に一度の結婚式なのに…裏切った私が親友のスピーチなんて…先輩に申し訳なくて…ならばいっそ、嫌われた方が…」
「嫌われる?裏切りを告白して?でも今、結衣さんが真実を知れば、どうなります?」
「それは…」
「2人の結婚は壊れるでしょうね?壊れなかったとしても間違いなく2人を傷つける。その場合小春さんも2人との全てを失うでしょう。
墓場にまで持っていくべき秘密とも言いますが、誰かの幸せを壊す真実なら話さない方が良いこともあります。それに…結衣さんと良太さんの物語において、小春さんは脇役なんです」
「…脇役…」
「そう。小春さんはこの恋物語においてずっと脇役でした。というか主人公になる努力をしなかった。私は小春さんの…今回の裏切りにつながる失敗は、あなたが思うよりももっと手前にあったと思います」
手前に?と聞いた小春に、ともみが淡々と続ける。
「結衣さんと良太さんが付き合う前なら、小春さんにも正々堂々と告白するチャンスはあったはずです。それなのに好きだと思いながら行動に移さなかった。なぜですか?」
「あの時は…彼が結衣先輩をずっと好きだと言ってましたし…他の女の子ではダメだという話も聞いていたから…」
「自分が動かなかったことへの言い訳を、この先もずっとそんな風に探し続けるんですか?」
ともみの言葉に、小春はハッとしたように固まった。
「小春さんにも主人公になれるチャンスはあったんです。でもそのチャンスにトライしなかったから、小春さんは闘わずして脇役になった」
闘わずして脇役に…その響きが、小春の胸をえぐる。
「結衣さんと良太さんが付き合う前に、一度でも気持ちを伝えるなどの行動に移せていれば、たとえふられたとしても未来は違ったはずです。
でも行動しなかったことで小春さんは片思いを悶々とこじらせ…大好きな先輩を裏切ることにつながったのではないでしょうか。そして今も過去に囚われたままです。
小春さんと違って、結衣さんと良太さん2人は行動し続けたから主人公になれた。そして過去の失敗を乗り越えて未来に進んだわけです。特に良太さんは一度断られても結衣さんを諦めずに愛を伝える努力をして愛を実らせた。
そんな主人公たちの努力を…幸せを壊す行動に出るのなら、それはもはや脇役ではなく悪役の仕業ということになります。小春さんには悪役として…2人の憎しみも恨みも受けとめながら生きる覚悟はありますか?」
「…悪役…」
「まあ、悪役には結構な才能が必要ですし、小春さんにその才能はなさそうですけどね」
「…私は…どうするべきでしょうか…?」
呆然と呟いた小春にともみは、私の意見を求めていただけるならば…とほほ笑んだ。
「もし、悪役になりきれないのなら。結衣さんのことが大好きで、結衣さんへの申し訳ない気持ちがあるなら尚更、小春さんが選ぶべき道は…結婚式に出て、親友として心を込めてスピーチをすることだと思います。
そして人生の晴れ舞台で輝く2人の、その最高の笑顔を目に焼き付ければきっと、その幸せを壊す過去の真実など話すべきではないと確信できるのではないでしょうか?」
ともみは、それができたなら、と続ける。
「過去の自分を…過去の小春さんの失敗や後悔を、今の小春さん自身が許してあげて欲しいんです。これ以上自分を罰し続けないでください。もう十分に苦しんできたはずですから」
そして、カウンターの上に置かれていた小春の手をそっと、握った。
▶前回:32歳女が、抱える秘密。高校時代からの親友に言えずにいる「あの夜」のこととは
▶1話目はこちら:「割り切った関係でいい」そう思っていたが、別れ際に寂しくなる27歳女の憂鬱
▶NEXT:3月13日 木曜更新予定
SNS裏アカ炎上した女優の孤独。仕組まれていた罠とは?