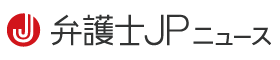北九州市のファストフード店、神戸市の地下鉄駅構内、長野駅前のロータリー。昨年末から今年1月にかけて全国で「無差別」と考えられる殺傷事件が相次いだ。
一部のワイドショーやSNS上では、これらの事件で逮捕された容疑者らがいずれも40代だったことから、非正規雇用で働く人が多い「就職氷河期世代」が、無差別殺傷など凶悪事件を起こしやすい状況に追い込まれているのではないかとの推測もなされた。
しかし、犯罪社会学・社会統計学を専門とする龍谷大学の津島昌寛教授は、「就職氷河期世代が無差別殺傷事件を起こしやすいとは断言できません」と慎重な姿勢をとる。
就職氷河期世代と前後世代で”差”はあるのか?
その理由として、まず”調査対象者”の少なさを挙げる。
「日本ではそもそも無差別殺傷事件の数は多くなく、調査対象者となる犯人も少ない。共通する属性や傾向を調べるには、数として足りない印象です。
日本における無差別殺傷事犯についての一番詳しい調査報告は法務省の『無差別殺傷事犯に関する研究(2013年)』ですが、これでも調査の対象となったのは52人。うち女性は1人しかいません」
また、他の調査からも「就職氷河期世代が、他の世代と比較して、無差別殺傷事件等を引き起こす傾向が高いことを示すデータはない」と津島教授は続ける。
たとえば、東京・秋葉原で通り魔事件を起こした加藤智大元死刑囚が事件前、友人に「生きていても仕方がない。死んでしまいたい」というメールを送っていたように、無差別殺傷事件は「拡大自殺」とも言われ、犯人が自殺企図を抱えていることが多い。
そこで津島教授は、世代(出生コホート)別の自殺死亡率(人口10万人あたりの自殺者数)を図に示し、以下のように指摘する。

オレンジ色のラインが「就職氷河期世代」が各年齢の時の自殺死亡率を表す(図作成:津島昌寛教授)
「自殺がすなわち無差別殺傷事件の代替と言えるかについては議論があると思いますが、少なくとも自殺傾向については、ほかの世代と比べて氷河期世代が高いわけではありません」
さらに津島教授は、「無差別殺傷事件とは原因が異なることも多いですが」と前置きした上で、一般的な殺人事件での殺人加害率(人口10万人あたりの殺人検挙人員数)も世代別に明らかにする(以下図)。

就職氷河期世代の一般殺人事件での殺人加害率は20代をピークに低下している(図作成:津島昌寛教授)
「氷河期世代が就職難や非正規雇用など、厳しい状況に置かれてきたことは事実です。個々のケースを見れば、そういった不景気のあおりを食ったことが無差別殺傷事件の発端になっていることもあります。
しかし、こうしたデータを見る限りでは『氷河期世代』としてまとめて語れるほど顕著な傾向は見当たりません。
つまり単純に『経済的に困窮すれば、どの世代の人であっても事件を起こす可能性がある』のではないでしょうか」
無差別殺傷事件の抑止に必要な”連携”とは
ちなみに前出の『無差別殺傷事犯に関する研究』(法務省、2013年)では、犯人の年齢層は20~30代が52人中30人と半数を超える。
また、〈交友関係のある友人がいない者、無職の者、収入のない者、中学校卒業・高校中退の者が多く、就労状況、生計状況は良くなく、犯行時の人との付き合いも少なく、学歴も低いと言った特徴〉があるとして、無差別殺傷事犯者は〈社会的弱者〉の一面があると分析されている。
さらに、精神鑑定が行われた37人のうち31人は〈パーソナリティ障害等の精神障害等があると診断〉を受けているという。
津島教授は「社会的弱者への支援や自殺予防などが、間接的には無差別殺傷事件の抑止になる」として、官民の連携の重要性を説明する。
イギリスでは多機関公衆保護協定(MAPPA)という枠組みが作られ、警察・法務省・保護観察所にとどまらず、雇用・教育・社会保障・保健医療・住居などに関連する行政部署や団体が連携し、社会に危害をおよぼす可能性の高い人について早期に情報を共有する取り組みを実施。運用が開始された2000年の前後で、再犯率(再度の有罪率)が6.5ポイント低下したという。
「基本的に日本は”縦割り行政”。情報が適切に共有されず犯罪リスクを抱えた人を見逃している可能性があります。
MAPPAのように、法務省や厚労省、警察や医療機関、不動産事業者等とも連携し、犯罪リスクのある人を早期発見・情報共有できる枠組みがほしいところです。
こうした連携は無差別殺傷事件の抑止だけではなく、社会問題一般に対してポジティブな効果が期待できるのではないでしょうか」(津島教授)