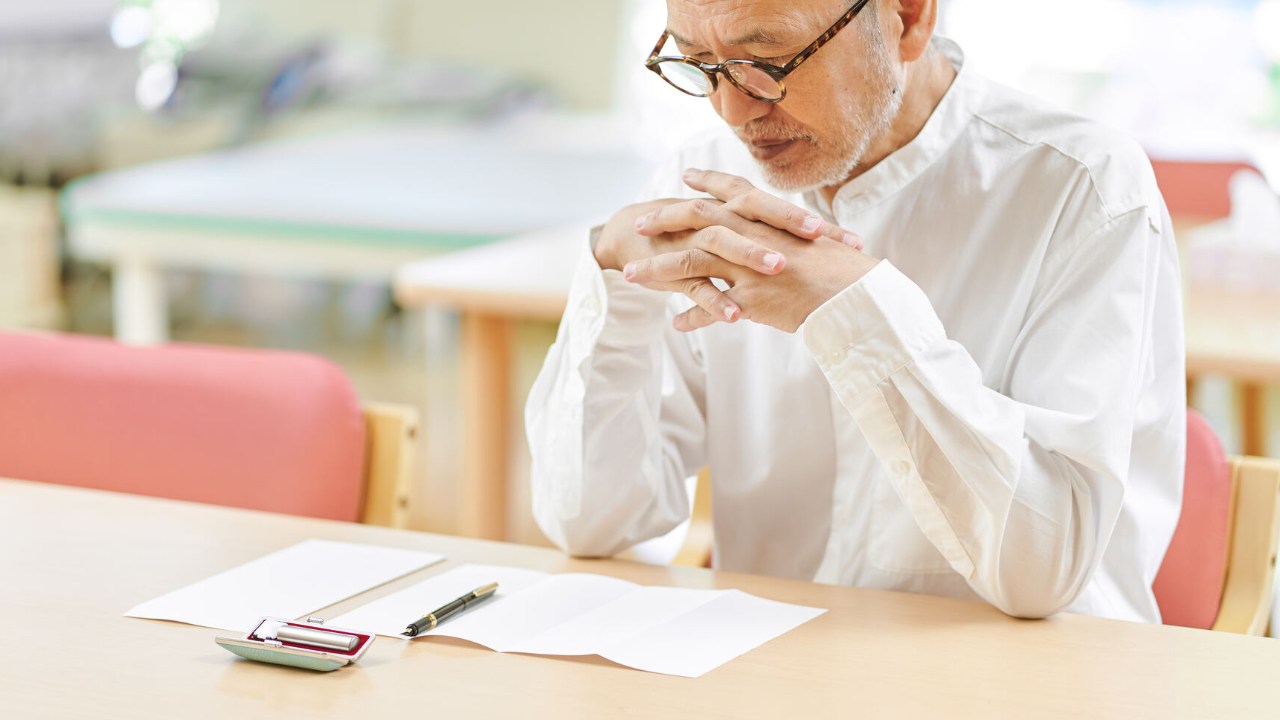社会的緊張に対する深い危機意識
他方、1970年代の財界は、社会的緊張に対する深い危機意識を抱いた。
たとえば、経済同友会は1972年に、「70年代の社会緊張の問題点とその対策試案」をとりまとめて発表した。
「”GNP至上主義”からの脱却が求められ、国民福祉の向上が叫ばれ、コミュニティの論理が模索されている今日は、機械的物質文明のなかにおける人間復権の時代の門口にある」がゆえに、「社会的変化の内容を人間的側面を中心に考察し、将来の望ましい社会への対応策を長期展望から検討すべき時」だとする。
この文書で注目されるのは、日本でもアメリカと同様にコンシューマリズムが高揚しているとして、消費者運動の展開に重大な関心が払われた点である。
具体的には、1960年代後半から「欠陥商品、二重価格などに対する不満、大気汚染、水質汚濁などが人間の生命や健康を損っているという危機感」から「市民運動」が発生しそこに「国民一般の価値観・意識の変化や、大企業に対する反発、いわばビッグなるが故に悪とする感情的反発がからみあっている」という。
経済同友会は、消費者運動の展開を公害反対運動などと同様に、人びとの企業観に関わる深いレベルの社会的緊張として受けとめていたのである。
あるいは、同じく経済同友会が翌73年に発表した「社会と企業の相互信頼の確立を求めて」でも、「企業外にあっては、公害・環境破壊の深刻化、コンシューマリズムの昂揚、新しい型のインフレの進行、企業内にあっては、従業員の意識変化に伴う職場への帰属意識の希薄化などの問題が生じている」として、このまま企業が「目先の効率追求に走る」ならば、「企業の拠って立つ自由企業体制を自ら危殆におとし入れることになりかねない」と強い危機感を露わにしている。
さらに、日本経済調査協議会が1975年にまとめた「住民運動と消費者運動」という報告書も、同様の危機意識に貫かれていた。
日本経済調査協議会は、1962年に経済団体連合会(経団連)、日本商工会議所、経済同友会、日本貿易会の財界四団体の協賛を得て設立された調査研究機関で、この報告書も財界の認識を示すものと見てよい。
報告書はまず、「環境問題にその典型的な例をみる住民運動や、消費者主権の復権を目指す消費者運動」のような「大衆運動」は、他の先進国と同様に「経済社会運営に対してかなりの影響を与えるに至っている」と記す。
そのうえで、「住民運動や消費者運動の一部には自己の利益を確保しようとする余り、社会全体の調和的利益と秩序を損ね、今後の日本の経済の発展力や経済社会運営に支障となるのではないかとの懸念を懐かせるケース」もあるから、政府や企業は運動を選別しつつ、関係者の「参加」や「対話」を通じた「事前的対応」と、「社会全体の調和的利益」への包摂に努めるべきだという。
社会運動史研究のなかで、この「住民運動と消費者運動」という報告書は、財界による「まき返し」を宣言したものとして知られ、1970年代後半から運動が「冬の時代」へ向かったこととの関係が注目されている(道場親信『「戦後日本の社会運動」と生活クラブ』市民セクター政策機構、2016年)。
満薗勇
北海道大学大学院経済学研究院准教授