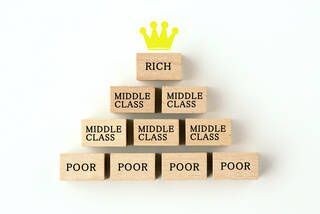新卒の給与がアップすれば、もちろん社員の給与もアップする
最近、大企業では新卒の初任給を大きく引き上げるニュースを見かけます。日本は横並び意識が強かったせいもあって、初任給については会社が違っても大差がないという傾向がありました。
実際のところ、初任給は似た水準であっても、中小企業では数年位給料がアップしない一方で、大企業は入社数年で給与が大幅にアップしたりして、給与の差が生じることが多かったのです。
近年の人材難、またグローバルな人材獲得競争の中で、優秀な人材を確保したいと考えた時、こうした横並び意識はマイナスに働くことが増えています。そこで大企業では初任給から大幅な差をつけるようになったというわけです。
新人の給与がアップした、とニュースになる時、あたかも新人とアラサー社員との間で給与の逆転が起きるような印象を受けますが、これは間違いです。
新人と先輩の給与逆転を起こせば、社員のエンゲージメント(愛社精神)はゼロになってしまいますから、どのような会社でも先輩社員はそれ以上の給与となります(自分の新卒の時はもっと低かったのに…という不満感は残りますが)。
院卒であるとか、極めて優秀な人材であるとか(日本語、英語、中国語ペラペラのマルチリンガル新人とか)、特別な理由がない限り、最初から給与が逆転する現象はまず起きませんので、そこは安心してください。
(広告の後にも続きます)
給与のアップは人材難を表していますが、物価上昇の影響も大きい

こうした給与アップのニュース、基本的には人材不足を表しています。優秀な人材にははっきりとした待遇差を示さないと内定に応じてもらえないという危機感が大企業ほどあるからです。
一方で、ニュースにあるような極端な数字でなくても、多くの会社員の給料はアップし始めています。「去年は月数千円位だけど給与がアップした!」というような人はたくさんいるのではないでしょうか。
おそらく今年もお給料がアップする人が多いのではないかと思います。労働組合がある場合は、新年度の賃上げ交渉の結果を公開しますので、確認をしてみてください。労働組合がない場合は、会社が賃上げの発表をすることになります。多くの場合、前年度より少し増えることでしょう。
その背景にあるのは物価の上昇です。モノの値段が上がってきた時、その度合いは物価上昇率で表すことができます。このとき、お給料も物価上昇率位金額を増やしておかないと、今までと同じ生活ができないことになります。
とはいえ、毎月毎月、物価上昇に見合う改定をするわけにはいきませんから、多くの会社では年に一回給与額の見直しを行います。多くの会社は4月が年度始まりなので、改定時期も4月が多いというわけです。
これは昇格に伴う昇給とは別で行うものです。労組の交渉の言葉ではベースアップなどと言われます。
ちょっと前まで「何年も給料は上がらなかった」という会社が多かったのに、ライフプラン3.0世代あるいはZ世代の給料が毎年上がっているのは大きな社会の変化です。