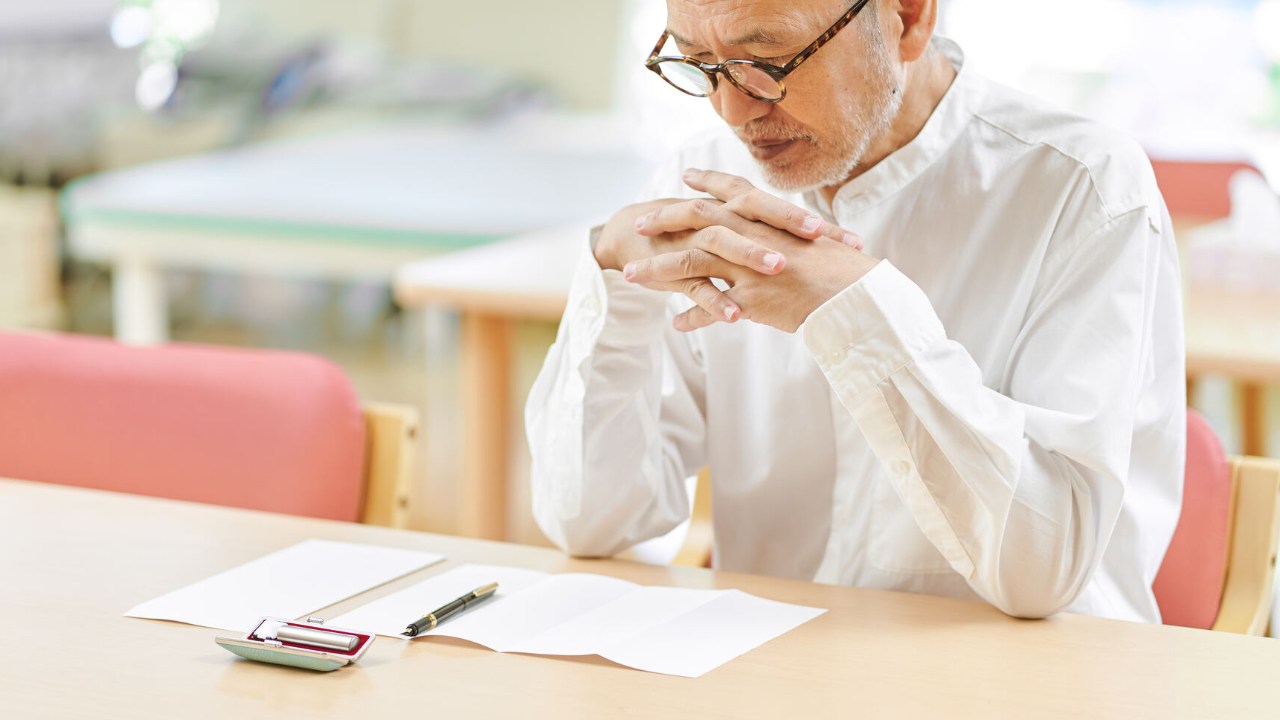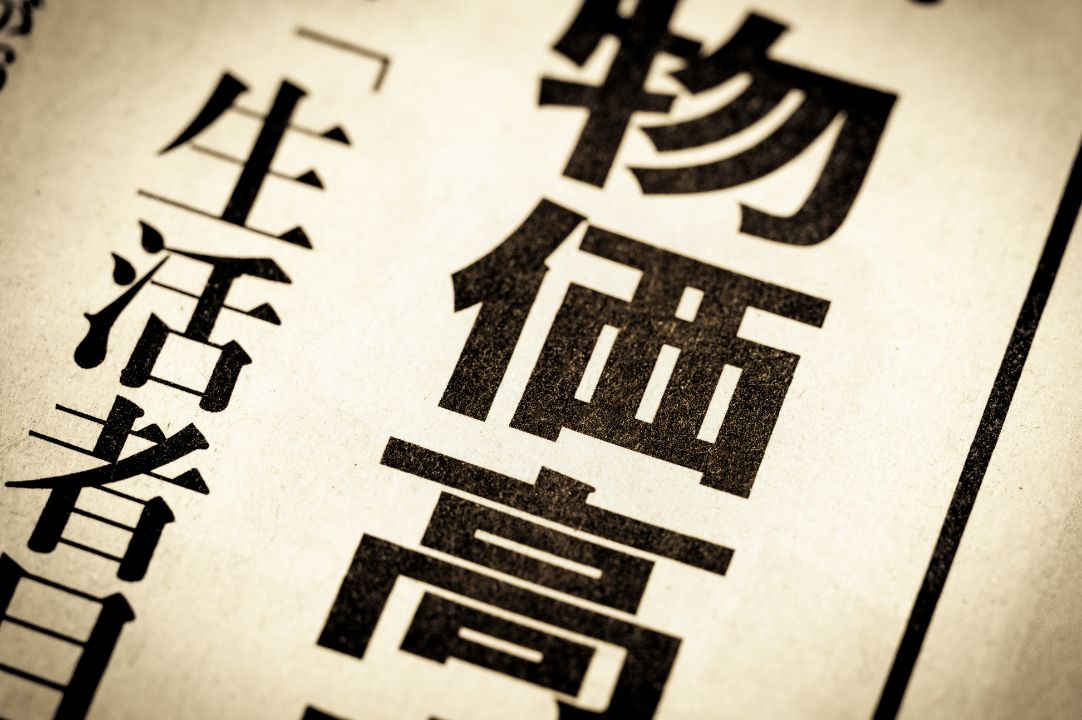
2012年のワールドシリーズ・オブ・ポーカー(WSOP)で日本人初優勝を果たし、投資家としても大活躍している木原氏と、新進気鋭のエコノミストであり、日本ポーカーの祭典JOPTで2度の優勝経験を持つエミン・ユルマズ氏。本記事では、エミン・ユルマズ氏/木原 直哉氏による書籍『「確率思考」で市場を制する最強の投資術』(KADOKAWA)を一部抜粋・再編集して、インフレ下における投資の必要性についてご紹介します。
インフレ下での合理的な経済行動とは
エミン:インフレにどう対抗すればいいのか、ということをよく聞かれるのですが、基本的にインフレ下ではあらゆるリスク資産が上昇します。インフレはモノの価格が上がる分お金の価値が目減りすることですが、それはとりもなおさず、お金以外の資産の価値が上昇することにつながります。
たとえば、3%のインフレ下では、株などのリスク資産は最低でも3%は上がるもので、実際はそれ以上に上昇することがほとんどです。
木原:なるほど。
エミン:これまでのように、インフレがゼロあるいはデフレの状態では、投資するインセンティブは働きません。お金をそのまま置いておいても価値は目減りしないし、デフレであればむしろ上がるので、かつてのデフレ経済下では銀行預金は正解だったわけです。
ところが、インフレ下ではお金の価値が下がるので、普段は投資しない人まで投資をするようになります。要は、お金を投資する強いインセンティブが生まれることから、株価はインフレ率以上に上昇するのです。
この現象が最もわかりやすく現れた例のひとつが、私の母国であるトルコです。2020年以降、トルコはハイパーインフレに見舞われてトルコの通貨であるトルコリラは暴落し、価値がほぼ5分の1になってしまいました。インフレ率と同じだけ株価が上がると考えれば、株価が5倍になってもおかしくありませんが、実際には10倍になっています。
なぜインフレ以上に株価が上がったかというと、トルコリラの価値がどんどん目減りしていくことで国民がパニックになり、株式投資を加速させたからです。
さすがに日本ではトルコほどの急激なインフレになることはないでしょうが、インフレ経済下では消費をするか、投資をするのが合理的な経済行動になります。
実際、これまで投資をしなかった層が危機感を持って株式投資を始めるという現象は、すでに起こっていますよね。そこに新NISAという追い風もプラスされ、これらが強力なエネルギーとなって株式市場を押し上げていくことは容易に想像できます。
木原:デフレ経済下では合理的だった預貯金も、いよいよこれからはハイリスクな行動になっていくわけですね。なにしろ預貯金だけだと、暴落中の日本円という銘柄に集中投資していることになるんですから、それはもうとんでもないリスクになりそうです。
エミン:ポーカーでは配られたハンドが弱くて降りるときでも、アンティ(最低限ベットしなければならない強制参加費)は取られるので、勝負を降りたときでも少しずつ手元のチップは減っていきます。
私に言わせれば資産を全部銀行預金にしている人たちは、まさに少しずつアンティを取られ続けているようなものです。当の本人は何も払っていないつもりでも、インフレという手数料を取られて資産の価値が少しずつ目減りしているんです。
要するに我々は望むか望まないかにかかわらず、プレーヤーにならざるを得ません。どのタイミングで、どれぐらいの頻度でプレーするかは選べるけれど、プレーするかしないかということは、もう選択の余地がなくなっているんですよ。
(広告の後にも続きます)
「ゆるやかなインフレ」が日本経済にもたらすメリットとは
木原:ゲームプレーヤー的な意見を言わせてもらうと、どこかで誰かが損をすれば、その分どこかで必ず得する人が現れます。
たとえば、3%のインフレ下では現金の価値が下がるので、現金を持っている人は損をします。その分、どこかで必ずだれかが得をしている。それは誰かというと、おそらく株を持っている人でしょうね。あるいは金でもビットコインでも不動産でもいい。現金以外の資産を持って、その値上がりの恩恵を享受している人なんです。
エミン:その通り。日経平均株価がバブル後の高値を更新したタイミングと、多くの人がインフレを実感したタイミングが重なったのは、そういうことなんだよね。
木原:物価の上昇で生活が苦しくなることから、インフレを歓迎しない人も多くいるようですが、長い間デフレが続けば現金で保有しておく方が安全だと考える人が増え、お金が循環しなくなります。だから、失われた30年と言われたわけです。本来はゆるやかなインフレを起こして、お金を循環させていくのが健全です。
よく言われる世代間の資産格差についても、インフレによって実質的な資産課税をすれば解決するのではないでしょうか。預金を貯め込んでいる高齢者がインフレによる資産の目減りを回避しようとリスク資産にお金を回せば、高齢者の資産が活用されることになり好ましいことです。しかも、利益が出ればその20%は税収になります。
実際に目に見える形で資産課税をすることは難しいでしょうが、インフレで金融資産が増えたときにその20%が税金として回収されるのであれば、それは資産課税そのものな上に、支払う人からすると利益から支払うことになるので資産課税と感じにくいです。
インフレで政府の借金の実質的な負担が軽くなることはよく言われていますが、それだけでなくゆるやかなインフレを安定的に起こすことで、結構いろんな問題が解決できる気がします。
エミン:株を持っているかいないかにかかわらず、インフレ下では人は欲しいものがあれば価格が上がる前に買おうとします。買い控えというものがなくなって消費が活発になるんです。もちろん、インフレ率が一定以上になると消費には逆効果になりますが、基本的にはゆるやかなインフレは経済にプラスに働いて、それが株価を押し上げる要因になります。
また、企業が値上げすれば、増収増益につながります。単純にPSRベースで考えても、売上高が増えれば株価も上昇します。
木原:僕は投資先を吟味(ぎんみ)するときも、価格転嫁をしているかどうかは強く意識します。このインフレ下で値上げをできない会社には、とても投資する気になれないですから。
エミン・ユルマズ
エコノミスト、為替ストラテジスト
木原 直哉
プロポーカープレーヤー
※本記事は『「確率思考」で市場を制する最強の投資術』(KADOKAWA)の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。記載内容は当時のものであり、また、投資の結果等に編集部は一切の責任を負いません。