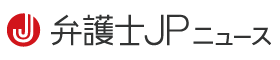3月27日、保険診療医が加盟する任意団体「全国保険医団体連合会」(保団連)が、マイナ保険証利用に関する調査について中間集計を発表。医療現場ではトラブルが多々起こっており、医療機関と患者の双方に不利益が発生している実態が明らかになった。
健康保険証を持たなくなる人が急増する見込み
12月2日、従来の健康保険証の新規発行が停止された。
既に保険証を持っている人は経過措置として最長1年間使用することができる。
だが、年度明けの4月は就職や転職・離職のシーズン。また7月末には後期高齢者医療制度の有効期限が切れることにより、多くの人の手元から健康保険証がなくなる。
保団連は2月中旬から医療機関を対象に「2024年12月2日以降のマイナ保険証利用に係る実態調査」を開始。今回発表された中間集計は、3月14日までに到着した回答8330件を取りまとめたもの。
調査によると、約7割の医療機関で、直近のマイナ保険証利用率は30%未満だった。昨年に比べると利用率は10%以上の上昇となったが、それでも依然として低迷が続く状況だという。
カードリーダーや書類が原因で医療機関に負担が…
健康保険証が廃止された12月2日以降の窓口業務について、調査では6割以上の医療機関が「負担を感じる」と回答。
高齢者を中心に、カードリーダーの使用が困難な患者や使用方法を説明されても理解できない患者は多い。医療機関のスタッフがサポートしなければならず、窓口や事務の業務に支障が生じる事態が全国で起こっている。
また、昨年9月から健康保険組合などを通じて各家庭に「資格情報のお知らせ」が送られており、さらに12月以降はマイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人などに「資格確認書」が送付されている。
この二つの書類は全く別物だが、名称が似ているために混同している人も多い。「資格情報のお知らせ」の書類が必要であるのに持参しない、逆に書類だけを持ってきてマイナ保険証を持参しない患者がいることも、トラブルの一因だ。
さらに、小さな子どもの顔認証がうまくできず、パスワードも間違えたことからロックされて、市役所へ手続きに行く必要が生じたケースもあるという。
保団連の井上美佐副会長は「政府はマイナ保険証で負担が減ると宣伝していたが、実際には逆の事態が起こっている」と指摘した。
約12%の医療機関では「患者が全額負担」
マイナ保険証でトラブルが発生した場合の対応としては、78%の医療機関が「患者が持ち合わせていた健康保険証で確認」と回答した。
一方で、資格情報などの確認が取れるまで、約12%の医療機関は「一旦は患者に医療費を10割負担(全額負担)させる」との対応を取ったケースがあるという。
医療保険の原則として、資格確認ができない患者は10割負担することがルールとなっている。逆に、資格情報に疑義がある患者に保険診療を行うことは本来の原則に反しており、後日になって医療機関がトラブルに巻き込まれるおそれもある。
井上副会長は「頼りになるのは健康保険証」と表現し、医療機関と患者の双方にとって従来の健康保険証が有益であることを強調した。

オンラインで会見に参加した井上副会長(3月27日都内/弁護士JPニュース編集部)
「初診の登録が簡単になった」などのメリットもあるが…
マイナ保険証の利用にメリットを感じると回答した医療機関は3割以下。具体的には、初診の患者の登録が簡単になった点や、資格情報の確認がオンラインで可能になったため入力が楽になったという点がメリットとして挙げられていた。
一方、保団連の山崎俊彦理事は「オンラインの資格確認は従来の保険証でも可能」と指摘する。
また、そもそも多くの医療機関では、患者は初診ではなく再診であることの方が多い。さらに、メリットを感じると回答した医療機関も「一度トラブルになるとものすごく大変で時間を取られる」と付け加えている。
山崎理事は「初診で、かつトラブルが発生しなかった場合にしか、メリットが感じられない」と表現し、実際にはデメリットの方が多大であると強調した。
2025年は「恐ろしい数のトラブルが予測される」
マイナンバーカードの更新期限は10年だが、ICチップに搭載されている「電子証明書」の期限は5年。
そして、政府がマイナポイント事業を開始した2020年にマイナンバーカードを作成して、ICチップの更新期限が迫っている人は多数いる。
冒頭で述べたように、今年は保険証が手元からなくなる人も多い。さらに電子証明書が失効してマイナ保険証が利用不可になる人も多数発生することから「恐ろしい数のトラブルが予測される」と、山崎理事は危惧を示した。
また、保団連は以前から自民党の河野太郎前デジタル相による「早くマイナ保険証に慣れてもらうことが大事」「早くマイナ保険証に対応すれば病院にとってデメリットはない」などの発言を批判してきた。
今回の中間集計は、2021年10月にマイナ保険証の本格運用が開始されてから数年が経過しても患者が慣れることはなく、医療機関にはデメリットが生じ続けている事実を示すものだと、山崎理事は強調する。
保団連の宇佐美宏副会長も「国は国民の思いを無視して健康保険証の廃止を強行してきた」と政府の対応を批判。「結局、健康保険証の方が良いということだ」と、調査結果を総括した。