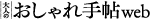介護保険のサービスを受けるためには?

介護が必要な人が無条件にサービスを受けられるわけではなく、「支援や介護が必要な状態」の認定を受ける手続きが必要です。
1か月程度かかるので、早めの動き出しが肝心です。
「要介護認定」までの流れ
サービスは65歳以上から家族または本人が申請
介護保険の申請を行うと、数日後に認定調査員の訪問を受けます。
74項目の聞き取り調査と主治医の意見書などをもとに、どのくらいの介護を必要とする状態かの審査・判定が行われます。
認定結果がでるまで申請から1か月程度かかります。
① 要介護認定の申請
② 要介護認定の訪問調査
③ 認定(介護サービス利用開始)
④ ケアプランの作成
認定調査で聞かれること(74項目の一例)
⚫︎ 両足で10秒立てますか
⚫︎ 座った状態から立ち上がれますか
⚫︎ 約1m先のものが見えますか
⚫︎ 普通の声が聞こえますか
⚫︎ 自分で歯磨きをしていますか
⚫︎ 自分でズボンの履き替えをしていますか
⚫︎ 1週間にどのくらい外出していますか
⚫︎ 自分の生年月日や年齢を言えますか
⚫︎ 今の季節がわかりますか
⚫︎ 自分でお金の管理をしていますか
⚫︎ 日常の買い物をしますか
….など
みんなが入っている介護保険
介護が必要になった人を、社会全体が支える仕組みが介護保険制度です。
40歳になると国民みんなが介護保険に加入し、健康保険と一緒に月々の保険料を納めています。
介護保険のサービスを受けられるのは、原則65歳以上(65歳未満で一部疾患の人は適用)。
65歳になると、被保険者証が郵送されてきます。
介護保険には、さまざまなサービスがあり、「要介護認定」で、支援や介護が必要だと認定されると、これらのサービスを利用することができます。
介護が必要な親の要介護認定を受ける
要介護認定を受けるには、本人が住む自治体の窓口に、本人または家族による介護の申請が必要です。
申請を受けて、市区町村の職員が自宅を訪問し、認定のための聞き取り調査を行います。かかりつけ医によって、健康状態についての「意見書」も作成されます。
調査の内容を受けて、原則30日以内に要介護度が決定されます。
要介護認定の方法は全国一律で、本人の健康状態だけではなく、家族や住まいの環境などもこまかく質問されます。
「親世代は遠慮やプライドもあり、できないことでも『できます』『問題ありません』と答えてしまうことがありますが、それでは正しく認定されません。
認定調査には、必ず家族も付き添いましょう」。
ケアマネジャーが「ケアプラン」を立てる
要介護認定を受けたら、どういったサービスをどれだけ利用するかを決める「ケアプラン」が作成されます。要支援の場合は、原則、地域包括支援センターでケアプランを作成してもらいます。要介護の場合は、ケアマネジャーと呼ばれる専門職に依頼します。
ケアマネジャーは、サービス事業者や施設との連絡調整、利用料の管理も行ってくれる、頼れる存在です。
ケアマネジャーを自分たちで探して契約する必要があるので、かかりつけの病院の関連事業所や近所の事業所に連絡を。面談して話しやすそうだと思ったら契約します。
ケアマネジャーは途中で変更もできます。
要介護度には、要支援1~要介護5までの7段階がある
要介護度は、日常生活の能力が基本的にはある要支援1から、介護なしには日常生活が営めず意思伝達も困難な要介護5まで、要支援1、2+要介護1~5の7段階があります。
認定調査の時に、何に困っているか、どんな介助をうけているか正確に伝えないと、軽い段階に認定されてサービスが十分に受けられないことに。
要介護度によって受けられるサービスの幅が異なる
認定された要介護度に応じて、サービスの利用に対する給付額の上限が定められています。
サービスを利用した場合、自己負担割合は、所得によって1割~3割と定められています。支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。
施設への入居などは急いで考えない
遠方に住む親が要介護になった場合、すぐに施設での介護を検討する人もいます。しかし、親の人生なので、本人の意思をしっかり確認することが大切です。
健康状態が変わるかもしれないので、在宅でリハビリしながら、施設への入居についてゆっくり話し合うのも一案です。
(広告の後にも続きます)
認定されれば手厚い!介護保険のサービス

在宅なら、ホームヘルパーの訪問を受けたり、デイサービスに通って入浴やリハビリをしたり。
介護用具のレンタルや購入ができるなどさまざまなサービスが。
訪問介護やデイサービスなど組み合わせて活用を
介護保険で受けられるサービスはさまざま。
在宅で介護を受ける人は、ホームヘルパーの訪問を受けて、食事、排泄、入浴などの介助が受けられるほか、理学療法士などによるリハビリ指導も受けられます。
デイサービスセンターという日帰りの施設もあり、入浴や食事、機能訓練などを受けることもできます。
こちらは、ワゴン車などで利用者宅を巡回して、自宅まで送迎してくれるサービスで、朝8時半ごろに迎えに来て、夕方16時過ぎに送ってくれるというスタイルが一般的です。
ショートステイという宿泊サービスを利用すれば、介護する人の負担を軽減できるかもしれません。
介護ベッドのレンタルや、転倒防止のために自宅の段差を撤去したり、手すりを付けるなどの改修をするための補助も出ます。

介護で仕事を休みたいときは?
「介護休業制度」を活用しよう
介護離職を防ぐために、家族の介護が必要になった人がとれる
のが、介護休業。パートや派遣社員を含めたほぼすべての労働者がとれるもので、対象家族一人につき、通算で93日まで(3回まで分割可能)の休業を取得できます。
家族の範囲は、親や配偶者はもちろん、配偶者の親・祖父母・兄弟姉妹も含み、2週間以上、常時介護が必要な状態というのが基準です。
「介護休業は、法律で決められた制度なので、就業規則になくても、労働者が申し出たら企業側は拒否できません」。
介護休業中は無給となるケースが多いですが、93日間は雇用保険から「介護休業給付金」として給料の67%が支給されます。
遠距離介護、交通費の出費が痛い!
航空会社の割引制度をチェック
遠距離の親を介護する場合は、そのたびの交通費が痛い出費に。
全日空、日本航空など一部の航空会社では、介護による帰省をする際の割引運賃を設定しています。
前もって予定が立っている場合は早期割引、急な帰省は、介護のための割引と使い分けるのもいいでしょう。
「割引サービスを利用しても、交通費は大きな負担になります。交通費も介護の経費と考えて、分担方法を親やほかの兄弟と相談することが大切です」。
*割引率などは各社HPなどで確認ください