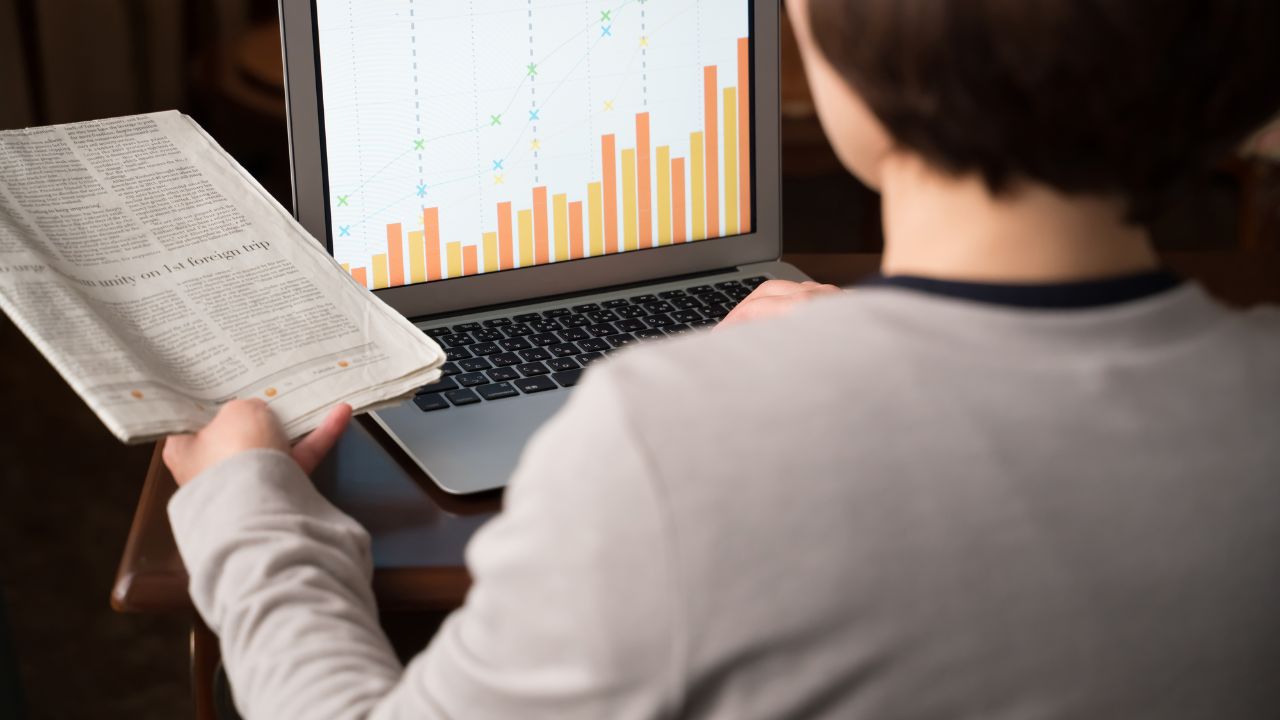世界のインターナショナルスクール市場は約7.9兆円に成長し、日本でも年間学費135万円~540万円の学校が注目されています。高額なイメージが強いインターナショナルスクールですが、一条校との連携や学費を抑えた新しい選択肢の登場で、富裕層以外にも手が届く存在になりつつあります。柴田巌氏の著書『未来をつくるインターナショナルスクール経営戦略』(プレジデント)を基に、その歴史と未来を紐解きます。
重要高まるインターナショナルスクール
世界のインターナショナルスクール市場は、グローバル化の進展や国際的な労働力の増加、そして質の高い教育への需要の高まりによって急速に成長しています。特にアジア、中東、アフリカなどの新興経済国では、経済成長とともに国際ビジネスの機会が増え、外国人駐在員だけでなく地元の富裕層も国際的な教育に高い関心を寄せています。
ISCリサーチ(ISC Research)は、インターナショナルスクール市場の動向を専門に調査する機関です。同社の2022年の報告によれば、世界には約1万3190校の英語を主な指導言語とするインターナショナルスクールが存在し、約550万人の生徒が在籍しています。このデータは、世界中のインターナショナルスクールの数や生徒数を詳細に調査した結果です。これらの学校は年間で約530億ドル(約7兆8705億円、2024年10月時点)の収益を生み出し、市場は新型コロナウイルス感染症収束後も拡大を続けています。
また、アドロイト・マーケット・リサーチ(Adroit Market Research)は、さまざまな業界の市場調査と分析を行うリサーチ会社です。同社の報告によれば、世界のK‐12(幼稚園から高校までの教育段階)のインターナショナルスクール市場は、2022年から2028年にかけて年平均成長率(CAGR)19%で成長し、市場規模が3619.8億ドル(約53兆7540億円)に達すると予測されています。
これは、世界中でインターナショナルスクールへの需要が高まっていることを示しています。この成長の背景には、英語教育への強いニーズや、より手頃な学費で提供されるインターナショナルスクールの増加、多国籍の生徒とともに学ぶ機会を提供する学校への需要の高まりがあります。
特にアジア太平洋地域では、経済成長にともなってインターナショナルスクールの設立が急速に進んでおり、現地の富裕層やエリート層を中心に、子どもに国際的な視野を持たせたいと考える家庭が増えています。
さらに、教育技術の進化も市場拡大に大きく寄与しています。多くの学校がオンライン学習プラットフォームやデジタル教材を導入し、2020年以降のコロナ禍を契機に、オンラインやハイブリッド形式の授業が一般化しました。これにより、地理的な制約を超えて幅広い生徒に教育を提供できるようになり、特に遠隔地に住む生徒や留学を希望する家庭にとって大きな利便性が生まれています。
しかし、市場の急成長には課題も存在します。特に高額な学費が多くの家庭にとって障壁となっており、インターナショナルスクールに通えるのは限られた層にとどまることが多いです。また、異文化間の統合や教育の質を保つための優秀な教員の確保など、学校運営における課題も依然として残っています。
総じて、世界のインターナショナルスクール市場は今後も成長が期待される分野であり、需要の増加と教育技術の進歩がその成長を支えています。しかし、より多くの生徒が質の高い国際教育を受けられるようにするためには、学費の負担軽減や教育の質の維持、多様性と包括性の促進が不可欠です。
(広告の後にも続きます)
日本のインターナショナルスクールの歴史、市場が発展し続けるワケ
1. キリスト教系から始まったインターナショナルスクール
日本におけるインターナショナルスクールの歴史は、1872年に横浜で設立されたサン・モール修道会学校(現・サンモール・インターナショナル・スクール)から始まりました。この学校は、布教活動の一環としてキリスト教の教えを広めるだけでなく、国際教育を提供することを目的としていました。当時、修道士たちは外国人子弟や多様な背景を持つ子どもたちに教育の機会を提供し、日本に住む異文化の子どもたちが母国の言語や文化とともに幅広い教育を受ける場をつくり上げたのです。
その後も、キリスト教系のインターナショナルスクールは日本国内で次々と設立されていきました。たとえば、1901年にはカトリック系のマリア会によって設立されたセント・ジョセフ・インターナショナル・カレッジが、そして1913年には神戸にカナディアン・メソジストアカデミーが開校しました。これらの学校は、当時の日本に住む外国人子弟に向けて、キリスト教的価値観に基づいた教育を提供するとともに、国際的な視野を持った人材を育てる場として発展していきました。
1950年代まで続々と新しい学校が誕生しました。これらの学校は、日本における初期の国際教育の礎を築き、国際的な視点を持つ教育を提供する先駆者的な存在でした。
2. グローバル化による英語教育ブームと裾野の広がり
1950年代に入ると、日本経済の復興とグローバル化の進展に伴い、民間主導によるインターナショナルスクールの設立が活発化しました。その代表例として挙げられるのが、松方アカデミーです。
同校は、設立者である松方種子氏が英語を教えるための小規模な塾としてスタートしましたが、中華系の転入生が増加することで規模を拡大し、1960年には生徒数が200名を超えました。その後、施設の増設とともに、現在の西町インターナショナルスクールへと発展していきました。
この時期、日本社会においても英語力の向上や国際的な視野の必要性が高まっていきました。海外旅行や留学が一般化するなかで、英語教育に対する関心は高まり、インターナショナルスクールへの需要が急増しました。特に、1990年代後半にはグローバル経済の発展とともに、国際教育を受けることが将来のキャリアにおいて重要視されるようになり、インターナショナルスクールの生徒数は大幅に増加しました。
また、この流れに伴って、プリスクール(幼児教育)やインターナショナルスクールへの入学準備をサポートする塾が人気を集めるようになりました。これにより、国際教育は早期からの準備が必要なものとして認識され始め、インターナショナルスクールに対する社会的な関心が一層高まっていったのです。
3.政府の補助金がなく、公的に学歴が認められない場合が多かったが…
インターナショナルスクールの需要が増加するなかで、教育の供給面でも大きな変化が生じています。最近では、従来のインターナショナルスクールが学校教育法上の「一条校」として認可を受け、正式な日本の教育機関としても認められるケースが増えています。また、一条校として設立された日本の学校が、国際教育を提供するカリキュラムを取り入れる動きも活発化しており、これによって日本の教育システムに多様性がもたらされています。
「一条校」とは、日本の学校教育法第1条に基づいて設立された公的な教育機関であり、国からの補助金を受けることができるほか、卒業生は日本の大学受験資格を自動的に得ることができます。
一方、インターナショナルスクールの多くは「各種学校」や「無認可校」に分類されるため、政府の補助金はなく、学歴も公的に認められない場合が多いです。そのため、学費が高くなる傾向があり、経済的な負担が大きいという課題があります。
こうした背景のなかで、インターナショナルスクールと一条校が連携してキャンパスを共有したり、双方のカリキュラムを統合する新しい教育モデルが誕生したりしています。このモデルは、日本の教育システムの多様化を進め、国際教育の重要性を高めています。具体的な連携例として、以下の学校間の協力が挙げられます。
・文京学院大学女子中学校
・高等学校×アオバジャパン・インターナショナルスクール
・ 昭和女子大学附属昭和中学校
・高等学校×ブリティッシュ・スクール・イン・トウキョウ昭和
・ 関西学院大阪インターナショナルスクール(※関西学院が学校法人千里国際学園を買収し、名称変更)
・芝国際中学高等学校×ローラス インターナショナルスクール オブ サイエンス
インターナショナルスクールと一条校が提携し、教育リソースや施設を共有することは、日本の教育に新たな可能性をもたらします。この新しい教育システムは、生徒に多様な学びの機会を提供し、日本国内における国際教育の選択肢を拡充します。また、文化的背景が異なる生徒同士がともに学び、グローバルな視点を育む場を提供することで、国際社会で活躍できる人材の育成にも貢献します。
日本の教育システムの柔軟性が向上することで、今後さらに多くの学生が多様な学びに触れる機会が増えていくことが期待されます。
4. 地域によって需要が異なるインターナショナルスクール
日本国内のインターナショナルスクール市場も、国際教育を求める家庭の増加に伴い、成長を続けています。特に東京を中心に、国際的な教育を提供する学校が数多く存在し、それぞれが独自の教育カリキュラムと学費体系を持っています。年間の学費は学校によって異なり、135万円から540万円まで幅広い選択肢が提供されています。
主要なカリキュラムとしては、イギリス式のケンブリッジ国際カリキュラム、スイス発祥の国際バカロレア(IB)、アメリカ式のカリキュラムなどがあり、生徒に多様な学びの機会を提供しています。
日本のインターナショナルスクール市場は地域によって需要が異なります。
東京は、インターナショナルスクールが集中しており、特に西洋式の教育が提供される学校が多くあります。たとえば、サンモール・インターナショナル・スクールやアメリカンスクールインジャパン、横浜インターナショナルスクールでは、国際バカロレア(IB)を含む多様な教育プログラムを通じて、多国籍の生徒に対して国際的な視野を育む教育が行われています。
関西地区では、カナディアン・メソジスト・アカデミーや聖ミカエル国際学校、マリスト国際学校といったインターナショナルスクールが質の高い教育を提供しています。
また、近年ではイギリスの名門校が日本国内にキャンパスを開設したハロウインターナショナルスクール安比ジャパンやラグビースクールジャパン、マルバーン・カレッジ東京などが、国内外の家庭に対して国際的な教育を提供する機会を拡大しています。
日本のインターナショナルスクール市場の成長は、外国人駐在員だけでなく、国際的な教育を希望する日本人家庭にも支持されています。また、日本の地政学的な安定性や生活水準の高さが、外国人駐在員にとって魅力的な要因となり、日本国内でのインターナショナルスクール市場の成長を後押ししています。こうした要因により、日本のインターナショナルスクール市場は今後も拡大が予想されます。
多様なカリキュラムの提供とともに、日本人および外国人の両方に対して質の高い国際教育を提供する学校が増え、国内の国際教育の機会はさらに広がっていくでしょう。
柴田 巌
株式会社Aoba-BBT
代表取締役社長