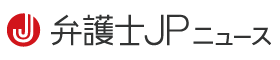遊技人口の減少や新型コロナ、新紙幣導入などの影響でパチンコ業界ではホールの倒産が相次いでいる。
警察庁の統計によると、2023年時点でのパチンコ店の店舗数は7083軒と、20年前の1万6076軒に比べて約56%の減少となった。
しかし、かつては庶民の娯楽として多くの人の心をつかみ、巨大産業にまで発展した。本連載では、そんな戦後・昭和のパチンコの歴史を紹介する。
第2回の舞台は昭和28(1953)年。現代では考えられないことだが、当時のパチンコ店では、店内で出玉の換金が行われていたところもあったという。(全4回)
(#3に続く)
※この記事は溝上憲文氏の書籍『パチンコの歴史』(論創社)より一部抜粋・構成。
機関銃式パチンコがブームに
昭和28(1953)年9月28日、愛媛県新居浜市S町は朝からぐずついた空模様がつづき、雨が降ったりやんだりしていた。
「なんでこんなことまでしなくちゃいけないのかしら。給料は安いし、やってられないわ」
パチンコ店「ライナー」(仮名)の従業員河野春江(仮名)は朝からイライラしていた。店はこの年の7月7日に開店。春江は求人募集を見て17歳で入店した。
パチンコがどんなものかよく知らずに入ったが、朝から夜遅くまで店内を走り回り、寝るのは深夜という毎日だった。店は開店早々から繁盛していた。
昭和27年暮れからブームがはじまった「機関銃式」全盛時代だった。左手で一個ずつ玉を入れて弾いたそれまでの「単発式」と違い、最初に大量の玉を自動玉入器に入れておけば右手一本で打てる。そのうえ、出玉は自動的に発射台の位置に集まるという画期的な機械だった。店は連日満員で、台当たりの売り上げが5000円(編注:当時のパチンコ機の価格は1台数千円程度。昭和27年の大卒国家公務員の初任給は7650円であった)の日も珍しくなかった。
「ちょっとおねえさん、早くしてくんない。いつまで待たせるのよ」
店の西側の出入口で40年配の主婦らしき女性が叫んでいる。店の正面の玉貸場で客に対応していた春江は急いで出入口の帳場に走った。主婦は「ハイ」と言ってタバコの「光」14個を春江に差しだした。
客に渡した景品を店舗で直接買い取り
「えーと、光1個が25円だから、350円ですね」
春江は「光」を受け取り、100円札3枚と10円玉5個を主婦に渡そうとした。と、そのとき出口から、「おい、おまえたち何をやっているんだ」と大きな声をだして男が寄ってきた。
とっさに主婦は駆け足で逃げ去った。男は警察官だった。主婦が持っていたのはパチンコ景品のタバコで、それを換金しているところを警察官に目撃されたのである。
そのとき店主が走り寄ってきて、いきなり春江に「そんなことをするなって言ってるじゃないか」と怒鳴った。𠮟られてしょげかえっている春江を尻目に、店主は警察官に頭を下げた。
「いや、やるなとは言っているんですがね。まだ未成年ですし、お客に無理を言われると無下にはできないもんで。私から注意しておきますので勘弁してください」
店主は一方的に客と春江のせいにしてその場を取りつくろい、警察官は厳重に注意して帰っていった。
すでにこの当時、客に渡した景品をパチンコ店が直接買うというように、店内で換金が行われていた。いつごろからはじまったのかわからないが、おそらく「連発式」が登場して以降である。
河野春江の店も例外ではなかった。実は、春江の店は警察官に注意されて以後も数回にわたって換金の現場を目撃され、そのたびに口頭、もしくは文書で注意を受けている。しかし、店主は従業員のせいにして改めようとしなかった。
その間、河野春江をはじめ従業員は所轄の新居浜警察署に呼ばれて何回かにわたって事情聴取を受けた。その場で春江は換金行為が店内で公然と実施されていること、タバコを定価より5円安く交換してよいと店主から言われていることなど、いっさいを白状したのである。
換金問題巡り裁判に…
そしてついに新居浜警察署は昭和28年11月13日、風俗営業取締法第4条に基づいて11月14日から12月2日までパチンコ店「ライナー」を営業停止処分にしたのである。
ところが、通常ならパチンコ店は警察の処分に「不徳の致すところでした」と素直に従うのだが、ここの店主は違った。
なんと、換金行為は愛媛県風俗営業取締法施行条例第23条第1号(当時)の「賭博その他著しく射幸心をそそるような行為」には当らないので営業停止処分は不当であり、撤回せよと松山地方裁判所に訴えたのである。
おそらく換金問題を巡って裁判で争ったのはこの事件が最初ではなかろうか。換金行為イコール法律違反ということがなかば常識となっている現在と違い、射幸心とは何かがわからなかった時代だ。その意味を裁判で明らかにするというのだから興味深い。
しかし、残念なことに裁判所は換金行為が法律違反に当たるかどうかの判断を避けた。判決が出た翌年1月14日、裁判所は「すでに営業停止期間はすぎているのだから停止を不当とする訴え自体が無効」との判断を下した。
だが、裁判で被告の警察側は換金が著しく射幸心をそそる行為である理由を述べている。簡単に要約すればこうである。
パチンコはもともと偶然によって当たる確率の高い遊びであり、客がパチンコ店にくるのは大なり小なり客の側に射幸心があるからだ。だから法律では著しく射幸心をそそることのないように営業許可規制を設けたり、現金、有価証券を景品に出すことを制限している。
したがって、景品を現金に換える行為が射幸心をそそる行為であることに疑いの余地がない―。
警察当局のこうした主張と営業停止という厳しい処分は、大方のパチンコ店をおおっぴらな店内換金の自主規制の方向に導いていく結果となった。