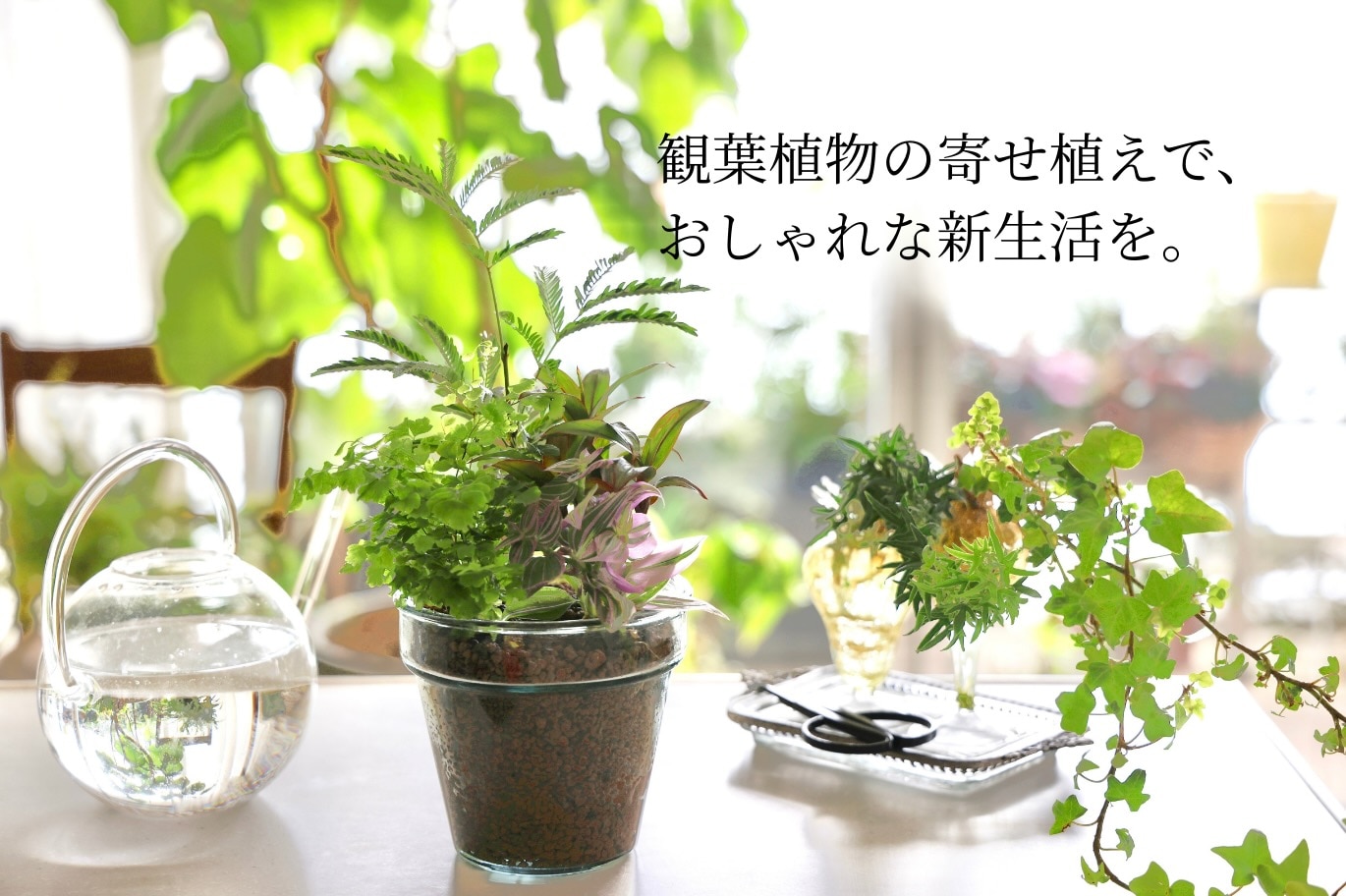植物を育てているときの心配ごとといえば、植物を枯らしてしまうこと。初心者は植物を枯らしたとき、しばしば「私は植物を育てるのに向いてない」と思いがちですが、それは早計、極論というもの。植物が枯れるのには、ちゃんとした理由があります。理由を知れば、回避も可能。今回は、植物が枯れてしまう主な5つの原因と、その対処法を解説。異常気象が頻発する中、世界の農業市場で大注目の新技術を取り入れた最新資材もご紹介します。
あなたの庭は大丈夫? 植物が枯れる主な原因5つ!

FotoDuets/Shutterstock.com
植物を育てたことがある人なら、毎日の水やりなど日々お手入れをしていても植物を枯らしてしまった経験があることでしょう。では、なぜ植物は枯れてしまうのでしょうか? ガーデニングのお悩みを解決する多くの園芸資材の開発・販売を行っている住友化学園芸の牛迫正秀さんによると、家庭のガーデニングで植物が枯れたり、生育不良に陥る主な原因としては、次の5つが挙げられます。
乾燥
根腐れ
光量不足
病害虫
肥料の過不足
これら5つの原因と、それぞれの初期症状について見ていきましょう。
乾燥

Natalia Kokhanova/Shutterstock.com
5つの原因のなかで、最も短期間で植物を枯らす原因となるのが乾燥です。他の要因ではほんの数日で植物が枯れてしまうことはほとんどありませんが、夏場の鉢植えなどは1日水やりを忘れただけでもぐったりし、乾燥した状態が数日続くと、水をやっても復活せずに枯れてしまうことも多いです。一方、地植えの場合は極端な乾燥は起こりにくいですが、暑さや乾燥が続く際は地植えでも水やりが必要となるケースもあります。
鉢植えの水やりの基本は、表土が乾いたら鉢底から流れ出るまでたっぷり水をあげます。ただし、植物(特に観葉植物や多肉植物)は種類ごとに好みの水分加減が異なるため、種類ごとの特性を調べて把握しておくとよいでしょう。
水不足のサインは、土壌が乾燥し、植物の水分が不足すると、葉がしおれて枝先がダランと垂れるのが典型的。また、葉の黄変もよく見られます。初期なら水をあげることで、復活が可能です。また、土が湿っているのにもかかわらず、水切れのような症状が出ることもあります。その場合は、次の項で解説する根腐れが原因かもしれません。
根腐れ

Stanislav71/Shutterstock.com
根腐れとは、水のやりすぎや土壌中にいる病原菌により、根が傷んで腐ってしまうこと。根の先端から腐りはじめ、症状が進むと株全体が腐ってしまいます。水やりの仕方が原因となることが多く、土が常時湿っている状態が続くと、根が呼吸できなくなり、根腐れにつながります。また、水はけや通気性が悪い土、不潔な用土、肥料焼け、根詰まり、大きすぎる鉢なども土が乾きにくく根腐れの原因となります。
根腐れにより根が傷むと、根から水分をうまく吸い上げられなくなり、葉に元気がないなど一見水不足のような症状が現れます。そのため水不足と誤解し、水を多く与えてますます弱らせてしまうことがあるので注意しましょう。土は湿っているのに葉は黄変したりハリがない場合、季節外の落葉は根腐れを疑いましょう。また、土の表面にカビが生えたり、腐ったような臭いがしたり、コバエが発生するなどの症状も根腐れのサインです。
光量不足

Lorna Roberts/Shutterstock.com
日陰や室内など、光が足りない環境では、植物はうまく生育することができません。茎や枝が徒長して細長く間延びしたり、葉が黄色や茶色に変色したりし、そのままにしておくと株自体が弱ってしまいます。光が足りないとすぐに枯れてしまう、という訳ではありませんが、弱々しく育ち、花や実の数も少なくなるので、健全に育てるためには適度な明るさを確保しましょう。
光量不足で植物が弱ると、葉に元気がなくなって葉が落ちたり、葉の色が薄くなるなどの症状が出るほか、茎がひょろひょろと弱々しく伸びたり、光源に向かって傾いたりします。このような株は日光への耐性が低くなっているため、急に明るい環境に置くと葉焼けを起こしやすく、枯れてしまうこともあるので注意しましょう。
病害虫

Nadiinko/Shutterstock.com
病気や害虫の発生も、植物が枯れる原因の1つとして考えられます。ちょっとした病気や害虫であれば、枯れてしまうほどの被害が出ないことが多いですが、放置してそのままにしておくと被害が進行し、最終的には枯れてしまうことも。こまめに株の状態をチェックし、病害虫を発見したら早い段階で対処するのがポイントです。
病気や害虫の種類により、その症状はさまざまですが、いずれにしても早期の発見と対処がポイント。日頃から、虫食いや病斑などの異常がないかをこまめにチェックするとよいでしょう。
肥料の過不足

Olya Maximenko/Shutterstock.com
肥料は少ないと養分が足らず、植物が元気に育ちません。一方で、肥料が多すぎるのもNG。肥料が少ない場合は生育不良に陥っても枯れることはあまりありませんが、むしろ肥料過多の場合は枯れるほどのダメージになることもあるので、与えすぎには注意しましょう。多すぎたり、高濃度であったり、根に直接触れる状態では植物にとってはダメージとなり、最悪の場合は枯れてしまうこともあります。
肥料不足のサインは、葉色が薄くなったり、生長が鈍くなるなどの症状が現れます。一方、肥料の三大要素の1つであるチッ素が過剰になると、葉ばかりが茂ったり、葉色が濃くなる、花や実がつきにくくなる、株全体は大きくなるが軟弱に育ち、病害虫が出やすくなるなどの症状が現れます。特に鉢植えの場合は、夏場の乾燥時にいつもの感覚で施肥すると濃度が高まりやすく、肥料焼けして株が傷み、極端な場合は枯れてしまうこともあります。適切な量の施肥を心がけましょう。
(広告の後にも続きます)
近年は気候変動が大きな課題に

aleks333/Shutterstock.com
近年、ガーデナーの間で「今までどおりの育て方ではうまく育たない」「育てている植物が枯れてしまった」という声をよく耳にするようになりました。最近は夏の高温や豪雨など、今までにない気象条件が頻発するようになりました。猛暑によって植物の生育適温を上回り、また夜温が下がらないことで植物が夏バテしたり、豪雨により傷んだりなど、極端な気候環境は植物への大きなストレスとなります。実際に近年の気象データを見てみると、猛暑日や熱帯夜、豪雨など、極端な気象現象が増加傾向にあることが読み取れます。

全国13地点平均での最高気温35℃以上の日数推移(1980~2023年)。

全国13地点平均での最低気温25℃以上の日数推移(1980~2023年)。

全国アメダスでの1時間降水量50mm以上の雨の年間発生回数(1980~2023年)。
※グラフすべて出典:
今後はこうした異常気象がニューノーマルになっていくと考えられます。これからの時代のガーデニングでは、こうした異常気象に対応できるだけの丈夫な植物を育てることが栽培のポイントになります。