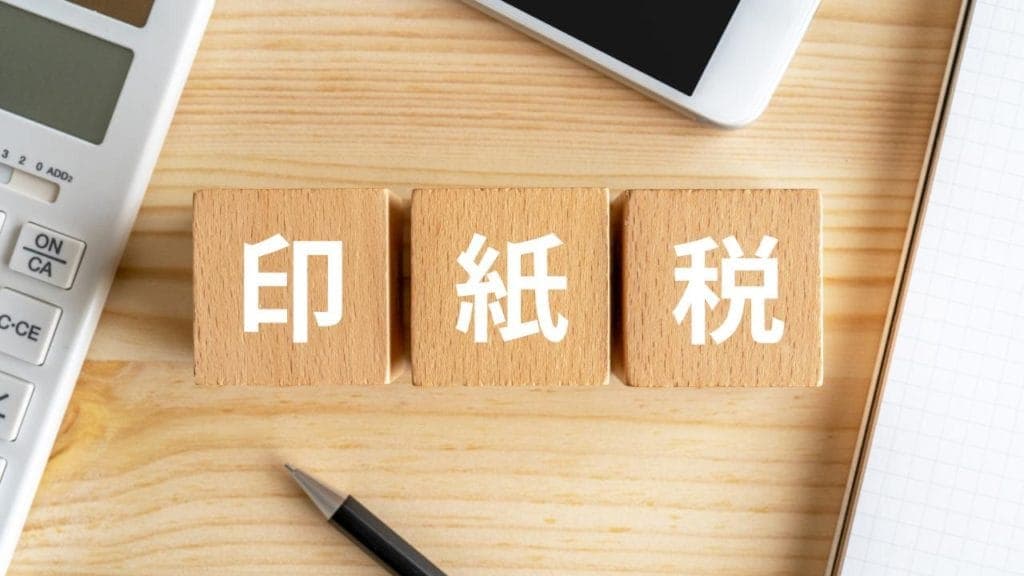手元に現金を残す、いわゆる「タンス預金」をしている方は一定数います。しかし、新紙幣が発行されたり、キャッシュレス決済が浸透したりと金融の世界は大きな変化を迎えています。今、タンス預金はどのようなリスクを抱えているのでしょうか? FP資格も持つ公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。
新紙幣の発行背景にタンス預金の影響?
2024年に新紙幣が発行され、1万円札は福沢諭吉から渋沢栄一へと変更されました。この新紙幣には高度な偽造防止技術が施され、ホログラムなどのセキュリティ機能が強化されています。
新紙幣の発行目的は単なる偽造防止だけではありません。日本では依然として現金志向が強いですが、近年はキャッシュレス決済が普及しています。店舗のレジ作業を効率化し、無人化を促進するためにも現金の流通を減らす意図があります。また、タンス預金として隠されていた現金を消費に回してもらうため、旧紙幣の取り扱いを徐々に不便にすることで、現金を流通させる狙いもあるのです。
加えて、新紙幣の導入は経済活動の活性化にもつながります。旧紙幣を持ち続けることが不便になれば、人々は消費活動を活発化させ、経済の循環が促進される可能性があります。これは政府にとっても重要な政策の一環となっているのです。
さらに、新紙幣の発行にはデジタル化の推進という側面もあります。キャッシュレス決済が普及する中、紙幣の利用を減らし、経済の透明性を高めることも狙いの一つです。特にマネーロンダリング対策として、現金取引の減少が求められています。
(広告の後にも続きます)
「タンス預金」は相続時に「脱税」を疑われるリスクもある
タンス預金にはいくつかのリスクが伴います。
まず、旧紙幣は無価値にはなりませんが、一部の自動販売機やATMでは使えなくなる可能性があります。新紙幣が普及すると旧紙幣対応の機械が減少し、不便になることが考えられます。さらに、タンス預金を持つ人が亡くなった際、相続人がその現金を銀行に預けようとすると、不正資金や脱税を疑われる恐れがあります。特に大量の旧紙幣を持ち込むと、銀行が税務署へ通報する可能性も否定できません。
盗難や火災のリスクも無視できません。タンス預金は現金を物理的に保管するため、泥棒に狙われたり、火災で焼失したりするリスクがつきまといます。また、インフレが進行すると現金の購買力が低下します。銀行に預ければわずかでも利息がつきますが、タンス預金には利息がつかず、資産価値が目減りする恐れがあります。
さらに、相続時に家族間でトラブルになる可能性もあります。タンス預金は発見者が遺産分割の際に正確な金額を報告しない場合、不公平感が生じて相続争いの火種になりかねません。適正に申告しても、多額の現金があると税務調査の対象になることがあります。
また、近年では金融機関による不審な大口入金の監視が強化されています。突然大量の現金を預けると、マネーロンダリング対策の観点から口座の凍結や詳細な資金の出どころを問われる可能性もあるため注意が必要です。