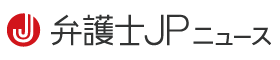自身の記憶と目を頼りに、人混みから事件の被疑者(容疑者)を探し出す「見当たり捜査員」。
警視庁では「見当たり捜査班」が発足した2001年から24年間で、約1400人もの被疑者をこの捜査員たちが検挙してきた。
街中の雑踏に目を凝らし、被疑者を捜し出す彼らは、どんな思いで捜査に臨んでいるのだろうか。警視庁の見当たり捜査員であるAさんに話を聞いた。
コツは「被疑者の印象を記憶に残しすぎない」こと
多くの被疑者の顔を、写真から頭にたたき込む。Aさんが記憶している被疑者の数は約500人に上る。
「長期間逃亡している被疑者や、社会的にも反響の大きい事件の被疑者などは印象に残りやすいですが、見当たり捜査は、特定の被疑者を発見するための捜査手法ではなく、行き交う人々の中から捜査員が記憶している被疑者を発見する捜査手法となります。
そのため、なるべく被疑者一人ひとりに関しての印象を記憶の中に残しすぎないように努めています」(Aさん)
記憶している500人全員を常に想定して、道行く人と合致点がないか注視する。
長時間、同じ場所や周辺にいることも多いため、その場の“空気”を読むことも忘れない。
「被疑者や一般の方が違和感を持たないように、その場所に自然と溶け込む服装などになるように意識しています」(同)
課題は「オンとオフの切り替え」
常に目を光らせ続ける捜査員らの課題は、もっぱら「オンとオフの切り替え」だという。
「私も含め『逃げ得を許さない』という強い気持ちを持っている捜査員が多く、つい捜査に没頭してしまうのですが、集中力を維持するためにも休憩は必須です。責任者の指示等により、オン・オフを明確にするなど、メリハリをつけるよう心掛けています。
とはいえ、どんな仕事にもあると思いますが“職業病”で、人が多いところでは行き交う人をつい確認してしまいます。私も帰宅途中で被疑者を発見し、検挙したことがあります」(Aさん)
毎年暑さが厳しさを増す夏も、寒風吹きすさぶ冬も関係なく人混みに目を向け続けるが、Aさんは捜査員が一番「キツい」と感じるのは、何より被疑者を見つけられない時だと話す。
「どのような気候・天候においても街中で集中し続けることは大変ですが、それ以上に他の捜査員が被疑者を発見する中、自分だけが被疑者を発見できない日々が続く時が一番ツラいですね」
対して、一番の喜びは、やはり「被疑者を発見した時」だ。
「見当たり捜査員として初めて指名手配された被疑者を発見した時のことは、はっきり覚えています。『自分に務まるのか』と不安がつきまとう中で発見できた達成感と、被害者からの感謝の言葉を伝え聞いた時の充実感は忘れられません」(同)
市民の協力も事件解決の「鍵」
インターネットやSNSの普及で、一般市民が「被疑者」の顔写真に触れることも多くなった。
たとえば、大分県別府市で起きた大学生死亡ひき逃げ事件の被疑者・八田與一の写真は、特に拡散されており、報道によれば大分県警にはこれまでに8600件以上の情報が寄せられているという。
こうした一般市民による情報提供について、Aさんは「ありがたい」としてこう続ける。
「過去にもみなさまから寄せられた情報がもとになって、指名手配されていた被疑者の検挙に至った事例が数多くあります。
みなさまにも今以上に、警察から指名手配されている被疑者に関心を持っていただくとともに、被疑者に似た人を発見した際には通報していただきたいです」
中には「ある程度“確実”な情報でなければ迷惑なのでは」と考える人もいるだろう。
しかし、Aさんは「公開手配されている被疑者に『似ているな』と感じる人を見たら、迷わず警察に通報してください」と力を込める。
「その際には、『今日、街ですれ違った』『先週、電車の中で見た』『昨日、客として来店した』『今、公園にいる』など、見た場所や時間を可能な限り正確に伝えてください。そうすれば、その後の捜査にも役立ちますから」
見当たり捜査員は今日も街のどこかで目を光らせている。