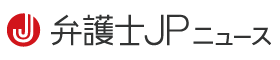バラエティー番組「月曜から夜ふかし」で中国出身の女性の街頭インタビューを意図的に編集し発言の趣旨を歪めたとして、3月27日、日本テレビが番組のホームページに謝罪を掲載した。
28日には村上誠一郎・総務大臣が「日本テレビは正確な情報発信を行い、国民の知る権利を満たす等の放送事業者の社会的役割を自覚していただいて、適切に対応していただければ」と苦言を呈している。
同月31日、日本テレビの福田博之社長が「不適切だった」と認め、番組の街頭インタビューを中止し、再発防止策を講じると発表。
「ねつ造」とも批判される編集を行った日本テレビに、法的な制裁が下る可能性はあるのだろうか。
「カラスを食べる」発言はなかった
問題の場面は、「この春上京する人へのアドバイス」をテーマに東京で実施された街頭インタビュー。
インタビューを受けた中国・広州出身の女性は、カラスが自宅のバルコニーに来てハンガーを持ち去り、それから外で洗濯物を干していないという経験を日本語で語った。
テロップで「東京はカラスに注意」と表示された後、インタビュー場所などは同じ構図のまま、女性が「みんな食べてるから少ないし」と語るカットや、「とにかく煮込んで食べて終わり」と話す別カットが続く。
また、画面には「※中国全域ではありません」との注釈が入っていた。
27日の謝罪文で日本テレビは「実際には女性が『中国ではカラスを食べる』という趣旨の発言をした事実は一切なく、別の話題について話した内容を制作スタッフが意図的に編集し、女性の発言の趣旨とは全く異なる内容になっていました」と釈明。
また、中国語の謝罪文も同時に掲載された。
なお、4月4日時点で「月曜から夜ふかし」公式ホームページに掲載されている謝罪文には、編集の詳細に関する記述はない。
代わりに、女性が「一日も早く元の生活に戻りたいと強く希望」していることや、SNSを含め女性に対する誹謗中傷や番組映像・画像の使用を控えるよう求める内容が記載されている。

日本テレビによる「お詫び」(4月4日時点・公式サイトから)
日テレの編集は「名誉毀損」に当てはまる可能性
発言の趣旨が誤って伝わるよう意図的に編集する行為に、法律的な問題はないのだろうか。
メディアと法律の関係に詳しい杉山大介弁護士は「あえて刑罰法規に照らせば、名誉毀損(きそん)罪にあたる可能性があります」と指摘する。
刑法上、「中国人全体」を対象とした名誉毀損罪は成立しない。原則的に名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人(個人や法人)の名誉を毀損した」場合に成立する犯罪であり、特定の民族や国籍を共有する集団は対象とならないためだ。
しかし、今回の編集内容では中国人全体だけではなく「女性自身がカラスを日常的に食べている」という虚偽の事実も流布されている。
「あとは、その女性がどこの誰なのか一定範囲にだけでも特定されるようであれば、名誉毀損罪の要件にも当てはまってくると思います」(杉山弁護士)
名誉毀損罪は親告罪であるため第三者が刑事告訴を行うことはできないが、もし女性自身が訴訟を提起すれば、刑罰や民事上の損害賠償請求が認められる可能性もあるという。
放送法に「罰則」が設けられていない理由
放送法4条3項では「報道は事実をまげないですること」とされている。
杉山弁護士も、本件は放送法に抵触しており、BPO(放送倫理・番組向上機構)で問題として取り上げられる可能性はある、と指摘する。
一方、放送法では、ねつ造や事実の歪曲に関して罰則が制定されていない。
なぜ、刑罰に問われないのか。杉山弁護士が指摘するのは、罰則を設けることが放送局に与える萎縮効果は非常に大きく、悪用される危険性も高いという点だ。
「罰則とは、ただ『罰を与える』というだけではありません。その過程で、警察による捜査、場合によっては局内への立ち入りまでをも許容することになります。
たとえば、罰則の最終的な適用要件が厳しいものだったとしても、『刑罰が設けられている』というだけで、公権力が放送局に対して捜査による圧力をかけることが可能になります」(杉山弁護士)
つまり、罰則の設定は、公権力による圧力の門戸を開くおそれがある。
「公権力による介入という形にはならないよう、放送局の側は、BPOのような自主規制的な組織で問題を取り上げる運用をしているのでしょう」(杉山弁護士)
大切なのは消費者による「健全な牽制力」
放送法で罰則が設けられていない背景には「報道の自由」と「公共の利益」との複雑な関係が存在する。
杉山弁護士は「報道にも時に問題が起こるため、何らかの牽制(けんせい)力が働く必要があるのは確かです」と認めつつ、以下のように続ける。
「報道が公権力と一体になり、そちらの顔色ばかりを伺うようになることの方が、最終的に情報を受け取る国民の不利益が大きくなるでしょう。
また、政治や刑事司法の分野では行政側の見解がそのまま垂れ流されがちであり、危険性は既に大きいと言えます」(杉山弁護士)
一方、昨今のフジテレビ問題では、消費者が総体となって反感を示すことでスポンサーが離れていき、フジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングスは第三者委員会の設置や元・取締役相談役であった日枝久氏の退任などの対応を余儀なくされた。
杉山弁護士は「これこそ、健全な牽制力だったと言えるのではないでしょうか」と評価する。
「今回の件については、スケジュールに追われるなかで使える映像を用意しなければならないという制作過程において生じる歪み、女性が中国籍ではなかった場合にも『カラスを食べること』にしていたのかという人種差別の疑いなど、具体的な問題に注目するのが適切だと思います」(杉山弁護士)