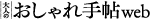今日は二十四節気の「清明(せいめい)」の6日目。“清らかで明るい”春の節気らしく、暖かいぽかぽか陽気の日も増えてきました。
しかしそんな春うららの季節なのに、頭痛が起こりやすい季節でもあるのが悩ましいところ。
頭痛が起きたら鎮痛剤で痛みを抑える人も多いと思いますが、できることなら痛みの原因を根本から改善できたら嬉しいですよね。
そこで今回は、頭痛の原因にアプローチする養生法や薬膳食材、漢方薬についてご紹介します。
あなたの頭痛の原因はなに?東洋医学でチェックしよう

東洋医学では頭痛を原因別に9種類に分類し、それぞれ異なる対処法で原因の改善をめざしていきます。頭痛に悩んでいるなら、まずはその原因を見極めていきましょう。
頭痛の原因は、痛み方や痛む場所などからある程度判別することができます。次から、当てはまる頭痛のタイプを選んでください。
①頭が熱っぽく張るように痛む
②後頭部から首すじにかけて痛む
③頭が重く締めつけられるように痛む
④疲れたときに痛みが強くなる
⑤鈍い痛みでふらつきをともなう
⑥弱い痛みが慢性的に続き、耳鳴りやめまいをともなう
⑦片頭痛がよく起こる
⑧ぼんやりした頭痛で、痛みがしつこく長引く
⑨痛む場所は固定していて、刺すような強い痛みがある
東洋医学では、頭痛は大きく「外感頭痛」と「内傷頭痛」とに分けられます。
外感頭痛とは天候や気温、感染症などの影響を受けて起こる頭痛で、①~③はその外感頭痛に当たる症状。
内傷頭痛とは体内の機能失調が原因で起こる頭痛で、④~⑨がその症状に当たります。
次からは、それぞれの頭痛の原因と予防法、おすすめの薬膳食材と漢方薬について見ていきましょう。
(広告の後にも続きます)
「外感頭痛」は暑さや寒さ、湿気などが原因で発症する

①~③の外感頭痛は、体外から侵入する原因を感受して発症するため「外感」と呼ばれています。基本的にはかぜにともなう急性の頭痛が多く、次の3つの種類があります。
◆ ①の熱っぽく張るように痛む頭痛は「風熱頭痛(ふうねつずつう)」
外界から熱が体内に侵入して気(き=エネルギー)や血(けつ≒血液)の流れを乱すことによって生じる頭痛で、春~秋に起こることが多い症状。熱っぽく張るような痛みが特徴で、頭が裂けるように痛む場合もあります。風熱頭痛は体内の水分が不足している体質の人に起こりやすいので、水分不足を招く夜ふかしやストレスなどを避けることが予防策に。薬膳で予防や改善をする場合は、菊花、ミント、セロリ、豆腐、緑茶などの体内の熱を冷ます食材をよくとりましょう。漢方薬では荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)などが用いられます。
◆ ②の後頭部から首すじにかけて痛む頭痛は「風寒頭痛(ふうかんずつう)」
外界の寒気が体内に侵入して生じる頭痛で、寒気で冷えることによって気と血のめぐりが停滞するために痛みが起こるもの。冬に発症しやすく、後頭部から首すじにかけて痛み、くしゃみ、鼻水、悪寒などをともなうことが多いです。風寒頭痛を予防するには、体を冷やさないこと、特に首周りに風が当たらないように防寒することが大切。薬膳で予防や改善をする場合は、しょうが、ねぎ、しそ、みょうがなどの辛味食材を用いて、発汗作用で寒気を体外に発散します。漢方薬では葛根湯(かっこんとう)、麻黄湯(まおうとう)、桂枝湯(けいしとう)などが用いられます。
◆ ③の重く締めつけられるように痛む頭痛は「風湿頭痛(ふうしつずつう)」
外界の湿度に影響を受けて生じる頭痛で、梅雨の季節に多く発生します。湿気が体内に侵入して頭部の気を包み込むため、重く締めつけられるような痛みが起こるのが特徴。風湿頭痛は体内に余分な水分がたまっている人に起こりやすいので、水分がたまる原因となる甘いものや脂っこいものを控えめにすることが予防策に。薬膳で予防や改善をする場合は、体内の余分な湿気を体外に発散するしょうが、ねぎ、しそ、パクチーなどを積極的に食べるといいでしょう。漢方薬では藿香正気散(かっこうしょうきさん)などが用いられます。