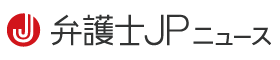6日、昨年2月に兵庫県警が12歳の女子小学生に対し警察署内で長時間の事情聴取を行い、身に覚えのない虚偽の「自白」を強要したことが報道され、物議を醸している。刑事事件の捜査において、捜査機関による自白の強要・誘導が問題になるケースが後を絶たない。
古くは昨年、再審で無罪判決が下された「袴田事件」、最近では「プレサンス・コーポレーション元社長事件」「大川原化工機事件」など、自白を強要しようとして長期間の身柄拘束を伴う取調べを行うケースが発生している。
そもそも刑事訴訟法上、被疑者・被告人の自白についてはどのように規律されているのか。そこにはどのような問題があるのか。
これまでに10件の無罪判決を勝ち取った実績があり、日本と欧米の刑事司法制度に詳しい川﨑拓也弁護士(藤井・梅山法律事務所、京都大学法学部・法学研究科客員教授)に聞いた。
取調べ段階での供述は「原則、証拠能力なし」だが…
取調べにおける自白(自白調書)は被疑者自身に不利な事実を認める供述であり、「証拠」の一種である。そして、訴訟上、裁判所が証拠調べをし、事実認定に用いるには「証拠能力」が認められなければならない。
証拠能力とは、いわば、訴訟(公判)の場で証拠として用いてよいかという「資格」である。
自白の証拠能力については刑事訴訟法上、どのようなルールがおかれているのか。
川﨑弁護士:「まず、取調べ段階で得た供述調書の証拠能力は、否定されるのが大原則です(刑事訴訟法320条参照)。これを『伝聞法則』といいます。
裁判の基本原則として、あくまでも判決を下す裁判所の面前で証拠調べが行われる必要があります。被告人や証人についても尋問等が行われ、供述内容の真実性がチェックされなければならないことになっているのです。
たとえば、捜査機関が被疑者を取り調べて『調書』を作成したとします。後に裁判の場で捜査機関がその調書を証拠採用するよう求めたのに対し、被告人が不同意にしたら、その調書には原則として証拠能力が認められません。これが伝聞法則です」
ただし、刑事訴訟法は例外的に証拠能力が認められる場合(伝聞例外)を定めている(321条~328条参照)。そして、被告人の自白については証拠能力が認められる要件が緩く設定されているという。
川﨑弁護士:「被告人の自白または取調べ等での発言を取調官がまとめる『供述録取書』で、本人が署名または押印したものは、その自白が任意になされたことを条件として、証拠能力が認められるとされています(322条1項)。
捜査官としては、いったん自白をとってしまって、『任意性』が認められさえすれば、裁判所に証拠として採用してもらえるので、とにかく自白をとろうとして手荒な取調べがなされがちです」
「自白の偏重」を招く…「任意性」の要件の問題点
強要された自白は、「任意になされた」の要件(322条1項)をみたさないのではないか。
川﨑弁護士:「『自白に任意性がなかった』という主張は実際上ほとんど認められません。なぜなら、取調室で捜査官から自白を強要されたと訴えても、捜査官が法廷で『そんなことをした覚えはありません』と証言してしまえば事実上覆せないからです。密室の取調べでは、水掛け論になってしまいます。
2016年の刑事訴訟法等の一部改正によって、一部の重大犯罪等に限り、逮捕・勾留中の被疑者の取調べについては、『取調べの可視化』が義務付けられました。これによって、水掛け論はなくなり、取調べが適正なものになるかとも思われました。
しかし、法改正後も、札幌の母親による子の監禁事件(不起訴)や、プレサンス・コーポレーション元社長事件、大川原化工機事件のように、身柄拘束下で自白を強要される事態が起こっています」
「自白だけでは有罪にできない」というルールもあるが…
刑事訴訟法では、自白以外の証拠がない場合には有罪とされないという「補強証拠法則」も定められている(319条2項)。しかし、川﨑弁護士によれば事実上、空文化しているという。
川﨑弁護士:「たとえば、殺人事件の場合だと、被害者の(他殺)遺体があればそれが『自白以外の証拠』と扱われることになっています。
補強証拠法則が機能するのは『殺人の自白は得られたが、遺体さえ見つからない』といった極めて稀なケースに限られています。事実上、自白偏重に対する歯止めとしては機能していません」
「取調べの可視化」が導入されたが…
2000年代以降、自白の偏重と、自白を得るための身柄拘束の長期化が問題視されるようになった。そして、日弁連等を中心に、取調べの可視化(録音・録画)の導入の必要性が叫ばれ、前述のように2016年に制度化された。
この制度はどのようなものか。また、可視化によって事態はどの程度改善されたのか。
川﨑弁護士:「取調べの可視化は、『裁判員裁判対象事件(※1)』と『検察官独自捜査事件(※2)』について導入されました。
捜査機関の録音・録画義務を担保するため、被告人が任意性を争った場合には、検察は必ず録音・録画データを格納した媒体の証拠調べを請求しなければなりません(刑事訴訟法301条の2)。
取調べの可視化の対象となる事件では、殴る蹴るなどの強引な取調べは一定程度なくなり、『任意性』の争いもだいぶ減りました」
※1:死刑または無期の懲役・禁錮にあたる罪など重大事件
※2:政治家や公務員による汚職事件、高度な企業犯罪など
しかし、現行の制度は、対象事件が限られていることと、「逮捕前」の任意取調べが対象外だという問題があると指摘する。
川﨑弁護士:「対象となる事件が少なすぎます。一定の重大事件に限られており、窃盗、詐欺、背任などは対象外です。対象外の事件でも検察では任意で録音・録画しているケースが増えていますが、警察ではしていないケースが多いです。
また、逮捕・勾留中の被疑者の取調べのみが対象で、逮捕前の任意取調べは含まれません。
そこで、逮捕できるほどの嫌疑がない場合に任意聴取して自白を取ろうとするケースがあります。
また、悪質なものだと、逮捕状をとっているのにあえて執行せずに、任意聴取をして強引に自白させ、逮捕後の取調べで『さっき言った通りですよね』と同一内容の供述をさせるケース(反復自白)があります」
「黙秘権の保障」の実質化も重要
黙秘権の保障が不十分だという問題も指摘される。
川﨑弁護士:「黙秘権は、『言いたくないことを言わなくていい』という権利です(憲法38条1項)。しかし、日本では黙秘権は絵に描いた餅になってしまっています。
被疑者が黙秘しても取調室に滞留させ続け、取調べを続けている実態があります。『説得』と称して、『黙秘するっちゅーことは、なんか後ろ暗いところがあるんちゃうんかい』などと脅したり、机をたたいたりします。
欧米の多くの国々では黙秘したらそれ以上の取調べを続けることも、取調室への出頭滞留を義務付けることも許されません。
どの国でも、日本では黙秘している人を長時間『説得』するという話をすると驚かれます」
アメリカでは『ミランダ警告』と言って、身柄拘束下の被疑者に対して尋問を行う前に、捜査官は、黙秘権や取調べに弁護士を立ち会わせる権利等を伝えなければならないルールが確立されている。もし、ミランダ警告が行われないまま被疑者が自白した場合には、その自白の証拠能力が否定される。
ここで一つ疑問が生じる。黙秘権が強く保障されているはずのアメリカで、冤罪事件が時として問題となるのはなぜか。
川﨑弁護士:「第一に、被疑者がミランダ警告で告知された権利を放棄することは認められています。そして、捜査官が被疑者に対し、黙秘権等の権利を放棄させるケースが多くみられます。そうなれば、日本と同じ問題が起こります。
第二に、日本と同様、あえて逮捕を遅らせて逮捕(ミランダ警告)前の段階で強引に自白させるという問題があります。
第三に、取調べの問題からは離れますが、アメリカには『司法取引』という制度があり、これが冤罪を生む方向に作用するケースがあります。捜査官は、『このままだと厳罰は避けられない。自白すれば罪が軽くなるから取引しよう』などと持ち掛けます。それに被疑者が応じ、実際には無実であるにもかかわらず罪を認めてしまうのです」
日本でもアメリカでも、法制度の多少の差はあれ、黙秘権や弁護人を取調べに立ち会わせる権利が実質的に保障されていなければ、冤罪を生む温床になるという問題を抱えていることがわかる。
全件・全過程の「録音・録画」と「弁護士の取調べへの立ち会い」を
このような問題を踏まえ、川﨑弁護士は、黙秘権を実質的に保障し、冤罪のリスクを排除するには、「全件全過程の録音・録画」「弁護士の取調べへの立ち会い」「被疑者が黙秘権を行使した場合の取調室への留め置きの禁止」が必要だと説明する。
川﨑弁護士:「これら3つはどれが優先ということではなく、全部必要だと考えています。
たとえば、可視化があるから弁護人立会いまでは必要ないのだ、との指摘が検察官などからなされています。
しかし、可視化だけでは十分に虚偽供述を防ぐことができないことは、プレサンス・コーポレーション元社長事件での、検察官による違法な取調べによって、すでに明らかになっています。
また、被疑者が黙秘権を行使したら取調べが終わるならば、『取調べの可視化』も『弁護士の取調べへの立ち会い』も不要、との考え方もあり得るかもしれません。
しかし、黙秘権を行使せず、積極的に供述をするような事件もあります。たとえば、起訴された場合に無罪を目指すような事件では弁解の後出しといわれないよう、取調べ段階で供述すべき場合もあり得ますし、不起訴処分を獲得するために積極的に供述する事件も考えられます。
だからこそ、『黙秘権の保障』=『被疑者が黙秘権を行使した場合の取調室への留め置きの禁止』だけでは足りません。違法な取調べを抑止するため『可視化』が必要だし、『弁護人の立ち会い』も全部必要なのです」
刑事裁判の大原則とされる言葉の一つに「十人の真犯人を逃すとも一人の無辜(むこ(※))を罰するなかれ」というものがある。
誰もがある日突然、身に覚えのない容疑で身柄拘束を受け、罪に問われる危険性があるといっても過言ではない。今なお、冤罪や強引な取調べが根絶されない背景に、現在の法制度が抱える「穴」があることは十分に周知される必要がある。
※無実の人