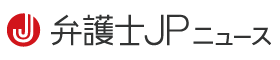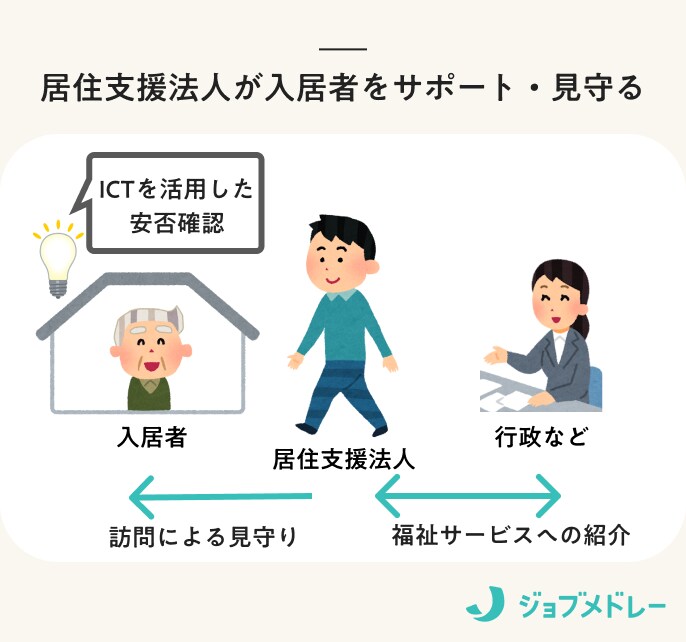遊技人口の減少や新型コロナ、新紙幣導入などの影響でパチンコ業界ではホールの倒産が相次いでいる。
警察庁の統計によると、2023年時点でのパチンコ店の店舗数は7083軒と、20年前の1万6076軒に比べて約56%の減少となった。
しかし、かつては庶民の娯楽として多くの人の心をつかみ、巨大産業にまで発展した。本連載では、そんな戦後・昭和のパチンコの歴史を紹介する。
第4回の舞台は昭和30年代。パチンコ店が景品の自家買いを避けるようになるなか、暴力団と在日朝鮮人や中国人の間で、景品買いを巡る泥沼の利権争いが勃発。
在日朝鮮人の景品買いの主流であった「おばちゃんたち」は、生活の糧を守るため、死をも恐れず、暴力団に対抗したという。
パチンコ店を巻き込んだ利権争いがエスカレートしていくなか、警察当局がついに動き出す。
それまで“スルー”されてきた景品買いだが、なぜ、急に取り締まりを強化する必要があったのか。背景には昭和39(1964)年の「あの出来事」があったという――。(全4回)
※ この記事は溝上憲文氏の書籍『パチンコの歴史』(論創社)より一部抜粋・構成。
殺人事件にまで発展、警察の最大の悩みに…
当時の警察はこうした事態に直接手を下すことはなかった。客が受け取った景品を第三者が買う行為は違法ではない。摑まえるとすれば「道路で客を待ち、立ち止まっているのを道路交通法違反でしょっぴく」(業界関係者)のがせいぜいだったという。
釈放された婦人たちは、また景品買いに戻った。「暴力団といざこざがあるなと予測すると、店から遠く離れて機動隊を配置し、事が起きてはじめて店に踏み込む。それまでは放っておくんですよ」と在日の経営者は当時を振り返える。
昭和31年以降全国的にエスカレートしていった在日と暴力団とのいざこざは、パチンコ店を巻き込み、時に殺人事件にまで発展した。とくに関西地区では暴力団同士の闘争も激化していった。
また、客に提供した景品をパチンコ店が暴力団からふたたび買い取るという法律違反行為も横行し、警察はこの問題をどう解決するべきかが最大の悩みとなる。
五輪開催控えた東京、警視庁が取締り強化
全国各地では暴力団と換金業務を切り離すために第三者を介在させる三点方式などの対策がとられていく。しかし、なぜか東京では暴力団排除がなされないままに放置された。
ところが、昭和38年ごろになって警視庁は急に取締りを強化するのである。その辺の事情について在日のある景品業者がこんな秘話を紹介してくれた。
「ある日、警視庁の担当者がきてこう言うのです。『東京オリンピックが近い。外国の客に景品買いをやっているのを見られるのはまずいし、やめてくれないか。その代わり店から100メートル離れて交換所を作るなら、こちらも黙っている』と。
それから換金用の特殊景品にタバコを使うのもやめてくれと言うんです。それならということで、われわれもそれにしたがい、特殊景品をチョコレートや味の素に代えて商売するようになったのです」
警察当局は、換金問題の根本的な解決策がないままこうした場当たり的なやり方をつづけていった。そして後年、パチンコ店と暴力団との関係をいざ解決しようとした時点で、大変な試練を味わうことになるのである。
戦後の動乱を経て、多くの日本人がパチンコ経営から離れていく中で、在日の経営者はパチンコ業を生業に数々の苦難を乗り越えて今日の一大レジャー産業を築くまでにいたった。
現在、在日のパチンコ店経営者の割合は一説には約8割を占めるといわれる。日本が生んだパチンコ文化は間違いなく在日の人びとが支えているのである。