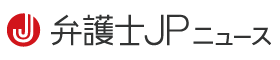国内に推計25万人の当事者がいるとされる「ダブルケアラー」。介護と育児を同時期に担う人のことで、うち8割が働き盛りの30~40代と言われている。
仕事への影響から経済的な困窮に陥る人もいれば、家族関係の変化に苦しむ人もいるというが、これまであまり大きな社会問題として認識されてこなかった。しかし、高齢化、晩婚・晩産化に伴い、 “ダブルケア”当事者のさらなる増加が見込まれている。
ダブルケアの実態を知り、社会的な“課題”を明らかにすべき時期に来ているのではないだろうか。
第2回は、ダブルケアがなぜ難しいのか、実例とともに具体的に解説する。(連載第1回はこちら/全5回)
※ この記事は相馬 直子/山下 順子両氏の書籍『ひとりでやらない 育児・介護のダブルケア』(ポプラ社)より一部抜粋・再構成しています。
かたときも気を抜けないしんどさ
ダブルケアの難しさは、なんといっても、異なるタイプの要求に同時に応えなければいけないところにあります。
それは、複数の人を見守りながら、日常生活をまわしていくことであり、相手の状況に応じて、かたときも気を抜くことなく臨機応変に対応しつづけなければいけない、という難しさです。
たとえば、次のような具合です。
「糖尿病で軽い認知症もあり、車椅子を利用している母親と、ベビーカーに乗る幼児、それに赤ちゃんの3人を連れての外出がとても難しくて、公園にもなかなか行けない」
「自分がトイレに行っている間に、認知症の母親が、泣きだした4か月の赤ん坊に、よかれと思って自分の薬をスプーンであげようとしていた。幸い赤ん坊が口を閉じて食べなかったけれど、口に入っていたらと思うと、トイレに行くタイミングを見つけるのも大変」
「義理の両親と同居しています。認知症の義理父の介護を義理母と一緒におこないながら、2人目、3人目を出産。3人目の妊娠中に、義理母が転倒骨折して入院。乳児の世話をしながら義理父も見なければならず、いっぱいいっぱいでした。
義理父の見守りでは、予測がつかないできごともありました。夜、子どもを寝かしつけている間に義理父が家の外に出てしまいましたが、子どもを家に置いたまま後を追うわけにもいきません。すぐに主人に電話しましたが、帰ってきてくれるまで義理父に何もないことを願いながら、待機することしかできませんでした」
「夜、赤ん坊が寝たと思ったら、認知症の母親が起きだしてきて話をしだすので落ちつかせ、母親が眠ったと思ったら、今度は赤ん坊が起きて授乳する、というくり返しで、いつも睡眠不足です」
このように、子育てと介護を同時に担うというのは、どんなに気力と体力がある人でも、一人で乗りきるのはあきらかに無理があるような厳しい局面の連続です。
社会的な問題意識の共有と、制度の整備が必要です。
「ケア労働」とは食事や排泄の世話だけではない
経済学者ヒメルヴァイト(Himmelweit)は、ケア労働には二つの局面があると論じています。
一つは、世話をすること(Caring for)、もう一つは気にかけること(Caring about)です。つまり、「ケア労働」とは食事や排泄、入浴や着替えといった、身体的な世話を指すだけでなく、相手の存在を気にかけたり、相手の様子に配慮したりすることも含まれるというのです。
身体的な世話をするわけではないけれども、危険がないか気を配ったり、話し相手になったり(あやしたり)、そばにいて時間を過ごすことも、ケア労働に含まれるということです。
ケア労働をこのようにとらえると、ダブルケアの複雑さがより浮き彫りになってくるように思います。
つまり、ダブルケアとは、おむつを替えながら、その横で食事をとる親に気を配ったり、泣く子どもをあやしながら、記憶障害の親の話に耳をかたむけるといったことなのです。
これは、同居している人に限った話ではありません。親の生活を支えるために実家に戻ったり、遠距離から電話をかけて安否を確かめたり、生活必需品を買って送ったり、ケアマネジャーなどの福祉専門家と連絡をとったりしながら子育てをしているといった方々も、すべてダブルケアラーと考えることができます。
ダブルケアをおこなっている方は、日々、子育てと介護のどちらを優先させるかの決断に迫られています。
泣く子どもをあやすのか、不安になっている親の話に耳をかたむけるのか。どちらに先に食事を出すのか。お風呂の順番はどうするか。健診か、通院か。「散歩」に出てしまった親を探しに行くのか、家で子どもと待っているのか。週末を子どもと過ごすのか、親のところに行って掃除や食料の買い出しを手伝うのか。
ダブルケアをする人の多くが、どちらかを優先しながら、選ばなかった一方に対して「十分に世話をできなかった」と悔やむ気持ちを抱えています。