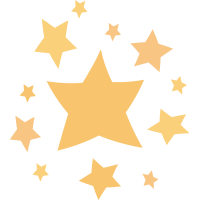奄美大島で総合医療医・産婦人科医として日々多くの患者と向き合っている小徳羅漢(ことくらかん)先生(32歳)。離島医療の課題などについてもSNSなどを通して発信しています。
小徳先生の実家は茨城県の診療所。家の扉を開けたら医療がある、ある意味24時間いつでも父親の医療が受けられる環境で育ったそうです。小徳先生が離島医療に取り組むことになったきっかけや、現在感じている課題などについて聞きました。
全2回のインタビューの1回目です。
夕方になると医師がいなくなる、離島の環境に衝撃を受け、離島医療に関心を抱く

――小徳先生が医師になろうと思ったきっかけを教えてください。
小徳先生(以下敬称略) 父が医師で、茨城県で診療所を開いています。そのため僕は、生まれたときから家の扉を開いたらすぐ診療所という環境で育ちました。父は昔ながらの町医者で、内科から整形外科、精神科など、さまざまな症状の患者さんを診ていました。自転車に乗り老人ホームなどに診療に行くこともありました。そんな父がかっこよくて、医師というのがとても身近な将来の道であったことはあると思います。「自分もいずれはそんな父みたいな町医師になるだろう」と思っていました。
――離島医療に関心をもったのはいつころでしょうか?
小徳 高校は神奈川県の私立高校に進学したのですが、修学旅行の行先が長崎県でした。自由行動の時間が1日あり、僕たちのグループは伊王島に行くことを選びました。島を散策したり、海で遊ぶことが目的でした。伊王島は、とても美しい島で、海はきれいで白い教会や温泉もあり、食事はおいしくて、とてもすてきな場所だなと思いました。
ところが、島には常駐の医師がいないと聞き、驚きました。医師は日中だけフェリーで島に来るのですが、夕方には本土に帰ってしまうそうです。「もし島の人が夜中に体調を崩したり、けがをしたりしたらどうしたらいいんだろう」と感じました。僕自身は、すぐそばに医師である父がいたので、ちょっとしたことでもすぐ診てもらえました。だから、具合が悪いときにすぐ医師に診察してもらえないのは、島の人たちはどんなに心細いだろうと思ったんです。
そのときに「自分が離島で医師として働けばいいんだ」と考えたのが最初のきっかけです。
東京の大学の医学部に進学。医師の将来を思いながらも悩み、さまざまなアルバイトも経験

――その後、医大に進学したそうですが、ずっと離島医療を目標にしていたのでしょうか?
小徳 それが大学時代は目標を見失い、勉強への興味が薄れてしまったんです。というのも、僕が進学した東京医科歯科大学は、研究者や世界で活躍する医師を育てるのを目的とした大学です。離島医療に関する授業もほとんどなく、卒業後は大学病院に残って最新医療を研究するのが当たり前というような雰囲気でした。
もちろん、専門的な知識を深め、重い病気と向き合う医師はすばらしい存在だと思います。でも、僕の医師のイメージは、町医者として多くの患者さんと触れ合う父の姿でした。だから、大学の雰囲気にギャップを感じることが多くて…。
あるとき実習で、外科の先生と一緒に病室を回った際、入院患者さんが風邪をひいたと訴えたんです。すると外科の先生は「じゃあ内科に相談しよう」と言っていました。その様子を見て「自分の専門以外のことを診察しないのは、僕がめざす道ではない」と思ってしまったんです。
医師という職業に対して失望し、勉強はあまりしなくなりました。医学部を卒業したら医師にしかなれないのであれば、在学中に医学以外のことをたくさん経験しようと学校の外に飛び出しました。カメラマンや映画のエキストラ、マッサージ屋のアルバイトをしてみたり、子どもたちの遠足に付き添う遠足のお兄さんをしてみたり、LGBTQの人たちのパーティーに参加したり…。今思えば、そのときの経験が医師になってから活かされています。広い社会を見られたし、世の中にはいろんな人がいると学べました。もし病院しか知らないまま医師になっていたら、「世の中には多様な人がいる」と頭でわかっていても、理解しきれなかったかもしれません。
配信: たまひよONLINE