高学年でも絵本の読み聞かせは大切

高学年の子どもにも、親の読み聞かせは大切です。読み聞かせをすることで親子のコミュニケーションが深まり、想像力を伸ばす手助けにもなるのです。
子どもから「もういいよ」と言ってくるまでは、ほんの数分でもよいので時間を作り、読み聞かせをしてあげたいですね。
親の愛情を感じられる時間
子どもにとって「読み聞かせ」は、親の愛情を肌で感じられる大切な時間です。
ママをひとり占めして甘えることで気持ちが安らいぎ、普段思っていることや学校でのできごとなどを口にするきっかけにもなるでしょう。
読み聞かせは、親子のコミュニケーションを円滑にする役割も担っているといえます。
読み聞かせを通して子どもの気持ちに寄り添えるのは、親にとっても大きなメリットとなるのです。
成長とともに想像力や感受性に変化がある
高学年になると、小さな頃とは違った想像力や感受性を持つようになります。
昔読んであげた絵本や低学年向けの絵本でも、読んでみると意外な反応を示すこともあるかもしれません。思い込みを捨てて、いろいろな種類の絵本を読んであげるとよいでしょう。
また、絵本は1人で読むよりも親に読んでもらう方が物語に集中しやすく、登場人物に思い切り感情移入できます。読み終えた後、親と感想を共有できるのも感受性を高めるポイントです。
はじめてみませんか 絵本の読み聞かせ|子ども読書の情報館 文部科学省
親子で楽しめる高学年におすすめの絵本
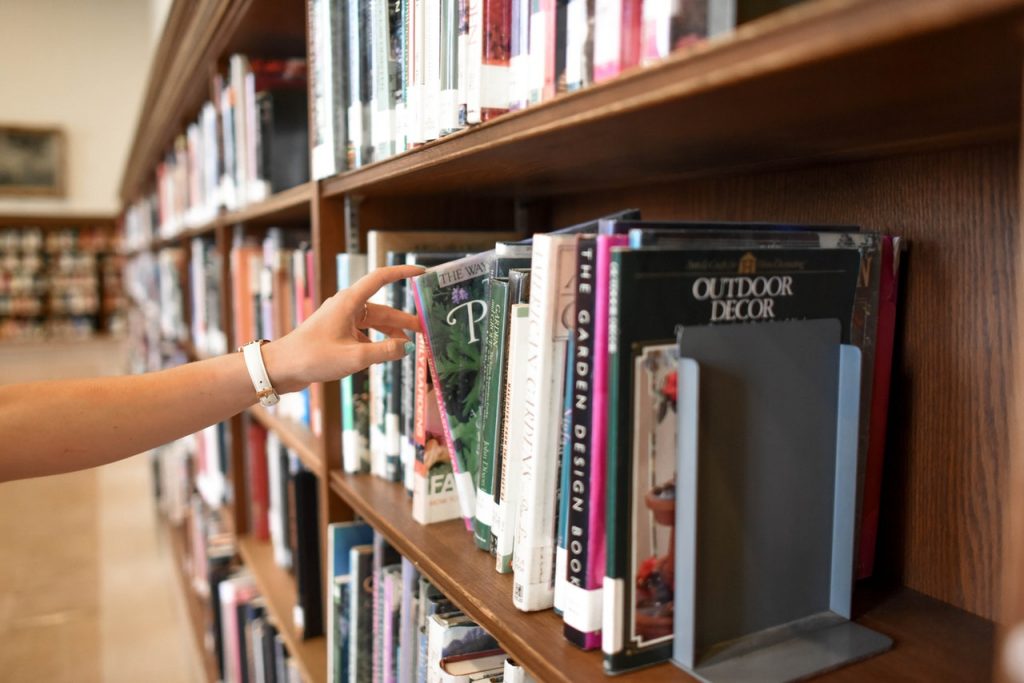
高学年の子どもには、ある程度のユーモアや、読み終えた後に内容について考えさせられるような「ひねり」の効いた絵本がおすすめです。
一緒に笑ったり考えたりして、親子で楽しめる絵本を紹介します。
思わず笑える 『オニのサラリーマン』
『オニのサラリーマン』は、普通なら怖いものとして描かれる存在の「鬼」や「地獄」を、コミカルに描いた作品です。
地獄を会社に、鬼をサラリーマンに見立てた親しみやすい設定が受け、読み聞かせ絵本として大変人気があります。
主人公の「お父さん赤鬼」が見せる哀愁や、関西弁で展開される会話にも、ついつい引き込まれてしまうでしょう。
読んでいる大人も、聞いている子どもも思わず笑ってしまう、ユーモアにあふれた絵本です。
読み聞かせの導入に 『ライフタイム いきものたちの一生と数字』
『ライフタイム いきものたちの一生と数字』は、動物の一生にまつわる数字に着目した斬新な内容で、子どもの好奇心を刺激する科学絵本です。
100や1000などの大きな数字が出てくるので、高学年の子どもに向いています。
「一生のあいだにキツツキが木にあける穴の数」といった興味をひきやすいテーマが満載で、「30個」という数字に対して「たった30個」と思うのか「30個も?」と思うのか、子どもの反応が楽しみになります。
3分程度で読み終わるため、長い読み聞かせ前の導入本としてもおすすめです。
ひねりの効いたロシア民話 『三つのまほうのおくりもの』
『三つのまほうのおくりもの』は、ロシアの昔話を元にした、ひねりの効いた結末が印象的です。
小麦粉をめぐって金持ちの兄と貧乏な弟が繰り広げるユーモラスなストーリーに、高学年の子どもも夢中になるでしょう。
遠い北の国「ロシア」の村の情景に思いを馳せることで、子どもの好奇心や想像力を一層ふくらませることができますよ。
