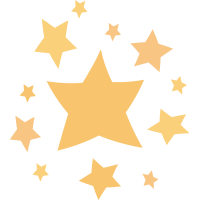3、「暴力行為等処罰に関する法律」違反となり得る事例
「暴力行為等処罰に関する法律」という名称から、暴力団などの集団に適用される印象をもたれがちですが、同法違反は日常生活でも生じ得る犯罪類型です。
そこで、以下では同法違反を問われるリスクがある代表的な事例について、それぞれ具体的に紹介します。
(1)DVなどの家庭内暴力
DVなどの家庭内暴力に同法が適用される可能性があります。
たとえば、夫が妻に対して日常的に暴力をふるっているなら、常習性が認定されて第1条の3違反を問われると考えられます。
また、包丁を持ち出した子どもが親に対して脅迫めいた言葉を投げかけたケースでも、第1条に定める「凶器を示し」ての「脅迫」に該当すると考えられます。
(2)グループ同士の喧嘩
グループ同士の喧嘩は「多衆の威力を示し」ての「暴行」といえるので、第1条に違反するでしょう。
たとえば、居酒屋などの酒席で他グループとの口論が殴り合いの喧嘩に発展した場合や、その喧嘩が原因で店舗の物品を損壊したケースなどが挙げられます。
(3)学生運動
学生運動が過激化すると同法違反に該当する可能性があります。
たとえば、学生運動の構成員が集団でデモ行為などを実施し、大学職員や警察官などと衝突した場合、第1条が適用されます。2009年には、法政大学の学生運動に参加した学生らが同法により起訴された事件もありました(2014年、学生らの無罪が確定)。
4、暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されたらどうなる?
「暴力行為等処罰に関する法律」違反で逮捕された後は、以下の流れで刑事手続きが進みますので、それぞれの段階に応じた対応が必要です。
逮捕後の取調べ
勾留手続
検察官による起訴・不起訴の決定
起訴処分が下された場合の刑事裁判
(1)逮捕後取調べの段階
警察官に逮捕された後は、捜査機関によって被疑者の取調べが実施されます。
警察による取調べは身柄拘束から48時間以内に行われ、検察に身柄が送致される場合には検察官が身柄を受け取った時から24時間以内(身柄拘束から72時間以内)に取調べが行われます。
なお、すべての事件が検察官に送致されるわけではなく、犯情が軽微であること、被害額が少額であること、被害者の処罰感情が厳しくないこと、前科前歴、その他被害者との関係性や犯行に至った経緯などを総合的に考慮して、犯罪事実が極めて軽微で、検察官があらかじめ送致の手続きをとる必要がないと指定したものは、「微罪処分」として、検察官に送致されずに事件は終結します。
たとえば、居酒屋で酔ったうえでの喧嘩で同法違反を理由に現行犯逮捕された場合でも、初犯で被害者の怪我が軽微であるなどの事情があれば、「微罪処分」により被疑者が釈放される場合もあります。
また、微罪処分に当たらない場合でも、これ以上身柄を拘束する必要がないと判断されると(反省の姿勢が見られる、罪証隠滅や逃亡のおそれがないなど)、「書類送検」という方式で、身柄拘束を伴わずに事件が検察官に送致されることがあります。
たとえば、夫婦間の突発的な喧嘩で、継続的なDVが認められず、被害を受けたパートナー側も捜査の継続を望んでいないような状況であれば、逮捕後釈放のうえ、書類送検によって手続きが進行し、不起訴処分を獲得できる公算もあるでしょう。
このように、「暴力行為等処罰に関する法律」違反で検挙された場合であっても、犯行の経緯や被害状況によって、警察署における捜査限りでの事件終結や身柄の解放を目指すことができます。
そのためには、逮捕後初期の取調べ段階での対応が鍵になるので、すみやかに弁護士に相談をして、捜査への対応などについてアドバイスをもらうべきでしょう。
(2)勾留手続の段階
身柄が検察官に送致された後、検察官が、罪証隠滅や逃亡のおそれがあり、さらなる取調べを行う必要があると判断したときは、勾留請求により10日間身柄を拘束されます。
また、捜査活動の進捗状況等によりさらなる証拠収集の必要が認められる場合には、さらに10日間勾留期間が延長される場合もあります。
つまり、勾留による身柄拘束期間は、最大20日間に及ぶ可能性があります。
たとえば、配偶者に対する暴力行為について同法違反の容疑で逮捕された後、度重なる長期的な暴力行為が判明した場合や、パートナーサイドが厳罰を望んで示談の成立が難しい場合、あるいは暴力行為の存在が明らかで被害者の傷害も深刻であるにもかかわらず加害者が犯行を否認している場合などでは、勾留請求がされ身体拘束が長期に及び、厳しい取調べが継続する可能性が高いといえます。
勾留期間が長期化すると、勤務先に対して欠勤理由を説明しづらくなり、無断欠勤により解雇されるリスクが高まります。
身柄の拘束期間を短縮するためには示談交渉や保釈に向けての手続きを進める必要があるので、すみやかに弁護士に相談した方がよいでしょう。
(3)起訴・不起訴決定の段階
逮捕・勾留後の取調べで得られた供述証拠やさまざまな物的証拠、被疑者の反省具合、被害者の処罰感情などを総合的に考慮して、検察官が起訴・不起訴を判断します。
起訴処分が下されると刑事裁判に進み、不起訴処分が下されるとその時点で事件が終結します。
まず、検察官が起訴処分を下す場合として、その後の刑事裁判で有罪を獲得できる高度な見込みがあるケースが挙げられます。
被疑者が罪を犯したとは考えられない場合や、罪を犯したことに疑いがあっても証拠が乏しいような場合には、不起訴処分が下されます。
とはいえ、同法違反で現行犯逮捕された状況であれば、犯罪事実自体を否認して不起訴を目指すのは現実的ではないと思われます。
一方、嫌疑が充分あっても、余罪の有無・犯人の性格・犯行に至った経緯・年齢や境遇・身元引受人の有無・更生の可能性・被害者の意向などを総合的に考慮して、公訴提起するべきではない、あるいは公訴提起する必要がないと判断できる状況であれば、不起訴処分や起訴猶予処分が下されます。
つまり、同法違反で現行犯逮捕されたようなケースで起訴処分回避を目指すのなら、無実の場合は別として、犯行自体を否認するのではなく、反省の姿勢を示したり、示談交渉をまとめたりする戦略が有効だということです。
被害者が負った傷害の程度が深刻であるほど不起訴処分獲得は難しくなりますが、街中での喧嘩や夫婦間での突発的なトラブルの場合には不起訴処分獲得の余地はおおいにあります。
逮捕・勾留されたからといって防御活動を諦めるのではなく、釈放後に社会復帰しやすい状況を作り出すために、弁護人を選任して適切な対処法を提案してもらうべきでしょう。
(4)刑事裁判の段階
検察官が起訴処分を下すと、刑事裁判にかけられます。弁論手続きや証拠調べ手続きを経て判決が下されます。
同法違反で検挙されたケースだと、適切な防御活動を展開しなければ適用条文に応じて懲役または罰金刑が科されかねません。
そこで、無罪判決を目指す場合には検察官の主張や立証を覆すことが必要です。
有罪が明らかな場合でも、執行猶予付き判決を獲得するために情状酌量による減刑を目指すなど量刑を争うべきです。
配信: LEGAL MALL