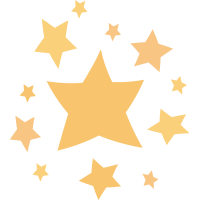旧満州で難民化した日本人妻たちとの“共通点”
当時日本の植民地政策下にあった旧満州で開かれた花嫁学校「女塾」にいた女性たちについて綴られたこの本にも、現在の取材に結びついた背景──本事件のよう逃げ場を失い、子どもに加害してしまうケースが繰り返し発生してしまうメカニズムが潜んでいました。
「『満州女塾』を書いたことで、子どもを殺めてしまう親としては、当時の親たちも、現代の親たちも、その時点で精神的な病理性を抱えるまで追い詰められているという点では同じではないかということに気づかされました。精神的な病理性とは、この上もない心の苦しみ、トラウマと呼んでいいものです。取材対象者となった女塾の卒業生は、日本から開拓民の妻になるために送り込まれましたが、満州国崩壊後に夫は兵隊に取られており、子どもを連れて難民化して窮地に立たされた。つまり、国家や社会が、さまざまな意味で母親を追いつめていったわけです。
そのなかで少なくない方が子どもをその場に放置したり、時には自ら殺めたりしています。『我が子の首に手をかけた』という人にも話を聞きました。中には出産直後、その場に新生児を置いてきたという方もいました。実際にそういうお話を聞く中で、人間が起こす行動というのはそれぞれが置かれる状況しだいであり、極限まで追いつめられた親が子どもに『死んでほしい』と感じてしまうこともあり得るとわかりました」
女塾のあった当時と違い、現代は公的機関へ救いを求める選択も設けられています。しかしほかの家族から受ける暴力や貧困、過去のトラウマ、またさまざまな要因からくる“生きづらさ”により身の回りにある逃げ道が見えないところまで追いつめられ、孤立してしまう親がいるのです。
「2010年に発生した大阪二児置き去り死事件では、加害者となった母親が子どもたちをマンションの一室に50日間放置して男性と遊んでいたことが大きな注目を集めました。取材をして見えてきたのは、母親は幼い時のネグレクト体験や、14歳のときに性被害に遭ったことなどで病理性を抱えていたこと。その上で人生を通じて『男性に頼る』ということしかサバイブする術を見つけられずにいたことでした。
子どもがいながら窮地に立たされた彼女は、男性に頼って生きていくという逃げ道しか見えず、公的な機関に救いを求めるという方法が見えなかったのではないか。追い詰められるとメンタルヘルスはとても悪化します。事実だけを見ると母親に悪意があったとも捉えられますが、私の目にその苦しさは、満州から逃避行を行っていた女性たちが抱えていたものと重なりました。まるでこの大阪事件の母親だけが、戦地に難民となって子どもと共に取り残されているようにも見えるわけです」
遠矢被告が吐露した胸中にみる、社会に根付く価値観

6月11日名古屋地裁では、遠矢被告が法廷で「献立が立てられず、自分にはあまり教養がないと思うことなどがありこんな母親でいいのかという気持ちでした」と胸中を吐露しました。この言葉は、社会に深く根付く“ある価値観”を表すものだと杉山さんは語ります。
「児童虐待事件の報道では、加害者が『怪物のような恐ろしい親』として伝えられます。このように、あたかも“異常な個人”が諸悪の根源であるように描く理由のひとつは、報道というものの背景に『社会正義』があるからです。それはつまり社会が考える“正しさ”であり、多数派のための価値観のこと。
しかしこれは必ずしも、女性や貧困家庭などの社会的弱者のための正義とはいえません。今回の事件で遠矢被告が法廷で語った言葉は、まさに『母親だったら子育てができて当たり前』というような、社会が思う母親像に自分がフィットできなかった生きづらさを表しています」
社会的正義に適応できない生きづらさを抱えるのは、もちろん女性だけではありません。目黒女児虐待事件では、加害を行っていた父親自身が、幼少期に実父から暴力を受け、中学時代にはいじめのような体験をし、社会人になってからは不適応を起こしつつ働いていました。
「彼はわが子に“しつけ”と称してダイエットなどを強制し、約束が守られないと“反省文”を書かせていたなかで『俺のような思いをさせたくないから』と言っていたそうですが、その自己肯定感の低さは、彼のトラウマからくるものでしょう。
報道では、彼がどれだけ異常で悪人かということが伝えられても、弱さについては触れられません。あくまでこれは私の考えですが、加害者の弱さについて報道が避けられる理由は、『我々も同じ状況に置かれれば、同じことをしうる』という可能性と向き合うことへの恐怖や忌避からではないでしょうか」
配信: 女子SPA!