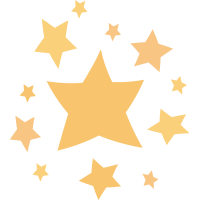どんなに好きな人と結婚できても、恋愛感情は一生続かない。恋愛感情を失った夫婦は破綻するかもしれないし、さもなければ「友達」に近づいていく。それならば、結婚よりも、気心のしれた友達と「家族」になってしまえばいいのではないか。
『たぶん私たち一生最強』(新潮社刊)は、こんな一見突飛な思いつきから、4人の女性たちが「家族」として暮らしていくことを決める。学生時代からの仲良し4人組。一緒に暮らせば絶対楽しい。しかし、果たしてそれはバラ色の日々なのか?気心しれた友達と「家族」になることは、「幸せを自らつかみにいくこと」なのか、それとも「結婚」や「出産」といった女性としての幸せを「早々に放棄すること」なのか?
結婚や出産、家族といった人生の大トピックについての価値観を揺らすこの作品がどのように構想され、書き上げられていったのか。作者の小林早代子さんにお話をうかがった。今回はその後編だ。
小林早代子さんインタビュー前編を読む
■女性の「気づかいスキルの高さ」が息苦しいことも
――女性4人で「家族」として一緒に暮らす、というのは人によっては「こんな選択肢もあるんだ」という希望になりえます。ただ、この作品は仲良しの4人で一緒に暮らす楽しさだけでなく、それぞれが抱える葛藤や悩みも書かれていて、誠実だと思いました。先ほど「ルームシェアものが好き」というお話がありましたが、「こんな話にしたい」というような狙いはあったのでしょうか。
小林:「こういう共同生活は自分にはいらないな」と感じる側からの視点も入れたかったのはあります。最後の一篇は4人を間近で見てきた子どもの話なのですが、彼女は男の人が好きだし、一緒に暮らしたいと思えるような友達もいません。それもあって、4人の共同生活を近くで見ていながらも、「女同士の暮らしは自分には向いてないな」と思っている。
共同生活をしている花乃子、百合子、澪、亜希って、ベースとして「それなりに恵まれている者たち」なんですよ。みんな普通に仕事をしていて、東京で一人暮らしができる程度には自立しているし、大学も出ていて親しい友達もいる。DVを受けた過去があるとか、親が毒親だといったこともありません。
それもあって、書きながらちょっと白けている自分もいたんですよね(笑)。それぞれに悩みはあるけど、その悩みだって「基本的にうまくいっている人の悩み」なので。そんな意識もあって、最後の一篇で彼女たちを一歩引いた目で見る話を書きました。
――最終話のラストはすごく印象的でした。
小林:ありがとうございます。『たぶん私たち一生最強』っていう元気なタイトルにしましたが、タイトルが想起させるほど明るさ一辺倒の話でもないのかなと思っています。アラサーの女性の多くが経験するしんどさについてもたくさん書いていますし。
私はただ、男の人と結婚や出産をする「幸せっぽい」ありふれたルート以外にももっと色んな可能性があることを示したかっただけで、「みんな今すぐ男なんか捨てて女同士で楽しくやろう!」って啓蒙したいわけじゃないんです。そういう意味では、ラストシーンは読者に委ねているようなところがあるかもしれません。
――「家族」としてではなくても、ルームシェア自体はさほど珍しいことではなくなっている現在ですが、他人との共同生活を円滑にやっていくためには何が必要なのかということもこの本を読んで考えさせられました。
小林:私の経験からいうと、女性って「気づかいスキル」がベースとして高いんですよね。会社員だった時は女性が多い部署にいたこともあるんですが、「気づいた人がやる」系のタスクがほとんど溜まらないんです。職場内に「気の利かない女性社員と思われるわけにはいかない」というプレッシャーがあったりするので。
そういうのが根付いている人たちだと、共同生活がうまく回ると思うんです。ルームシェアものって、男を取り合うとか家事で揉めるとかがありがちなのですが、実際にはそんなことはあまり起こらないんじゃないかと思って書きました。私としては、そういう女性の気づかいスキルの高さを快適だと思いつつ息苦しくもあるのですが。
――どういったところが息苦しいんですか?
小林:私自身はそういう気づかいが苦手な方なので、女性同士で一緒にいて食べ終わったお皿を下げてくれたり、ドアを開けてくれたり、気の利いた手土産をくれたりすると「そんなのどこで習ったの?」って思うんですよね。そういうのって単純に性格がいいだけじゃなくて、みんなどこかで習得しているんですよ。それで自分だけが役立たずに思えて情けない瞬間があるんです(笑)。
――そういうことも含めて、この本は共感する女性が多いと思います。
小林:そうだと嬉しいです。同世代の女性、もしくはアラサーになる前の女性が感じる独特の息苦しさを経験している女性に読んでほしいと思っているのですが、女同士の共同生活は自分には向いてないと思う人とか男性からも良い感想をたくさん頂いているので喜んでいます。
――20代の女性が感じる息苦しさとはどのようなものなのでしょうか。
小林:私自身、20代だった当時はそんなに苦しいとは思っていなかったのですが、30代になった今思い返すと、やはり見えないプレッシャーを感じていたように思います。
結婚ひとつとっても、自分が本当に結婚したいのか、子どもが欲しいのかまだはっきりわかっていない段階で「35歳以上の初産は高齢出産になるから、子どもを産む選択肢を残すなら、それまでに産まないといけない。となるといつまでに結婚して、いつまでに夫になるべき人と知り合って」という逆算を強いられている感覚はありました。そういうのが今思うと女性特有の息苦しさだったなと思います。
でも、家族になってもいいと思えるほど仲のいい友達がいるならば、必ずしも結婚する必要はありません。子どもが欲しいならそこだけ「外注」するという選択肢もあるよ、という気持ちで中盤以降のお話は書いています。
――最後に読者の方々にメッセージをお願いいたします。
小林:この作品を読んで「生きていくためにこういう選択もあるんだ」と、今より少しでも自由な視点を持ってもらえたり、心が軽くなったりしてもらえたらうれしいです。
(新刊JP編集部)
小林早代子さんインタビュー前編を読む
配信: 新刊JPニュース