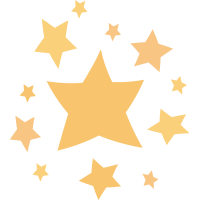「男は一家の大黒柱であるべきだ」「男は仕事、女は家庭」など、前時代的な“男らしさ”に苦しめられる40、50代の中年男性はいまだに少なくありません。

2004年に『野ブタ。をプロデュース』(河出書房新社)で作家デビューし、2018年に三人の男性それぞれの生きづらさを男性目線で綴った『たてがみを捨てたライオンたち』を上梓した作家の白岩玄氏(41歳)もまた、こうした“男らしさ”の呪縛に苦しめられたひとり。彼が、初めて生きづらさを感じたのは20代半ば頃だったといいます。
“男らしさ”に向き合えるようになった妻の言葉
「作家としてデビューして色々なテーマを扱う中で、漠然とした生きづらさを覚え、男性の心の内を書きたいという欲求が芽生えてきました。ですが、実際に文章にしようとしても、その生きづらさの正体が何なのか、うまく言葉が出てこない。そればかりか、自分の中で頑なに『書くんじゃない』と首を横に振るもう一人の自分が居て、どうしても書き進めることができなかったんです。
自分の弱さに向き合うことに抵抗があったのか。それとも、男性は強くなくてはいけないという価値観が幅をきかせている日本社会において、弱い自分を他人に見られるのが嫌だったのか。あるいは、女性の居場所を奪っているかもしれない自分にメスを向けることに恐怖を覚えたのかもしれません」
書きたいのに、書けない。そうしたジレンマに苛まれた白岩氏が自身を縛る“男らしさ”に向き合えるようになったきっかけ、それが「妻との対話」でした。
「僕自身、収入が不安定なことで妻との結婚を躊躇したこともあるし、妻の稼ぎが安定していることに劣等感を感じたこともあります。
ですが、『女だから、男だからこうあるべき』といった性役割にこだわりがなかった妻が、『できない部分はお互いが助け合って補えばいい。男性だからといって稼ぐべきだなんて思わない』という言葉をかけてくれた。夫婦で協力して生活していくことができれば、別にそれで何の問題もないんだなと思えるようになり、そういったところからも自分の弱さを少しずつ見せられるようになっていきました」
自分のなかに社会が望む“男らしさ”が形成されていく
自身の首を絞め続ける、漠然とした生きづらさの正体とは――。知らないうちに纏うようになっていた「男性」という鎧を一つひとつ脱ぎ捨てていくと、幼少期から青年期の原体験に辿り着いたという。
「『男は泣くな。辛くても歯を食いしばって耐えろ』と、父親からは口酸っぱく言われましたし、『男の子が母親に甘えるなんてマザコンだ』『スポーツができる方が男らしい』など、周りの大人たちからも、らしさの押しつけを受けてきた。そうした積み重ねによって、自分のなかに社会が望む“男らしさ”が形成されていき、いつの間にか『男たるもの』が紐づいた感情と思考に支配されていきました。
その結果、僕の場合は、悲しみや不安や戸惑いといった、自分に不都合な感情に襲われると、そうした感情に蓋をして抑圧するか、あるいは、誰かにマウントすることで、偽りの自信を得ようとする傾向があることに気がついたんです。
それは夫婦関係にも影響していて、妻との関わりの中でも、自分が不都合な感情に襲われたときは、それに蓋をして心の内を見せないように壁を作ったり、喧嘩をした際に相手を論破しようとするようなところがあったんです。これでは夫婦関係なんて到底作っていけないなと思い、それ以外の対処法を見つける努力をしたのですが、なかなか難しく……。
今でもこれという方法は見つかっていないのですが、抑圧したり、ごまかそうとする前の感情、たとえば「悲しかった」とか「不安だった」とか、そういう自分の弱さを認めるような言葉を、あとになってでもいいから伝えるようにはしていますね」
配信: 女子SPA!