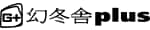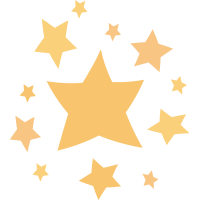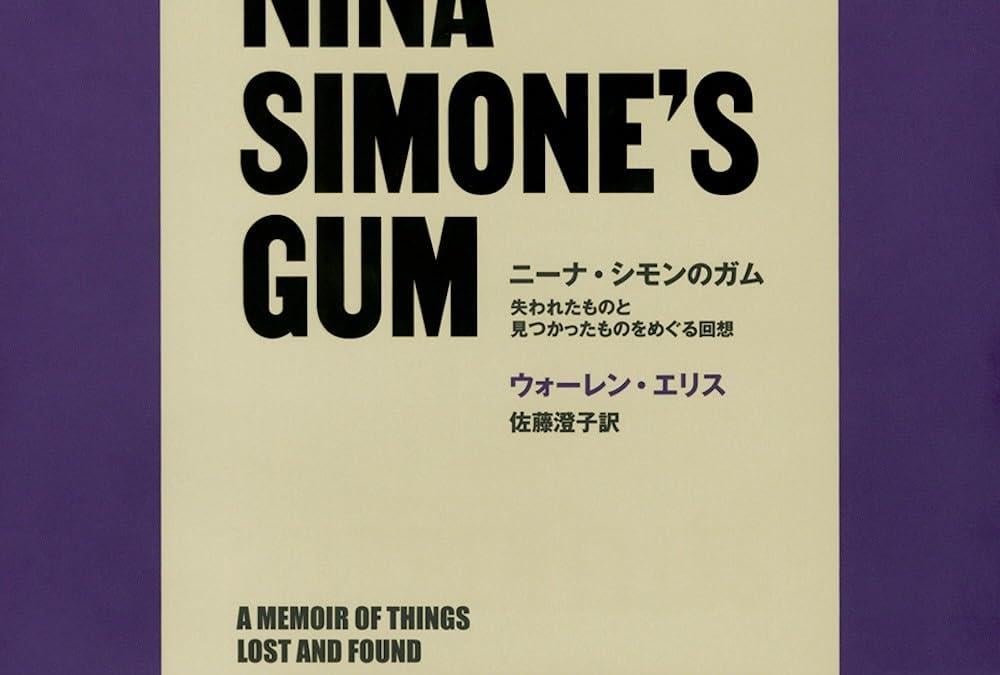伝説的なミュージシャンであるニーナ・シモン。一九九九年、その最後の公演となったロンドンでの演奏後、本書の著者であり、彼自身にもまた熱烈な支持者がいるというミュージシャン、ウォーレン・エリスは必死の思いで舞台に這い上がった。なぜなら、演奏を始める直前、ニーナが口から出したガムを無造作にスタインウェイのピアノにつけたのを見ていたからだ。ピアノの上に置かれたままになっていた、ニーナが汗を拭った白いタオルでそのガムを包んで、ウォーレンは持ち帰る。途中手に入れたタワーレコードの黄色いビニール袋に入れ、そのままの状態で二十年も他人の目に触れないところに仕舞っていた。
2020年6月、そのガムがデンマーク王立図書館で開催される展覧会で展示されることになる。金色のベルベットの布が敷かれ、大理石の台座が据えられたショーケースの中で、ニーナ・シモンのガムはスポットライトを浴びたのだ。本来は捨てられるべきもの、あるいは失われるはずだったものが、なぜ信仰の対象、つまり聖遺物のような存在になったのか。
本書では、その驚くべき経緯がウォーレンと彼に関わった人々の声とともに語られる。音楽マニアであれば、ここまでの話だけで心酔するのかもしれない。ところが私のように熱心なファンでなくても、読み進めるにつれてページを捲るその手が止まらなくなった。というのもウォーレンの人生にとって、ニーナのガムの存在があまりに大きいことに圧倒されるからだ。「僕のすべての創作活動を1999年から見守ってくれたガム」は、他の人間にはただのゴミである。けれど彼にとっては、決して失われてはならないものなのだ。
だからこそ、展示のために自身のもとからガムを手放すことはウォーレンにとって決死の覚悟が伴った。もしもに備えてレプリカを作ることとなり、ガムを持ってジュエリーデザイナーのハンナに会いにいく。二人のやりとりの緊張感は読者の胃まで締め付けるようなもの。そしてその強烈な緊張はニーナのガムに関わる人々が一様に味わうことになる。ちなみにハンナはガムにまつわる何ヶ月かの仕事を終えると、母親に腎臓のひとつを提供するためにロンドンからニュージーランドへ旅立っていく。なぜかニーナのガムと因縁があるように思えるのは、ガムのかたちが腎臓か心臓を想起させるからか。しかしその時のハンナにとって、腎臓を失うことはできても、ニーナのガムはすでに失うことのできないものになっている。
持ち主の手から離れようとするニーナ・シモンのガムが、ウォーレンの“信仰”を宿しながら展示に向けて人から人へ渡っていく。ものに宿る人の強い思いは、なんと偏ったもので、なんと強烈なのだろう。ピアノにつけられたガムをめぐる物語は、不思議な引力を持っていた。
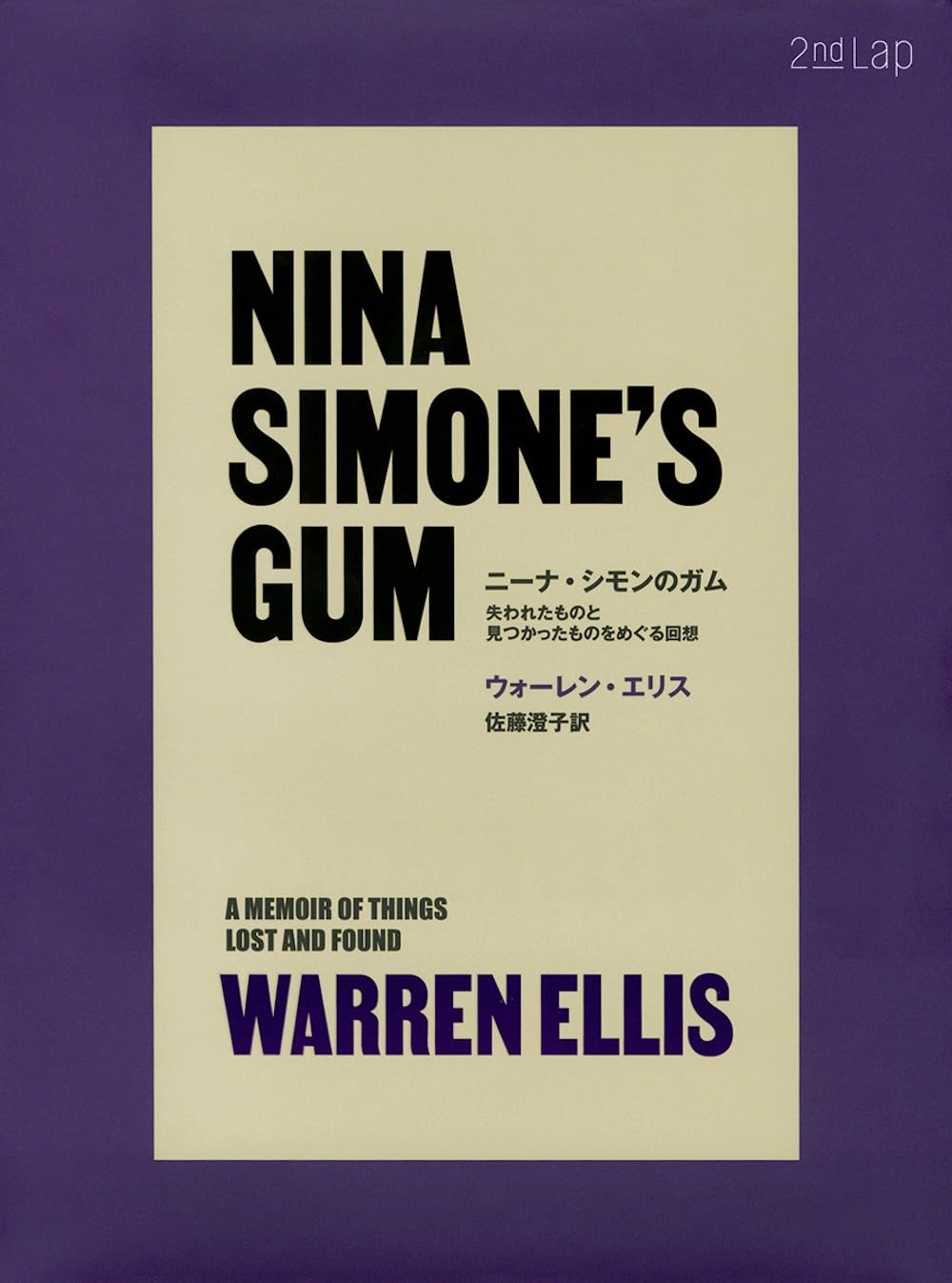
ウォーレン・エリス『ニーナ・シモンのガム 失われたものと見つかったものをめぐる回想』
- Amazonで購入
- 楽天ブックスで購入
ロンドンの最後の公演でピアノの上に置かれたガムが、二十年を経てデンマークで展示されることになる。その“奇跡”についての証言集。
配信: 幻冬舎Plus
関連記事: