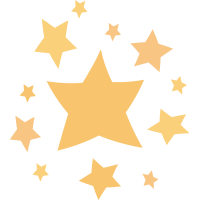大阪地検トップの検事正が部下に性暴力したとして準強制性交罪に問われた事件。検察を揺るがす大不祥事にもかかわらず、被害から6年が経ってから表面化した。
2010年に発覚した大阪地検特捜部の主任検事による証拠改ざん事件で検察への信頼は大きく低下したが、近年も強大な権限を持つ組織の様々な問題が噴出している。
不正義を許さない志を持った人たちが集まるはずの組織で、なぜこうしたことが起きるのか。元検事で自身の検察官時代の過ちを著書で告白したことがある市川寛(ひろし)弁護士は「検察はもともと制度的にハラスメントが起きやすい」と話す。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

●「お尻を触ったこと自体が早く上層部に伝わるべきだった」
事件は2018年9月に起きた。報道によると、大阪地検の検事正だった北川健太郎氏は職場の懇親会が終わった後、酒に酔った部下の女性検事を官舎に連れ込んで性的暴行を加えたとされる。
しかし、この加害行為を伏せた状態のまま定年まで3年を残しながら2019年11月に退官し、弁護士として活動していた。そんな中、今年6月に大阪高検が準強制性交の疑いで逮捕。
10月に大阪地裁で開かれた初公判では、北川氏が被害者の女性に「これでお前も俺の女だ」「時効がくるまで食事をごちそうする」などと話していたことが明かされた。
「大阪地検の検事正で辞めたということがそもそも不思議でした。今になってみると、その時点で何かしらけじめをつけるために辞めたのだろうなと思います。大阪地検の検事正は、その多くが大阪高検の検事長になれるという絶対的なポストなのです」
そう話すのは元検察官の市川弁護士だ。1993年検事任官後は横浜地検、大阪地検、佐賀地検などで勤務。2005年に辞職し、2007年に弁護士登録した。
市川弁護士は佐賀地検の三席検事だった時に検察内部の研修で、当時大阪地検特捜部の検事だった北川氏に会ったことがあり、「悪い印象は全然なかった」という。そのうえで事件の衝撃を次のように振り返る。
「検事正にまでなった後に、まさかこんな事件を起こしていたとは思わなかった。報じられた話を見ると、人を人だと思っていないからできるのでしょう。人間扱いしていない。部下を物だと思っている。でないと、いくらなんでもあんなことはできないと思います。一体今までどういう感覚で仕事をしてきたのでしょうか。そのあたりのことも裁判で本人に話してもらいたいと思います」
被害者の女性検事は初公判後に開いた記者会見で、北川氏が他の女性検事のお尻を触っていたという話を耳にしたことがあったとも明かした。
この点について、市川弁護士は「本来はその時点でアウト。女性のお尻を触るという行為自体、もっと早く組織の上層部に伝わって然るべきでした。検察にも内部通報の窓口はありますが、機能していないという話も聞きます」。

●ハラスメントを生む「検察システム」の宿命
検察で相次ぐ不祥事。市川弁護士はその背景に「検察庁法の相反する規定」があると説明する。
それが、個人個人の検察官が独立して職務を遂行する「独任制官庁」という制度と、各検察官は上司の指揮監督に従わなければならないという「検察官一体の原則」だ。
つまり、検察官には、起訴するかどうかを単独で判断する権限があるとされている一方、その判断を実行するためには上司の検察官の決裁が必要になるという特徴があるというのだ。
「検察は原則としてチームプレーで動くので、どうしてもリーダーと部下という仕組みになりやすい。独任制官庁と言っても部下は上司の言うことを聞かなければなりません。検察庁のシステムとしての宿命ですが、この制度そのものが危うい。そもそもハラスメントが生じやすい素地を持っているのです」
被害者の女性検事がすぐに被害を申告できなかった理由には、北川氏から「(性加害が)公になれば私は生きていけない、自死を考えている」「検察庁に大きな非難の目が向けられ、業務が立ち行かなくなる。総長の辞職もありえる」「私のためでなく、あなたの愛する検察庁のため告発はやめてください」などと伝えられていた事情もあったとされる。
これに対して、市川弁護士は大阪地検を含む「関西検察」にあるという特有の文化を踏まえて、こう説明する。
「検察は一般の人が思っているより何倍も閉じた世界です。外からの批判に耳を傾ける素地がない。中でも関西検察は家族的な雰囲気があり、さらに閉じています。現職の時から検察OBと飲み会をしている検事も多い」

配信: 弁護士ドットコム